 世帯・住宅
世帯・住宅 無職世帯の子ども数の推移と地域差―18歳未満人員の実態と課題
2018年から2025年までの家計調査によると、無職世帯における18歳未満の平均人員数は全国で0.04人と極めて少なく、少子高齢化の進行や無職世帯の高齢化が浮き彫りになっています。都市別に見ると、地方圏の一部で子育て世帯が残る傾向が見られる...
 世帯・住宅
世帯・住宅 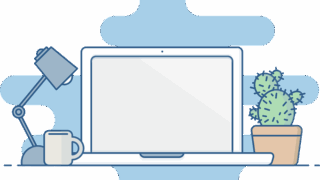 世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅  世帯・住宅
世帯・住宅