家計調査によると、勤労世帯の肉類支出額は地域で大きく異なり、京都市や川崎市で高く、甲府市や福井市で低い傾向が見られた。都市部では外食志向や高品質志向、また高齢化や単身世帯の影響もあると考えられる。一方、地方都市では節約志向や物価感応度が強く出ている。今後は物価上昇や健康志向の高まりにより、支出の質的変化が進むと予測される。地域や世代による消費スタイルの違いがより顕在化していく可能性が高い。
肉類(勤労)の家計調査結果
肉類(勤労)の多い都市
肉類(勤労)の少ない都市
これまでの肉類(勤労)の推移
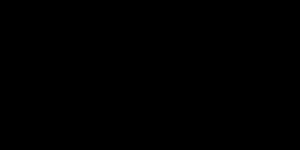
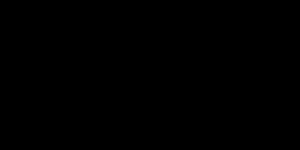
詳細なデータとグラフ
肉類(勤労)の肉類現状と今後
家計調査における「勤労世帯」とは、主に現役で働く世帯(特に会社員・公務員など)が属する層であり、食費の構成比やライフスタイルにおいて非勤労世帯(高齢者中心の世帯)とは異なる動きを見せるのが特徴です。2025年3月時点で、勤労世帯の肉類への平均支出は8,816円であり、これまでと比較しても比較的高水準にあります。
2000年代以降、家庭での調理から中食(惣菜)・外食へと志向が移行しつつある中でも、肉類は栄養価・満足感・調理の汎用性から消費が根強く、特に共働き世帯の増加が肉類消費の底上げに寄与してきました。
肉類支出が多い都市の特徴
京都市(12,350円)が圧倒的に高く、川崎市、堺市、長崎市、広島市といった政令指定都市が続きます。特に注目すべきは京都市の+41.07%という急激な伸びで、これは物価上昇だけでなく、和牛・地元産ブランド肉の購入増加、観光再開による外食気運の高まり、生活水準の高い層の消費回復が影響していると考えられます。
また、川崎市(+35.12%)や大阪市(+10.7%)など都市部では、冷凍肉や量販スーパーでのまとめ買いよりも「近場の高品質商品」「外食代替的な高価格惣菜」への支出傾向が見られる可能性があります。
肉類支出が少ない都市の特徴
1方、甲府市(6,316円)を筆頭に、水戸市、前橋市、福井市、福島市など地方中核都市では全国平均を大きく下回る支出額が見られます。とくに甲府市(-29.07%)や福井市(-23.04%)では顕著な支出減少が観察され、これは
-
食品全体の節約志向
-
家庭菜園・地元産物利用の活発さ
-
高齢化進展による消費縮小といった地域的特性が影響していると考えられます。
また、これらの地域では家族構成が高齢者中心や単身世帯の割合が高く、肉類そのものの摂取量が減っている可能性も高いです。
世代別に見る肉類消費の変化
若年〜中年層(30~50代)では、筋トレ・健康志向のブームにより「高タンパク・低脂質」な鶏肉や赤身肉を中心とした積極的な消費が続いています。とくに男性を中心に「プロテイン食品の代替」として肉を選ぶ例も増加しています。1方、高齢層では「咀嚼の負担」「コレステロール懸念」「食欲低下」から肉類摂取を避ける傾向が見られ、世代間での需要ギャップが広がっています。
今後の見通しと課題
今後、勤労世帯における肉類支出は次のような傾向をたどると予想されます:
-
物価高による単価上昇:特に輸入肉の価格が円安や輸送コスト増で今後も高止まり。
-
量から質への移行:鶏むね肉や赤身牛肉、国産志向など「健康」や「安心」を重視する選択にシフト。
-
惣菜・ミールキットの活用:家庭調理の簡素化と時間短縮志向により、家庭内消費の形が変化。
-
地域格差の固定化:都市部では外食代替的な「高付加価値支出」が増え、地方では節約型購買が継続。
また、食肉業界としても環境対応・サステナブル畜産への転換が求められ、価格上昇をどう抑えるかが課題となるでしょう。
まとめ
勤労世帯における肉類支出の動向は、経済状況や都市の社会構造、世代特性を色濃く反映しています。都市部と地方のギャップは今後ますます広がる可能性があり、消費の2極化も進行中です。「高くても良いものを少し」か「安くて量を確保」か――。それぞれの選択が支出データに映し出されており、日本の暮らしのリアルな姿が肉類支出から垣間見えます。




コメント