2025年3月時点の家計調査によると、二人以上世帯での乳製品の月間平均支出は2,088円。さいたま市や仙台市など都市部を中心に支出が高い一方、和歌山市や北九州市などでは低水準にとどまる。増減傾向には地域差が大きく、物価や生活スタイル、世代構成の違いが背景にある。今後は高齢化や健康志向の影響、さらには物価上昇の継続などが、消費動向を左右する可能性が高い。
乳製品の家計調査結果
乳製品の多い都市
乳製品の少ない都市
これまでの乳製品の推移
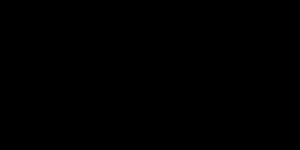
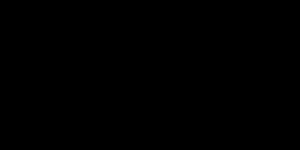
詳細なデータとグラフ
乳製品の肉類現状と今後
2008年から2025年3月にかけて、乳製品支出は緩やかながらも上昇傾向を示してきました。特に2020年以降、新型コロナウイルスの影響で家庭内消費が増加し、外食よりも家庭調理や健康意識を反映した食材への支出が伸びました。乳製品もその1環として需要が拡大し、2025年時点での全国平均は2,088円と堅調に推移しています。
1方、物価高や円安、原材料費の上昇により、小売価格が上がっていることも平均支出額を押し上げている要因の1つです。実質的な「量」ではなく、「価格」による上昇も無視できません。
都市間の支出格差とその背景
支出が多い都市では、さいたま市(2,790円)、仙台市(2,615円)、福島市(2,571円)が上位に並びます。これらの都市に共通するのは、比較的都市インフラが整い、世帯所得も高めであること。また、子育て世帯や中間所得層の比率が高く、健康意識の高い家庭が多い点も関係していると考えられます。
特筆すべきはさいたま市の+27.57%という急上昇で、これは家計の見直しや健康意識の高まり、もしくは価格転嫁の影響を反映している可能性が高いです。逆に、和歌山市(1,177円)や北9州市(1,501円)などでは消費額が低く、これは高齢化率の高さや世帯所得の低さ、あるいは都市機能の縮小が背景にあると見られます。
世代別の乳製品消費傾向
世代間で見ると、以下のような傾向が見られます:
-
子育て世代(30〜50代):育ち盛りの子どもがいるため、牛乳・ヨーグルト・チーズの消費が多く、支出も高くなる。
-
高齢世代(60代以上):健康維持を目的にヨーグルトやチーズを選ぶものの、全体的な摂取量は少なめ。物価上昇に対しても節約志向が強い。
-
若年単身世代:2人以上世帯の統計には含まれないが、乳製品消費の中心がヨーグルトやスムージーなどの“手軽な健康食”に偏る傾向があり、従来型の牛乳消費は減っている。
問題点と課題
-
地域間格差:食文化の違いに加え、物流コストや販路の集中/分散によって、乳製品の価格や入手性が大きく異なっている。
-
高齢化の影響:高齢化が進む地域では、乳製品の消費そのものが縮小傾向にある。また乳糖不耐症に悩む高齢者層の増加も、消費抑制要因となる。
-
国内酪農の不安定化:原材料高騰や生産者離れにより、国内生産が不安定化し、将来的な価格上昇リスクが内在している。
今後の予測と展望
今後の乳製品支出は以下の3つの要素に左右されると予測されます:
-
物価と収入のバランス:実質賃金が伸び悩む中、今後も物価が上がり続ける場合、乳製品は節約対象になる可能性があります。
-
健康志向の高まり:プロバイオティクスやカルシウム摂取を目的とした乳製品(機能性ヨーグルトやチーズなど)の消費は引き続き堅調と見込まれます。
-
地産地消とブランド化:地域ごとの乳製品(例:北海道産チーズや長野県のヨーグルトなど)が付加価値商品として選ばれ、支出額に影響することも考えられます。
まとめ
乳製品の家庭支出は、都市規模や世帯構成、健康意識、さらには物価変動の影響を受けながら、今後も2極化の傾向が続くと考えられます。とくに都市部では高価格帯乳製品の需要が伸びやすく、地方ではコスト意識が消費を抑制する力として働いています。消費者ニーズの多様化と、酪農業界の安定供給体制が今後の大きな鍵となるでしょう。




コメント