家計調査によると、2025年3月時点での二人以上世帯の生鮮果物支出は月平均3,016円。奈良市や横浜市では支出が高く、青森市や北九州市では低い傾向がある。都市間では経済力や健康志向、流通環境が影響し、世代間では高齢者ほど支出が多い傾向が続く。今後は高齢化や物価高、生活様式の変化により、果物支出の地域差・世代差はさらに拡大する可能性がある。
生鮮果物の家計調査結果
生鮮果物の多い都市
生鮮果物の少ない都市
これまでの生鮮果物の推移
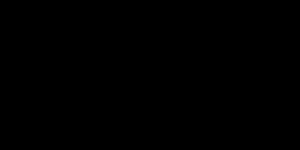
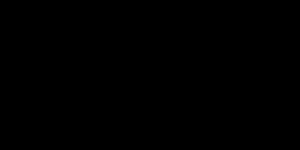
詳細なデータとグラフ
生鮮果物の果物現状と今後
日本の家計における生鮮果物の支出は、長期的には減少傾向から横ばい、そして近年は再び微増傾向に転じている。背景には以下の要素がある:
-
少子高齢化:若年層の果物離れと、高齢者の健康志向による需要の2極化。
-
価格の上昇:天候不順や人手不足による果物価格の上昇。
-
ライフスタイルの変化:簡便な加工食品へのシフトと、食への関心の多様化。
2008年から2025年までの家計調査を通じてみると、果物支出の中でも生鮮果物は特に高齢層の食生活に根強く残っており、平均で約3,000円前後を推移している。
都市間の支出格差の背景
支出の高い都市(奈良市、横浜市、富山市など)と、低い都市(青森市、北9州市、熊本市など)では、主に以下の点で違いが見られる。
高支出都市の特徴:
-
高齢者人口の割合が高く、健康意識が強い地域(例:奈良、京都)
-
購買力が高く、価格への感度が比較的低い都市(例:横浜、東京都区部)
-
交通網と流通が発達しており、新鮮な果物が手に入りやすい(例:さいたま、相模原)
低支出都市の特徴:
-
所得が低く、生活費に占める果物支出の優先度が下がる(例:北9州、青森)
-
果物の栽培地域であり、自家消費が多い傾向も(例:熊本、和歌山)
-
若年層の比率が高く、果物消費の習慣が薄い地域(例:静岡、高知)
支出格差は物理的な流通の問題だけでなく、文化的・社会的背景や食の価値観の違いにも基づいている。
世代間の果物消費の特徴
生鮮果物の支出は、高齢世代ほど多く、若年世代ほど少ない傾向が続いている。理由は以下のとおり:
-
高齢者は医療・健康維持のため果物を習慣的に摂取。
-
中高年は料理習慣があるため、果物も日常的に購入。
-
若年層は価格や調理・皮むきの手間から敬遠しがち。
加えて、果物をおやつ代わりに摂る文化や、昔ながらの家庭食が残っているか否かも大きな違いを生む。たとえば、定年退職後の世代は「手間を惜しまない」層であり、果物を自ら切って食べる習慣を持つが、20〜30代では「そのまま食べられる加工品」の方が人気となっている。
消費増減の背景にある社会的要因
生鮮果物の支出が増加している都市と減少している都市を比較すると、以下のような傾向が読み取れる:
増加の背景:
-
高齢人口の集中(奈良、富山)
-
高所得・教育水準が高く、健康意識が強い(横浜、京都)
-
スーパーマーケットの利便性向上や、生産者直売所の人気
減少の背景:
-
若年層の増加(青森、静岡)
-
可処分所得の減少と物価上昇による家計の節約志向
-
コロナ禍以降の生活リズムの変化と内食傾向の縮小
都市によっては、果物が「ぜいたく品」として見なされる傾向が強まっており、家計に余裕がないときには真っ先に削られる支出にもなっている。
今後の予測と課題
今後の生鮮果物支出については、以下のような動向が予想される:
-
高齢化の進行により、果物支出は高水準で維持される地域が続出。
-
若年層の果物離れが進行し、全体としては横ばい〜微減の可能性。
-
果物の加工・即食需要(カットフルーツ、冷凍フルーツなど)が拡大し、支出構造も変化。
-
地域格差は広がる1方で、地産地消や教育を通じた果物の魅力再認識運動が鍵となる。
さらに重要なのは、価格高騰や輸入果物への依存度の高まりによる国内生産とのバランスの問題である。将来的には、「日常果物」から「特別な果物」への位置づけが再定義される可能性もある。
まとめ
生鮮果物の支出は、日本人の生活様式・価値観・経済状況を反映した鏡である。高齢者中心に支出が維持されている1方で、若年層の習慣や地域経済によってその姿は大きく変わりつつある。将来的に果物の消費を持続可能にするためには、地域間格差の是正や若年層への果物習慣の啓発が欠かせない。




コメント