無職世帯におけるガス代は、2025年3月時点の全国平均で月額6,723円と、光熱費の中でも特に地域差が大きい項目です。高齢者中心の無職世帯では、暖房や調理にガスを多く使用し、寒冷地や都市ガスの普及率が低い地域では支出がかさみがちです。また、高齢者は機器の更新が遅れがちで、省エネ型への移行が進んでいません。将来はエネルギー価格の変動や生活支援策の拡充により、支出に地域差がさらに拡大する可能性があります。
ガス代の家計調査結果
ガス代の多い都市
ガス代の少ない都市
これまでのガス代の推移
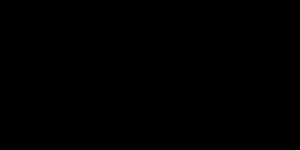
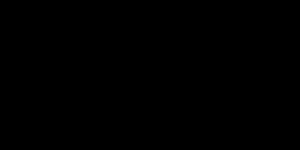
詳細なデータとグラフ
ガス代の現状と今後
ガス代は、光熱費の中でも調理・暖房・給湯に直結し、無職世帯にとって生活の質を左右する重要な支出項目です。特に高齢者の単身・夫婦世帯においては、在宅時間が長くガス使用頻度も高いため、その動向は家計への影響が大きくなります。
ガス代のこれまでの推移と背景
2018年から2025年までのガス代は、エネルギー市場の動向や円相場の影響、そして国際的なガス供給不安定化の影響を受け、断続的に上昇してきました。特に2022年以降、LNG(液化天然ガス)価格の高騰が都市ガス料金に反映され、都市部を中心に負担感が増しています。
加えて、プロパンガス地域では都市ガスより割高な料金体系が多く、地方を中心にガス代が高止まりしています。
地域間格差の要因
都市別に見ると、ガス代が高いのは寒冷地・山間部・離島などが多く、主に以下の理由が挙げられます:
-
暖房・給湯にガスを使用する頻度が高い(冬季が長い)
-
プロパンガス依存地域で料金競争が限定的
-
建物の断熱性能が低く、ガス機器効率が悪い
1方、都市ガス網が整備された都市部では、ガス代が抑えられる傾向にあり、加えてIHクッキングヒーターや電気温水器などへの切替が進んでいる地域では、ガス使用量が減少傾向にあります。
無職世帯・高齢世代の特性と問題
無職世帯、とりわけ高齢者層には以下のような特徴があります:
-
冬場に暖房としてガスファンヒーターを使用する割合が高い
-
台所でガスコンロを使う習慣が根強い
-
機器の老朽化や、省エネ意識の浸透の遅れ
これらにより、他の世帯層と比較してガス使用量が減りにくい傾向にあります。さらに、高齢世帯は新技術への適応が遅れる傾向があり、エコジョーズ(高効率ガス給湯器)などの導入率も低いのが実情です。
将来の見通しと政策的課題
今後、無職世帯のガス代は次の要因で変動する可能性があります:
-
再エネ政策の進行により、都市ガス価格が緩やかに上昇
-
災害対策やエネルギー安全保障上の観点から、プロパンガスの役割が再評価される
-
生活保護世帯や低所得高齢者世帯向けにガス代補助制度が拡充される可能性
加えて、国や自治体の住宅リフォーム支援や機器交換補助制度が、家計負担軽減につながる重要な鍵となります。
まとめ ― エネルギー支出の適正化に向けて
ガス代は、無職世帯の生活コストにおいて静かに家計を圧迫する存在です。都市と地方、都市ガスとプロパン、若年層と高齢層といった多様な分断があり、平均値だけでは実態が見えにくい項目でもあります。
これからの日本社会では、ガス代を「生活必需支出」として政策的に捉え、支援のあり方やインフラの整備方針を再構築することが求められます。生活の安心と環境負荷の両立をどう図るかが、大きな課題となるでしょう。




コメント