2025年3月時点の家計調査によると、勤労世帯の交通・通信費の全国平均は月6.917万円。地方都市では富山市(35.86万円)などで大幅な増加が見られ、自家用車利用や通信契約の影響が大きい。一方、都市部では公共交通網の発達や節約志向から、支出が安定もしくは減少傾向。世代間では若年層が通信費に重点を置き、高齢世代は移動手段の維持が負担に。今後は働き方や技術進化、地域交通政策によって支出構造がさらに変化する見通し。
交通・通信の家計調査結果
交通・通信の多い都市
交通・通信の少ない都市
これまでの交通・通信の推移
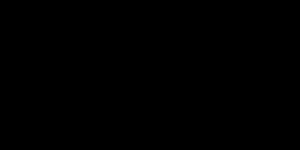
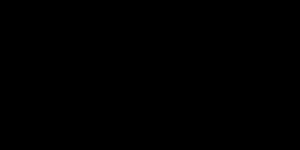
詳細なデータとグラフ
交通・通信の現状と今後
交通・通信費は、主に「通勤・通学や日常の移動手段にかかる交通費」と「携帯電話・インターネットなどの通信費」に分けられ、家計の中でも大きな固定支出の1つです。2000年からの長期データを見ても、通信費はスマートフォンの普及に伴い増加傾向、交通費は在宅勤務の影響で1時減少したものの、地域ごとの移動手段の違いから増減の差が顕著です。
地方と都市で大きく異なる支出構造
地方都市では自家用車依存が強く、車両の維持費や燃料費、保険料が家計を圧迫しています。たとえば富山市では35.86万円という突出した数字が出ており、前年から+582.6%と急増しています。これは1時的な購入費の集中や、ガソリン価格の高騰、通信プランの変更など複合要因によるものと推測されます。
1方で、神戸市(3.023万円)や横浜市(3.456万円)など大都市圏では、鉄道やバスといった公共交通機関の利便性により、自動車関連の負担が軽減されています。また格安SIMや通信費節約サービスの普及も影響しており、特に若年層では通信費をコントロールする意識が高まっています。
世代間の支出傾向と課題
世代によっても交通・通信費の支出には違いがあります。若年層(20~40代)はスマートフォンやSNS利用の比重が高く、通信費への支出割合が大きくなりがちです。1方、中高年層では通勤や業務用の移動手段として車を所有している世帯が多く、交通費がかさむ傾向にあります。高齢者世帯では、運転免許返納後の代替移動手段の確保が問題となりつつあり、地方では交通弱者化が進行しています。
通信費の負担増と政府の対策
通信費については、月額1万円を超える世帯も珍しくありません。格安スマホや光回線の競争が進んでいるとはいえ、家族全員がスマートフォンを持つ時代となり、子育て世帯では教育目的の通信環境整備(タブレット・Wi-Fi等)も支出に影響します。これを受け、政府は携帯料金の値下げ誘導や通信インフラの整備補助などの政策を打ち出していますが、効果は地域差があります。
今後の展望と変化の方向性
今後、リモートワークやサブスクリプション型の交通サービス(MaaS:Mobility as a Service)導入、5G・6G通信の普及が、支出構造をさらに変化させると見られます。公共交通の利用促進による都市部の交通費削減、自動運転技術による高齢者の移動支援、通信インフラの均等化による地域格差の縮小などが期待されます。とはいえ、地方における車依存の構造はすぐに変わるものではなく、燃料価格や税制動向も含めた支出増リスクは続く見通しです。
結語
交通・通信費は、地域のインフラと生活様式の反映であり、都市と地方、若者と高齢者で大きな違いを生みます。デジタル化と社会変化が進む中、家計への影響を見極め、効率的な支出管理と政策支援が今後ますます重要になるでしょう。




コメント