2020年~2025年の家計調査によると、無職世帯の持家における平均畳数は全国平均で40.3畳。小都市ほど住宅は広く、大都市では狭い傾向が続く。高齢世帯の多くは広い住宅に住む一方、都市部の若年層はコンパクトな住まいが中心。今後は住宅面積よりも快適性や利便性を重視する社会へとシフトしていく見通しです。
平均畳数(持家)の家計調査結果
平均畳数(持家)の多い都市
平均畳数(持家)の少ない都市
これまでの平均畳数(持家)の推移
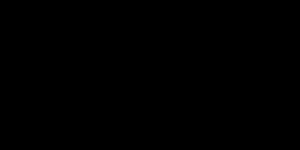
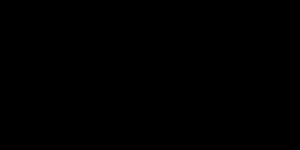
詳細なデータとグラフ
平均畳数(持家)の現状と今後
2020年11月から2025年3月までの家計調査によると、無職世帯における「持家」の平均畳数は全国平均で40.3畳となっています。これは、就労世帯と比べても住宅面積に大きな遅れが見られないことを示しつつも、地域差が如実に表れた数値です。
畳数の都市別順位:
-
小都市B:44.0畳(+7.317%)
-
小都市A:41.5畳(+0.242%)
-
中都市:39.4畳(-1.005%)
-
大都市:38.2畳(+1.867%)
このデータからも分かるように、小都市ほど住宅の広さに余裕があり、大都市ほどコンパクトな住宅が多いという特徴が現れています。
これまでの動向と住宅政策の影響
戦後から平成期にかけて、地方では土地価格が比較的安価であったため、広い戸建てを構えることが1般的でした。特に定年退職後に地方に住居を移す動きがあったことで、地方の無職世帯(主に高齢世帯)の住宅は平均的に広めです。
1方で、大都市では地価の高騰や住宅密集によって、世帯当たりの居住面積が年々縮小してきました。無職世帯であっても都市部に住み続ける場合、もともと狭いマンションや団地に住むことが多いため、畳数は少なめとなっています。
都市間の特徴と構造的な要因
小都市の特徴
小都市BやAのように、地価が安く、住宅地の広がりに余裕があるエリアでは、持家は広めに設計される傾向があります。また、こうした都市では、2世帯住宅や家族同居も依然として残っており、畳数が増える1因となっています。
中都市の特徴
中都市は人口集中と郊外化が進み、住宅の構造も中間的なものが多く、畳数にもそれが反映されています。今回のデータで唯1、前年同期からマイナス成長(-1.005%)を示したことからも、都市再開発や老朽住宅の取り壊しなどの影響がうかがえます。
大都市の特徴
大都市では、持家であっても集合住宅が主流となっており、個別の畳数は抑えられる傾向にあります。とはいえ、今回のデータでは+1.867%と増加傾向にあり、住宅再建やリフォームによって、居住空間が見直されていることも考えられます。
世代間の居住スタイルの違い
高齢世代(団塊・戦後世代)
持家の取得時期が1980〜1990年代に集中しており、当時の郊外型住宅ブームに乗って広めの1戸建てを建てた世代です。この世代の無職世帯が全体の畳数を引き上げる主因となっています。
若年・中年世代(40〜60代)
現在無職であっても、都市部に住むことを選ぶ世代は増えており、リタイア後も交通利便性を重視してマンション住まいを選ぶ人が増加中です。したがって、今後は畳数が縮小する方向へ向かう可能性もあります。
今後の予測と住宅政策の必要性
無職世帯の住宅環境は、今後ますます多様化する見通しです。特に以下のような傾向が予測されます:
-
都市部では畳数の微増または維持:高齢化とリフォーム促進政策により、居住空間の最適化が進む。
-
地方では横ばいまたは緩やかな縮小: 世帯人数の減少、空き家の増加、住宅の老朽化が影響。
-
中都市では減少傾向が継続する可能性: 更新投資が進まず、コンパクト化が進む。
また、高齢者向けのリフォーム助成制度や住み替え支援策の充実も、今後の住宅面積の動向に影響を与えると考えられます。
まとめと政策的示唆
無職世帯における平均畳数の推移は、その都市の歴史的経緯、地価、住宅供給政策、そして住民の価値観によって大きく左右されます。今後は住宅面積そのものだけでなく、「どのように快適に暮らせるか」を重視する方向に移行していくことが求められます。
政策としては、高齢者の住み替え支援や空き家活用、集合住宅でのバリアフリー整備など、畳数に代わる居住の質向上を目指した取り組みが重要です。




コメント