2025年3月時点で全国平均56.7%の女性配偶者の有業率は、都市や世代、地域文化により大きな差がある。富山市や金沢市など共働き志向が強い地方都市では70%を超える一方、福島市や東京都区部などでは50%未満にとどまる。世代交代や働き方改革の進展により、今後は都市部でも上昇の余地があるが、育児・介護負担や保育環境など社会的な支援整備が鍵を握る。
女性配偶者の有業率の家計調査結果
女性配偶者の有業率の多い都市
女性配偶者の有業率の少ない都市
これまでの女性配偶者の有業率の推移
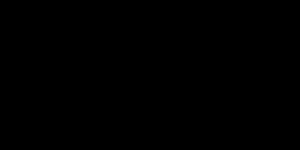
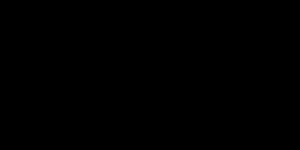
詳細なデータとグラフ
女性配偶者の有業率の現状と今後
女性配偶者の有業率とは、勤労者世帯における世帯主の配偶者が有業者である割合を示す指標であり、日本では事実上、主に「妻の就業率」とほぼ同義で扱われる。この数値は、日本社会における女性の社会進出の度合い、家計の共働き依存度、地域社会の保育環境や雇用環境、文化的背景などの複合的要因を反映している。
2000年から2025年にかけての全国的な傾向
2000年初頭の女性配偶者の有業率はおおむね40%台半ば程度であったが、次第に共働き世帯の増加とともに上昇を続け、2025年3月時点では全国平均56.7%に達している。背景には以下のような要因がある:
-
景気停滞により家計補助の必要性が高まった
-
働き方改革による短時間勤務や在宅勤務の普及
-
保育施設や制度整備の進展(ただし都市間差あり)
-
世代交代による「専業主婦」志向の変化
特に2010年代以降の上昇は顕著であり、「女性活躍推進法」の制定や、待機児童解消への政策努力が後押しした。
有業率が高い都市の特徴
2025年3月時点で有業率の高い都市は以下の通り:
-
富山市(74%)
-
津市(72.3%)
-
金沢市(72%)
-
千葉市(69.3%)など
これらの都市の共通点としては、
-
地方都市ながら安定的な産業構造(製造業、公務員など)を持つ
-
家族主義的価値観が根強く、地縁・血縁の支援が強い
-
保育環境が比較的整備され、地域ぐるみの子育てが可能
-
車社会で通勤利便性が高く、職住近接も実現しやすい
また、富山市は前年から+35.28%の大幅増、千葉市は+54%と急上昇しており、いずれも共働きを志向する若年層の流入が背景と考えられる。
有業率が低い都市の特徴と課題
有業率が低い都市は以下の通り:
-
福島市(43.1%)
-
那覇市(44.7%)
-
宮崎市(47.2%)
-
東京都区部(48.6%)
これらの都市には以下のような課題がみられる:
-
核家族化とサポート不足(特に東京都区部など)
-
保育施設不足や待機児童問題
-
雇用環境の非正規化・低賃金化(特に沖縄・宮崎など)
-
災害影響(福島市など)や人口流出による労働力縮小
-
保守的な価値観が根強い地域もある
特に横浜市(-28.42%)や東京都区部(-23.58%)など、都市部の1部では前年よりも大幅に低下しており、子育て環境や職場と家庭の両立支援の限界が表れている。
世代間の価値観の変化
団塊世代やバブル世代の妻には「専業主婦」志向が強く、結婚後は家庭に入ることが1般的であったが、2000年代以降に社会進出を果たした就職氷河期世代〜ミレニアル世代の女性は、経済的な自立志向やキャリア志向を持つ者が多く、有業率の押し上げに寄与している。
さらに、Z世代以降の若年層では「共働きは当たり前」「夫婦で家事・育児をシェア」という価値観が浸透しており、都市によっては今後急激に有業率が上がる可能性もある。
今後の推移予測と政策の課題
今後の有業率は、次のような傾向で推移すると予測される:
-
地方都市は安定的に高水準を維持
-
都市部は保育政策次第で再上昇の余地あり
-
地域格差はやや縮小方向へ進むが、完全解消は困難
政策的には以下の対応が不可欠である:
-
保育施設のさらなる整備(都市部優先)
-
在宅勤務制度の普及と支援(テレワーク手当など)
-
男女共同3画教育の拡充
-
介護との両立支援(特に中高年層)
これらが整えば、2020年代後半には全国平均で60%台半ばに到達する可能性もある。
まとめ
女性配偶者の有業率は、単なる統計指標ではなく、その都市の経済力、社会支援、文化、そして家族観を映す鏡である。これからの日本社会においては、共働きを前提とした制度と社会意識のアップデートが求められており、それを地域ごとの状況に合わせて展開していくことが鍵となる。


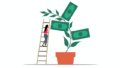

コメント