家計調査によると、無職世帯の繰越金は全国平均で9.147万円。小都市Aと中都市では前年同期比で大きく増加し、小都市Aは+49.1%と際立った伸びを示しました。一方、小都市Bでは減少傾向が見られます。これは地域ごとの生活費圧力や支援制度の違い、世帯構造の影響を反映しています。今後はインフレや年金支給タイミングの変化により、繰越金の地域格差がさらに拡大する可能性があります。
繰越金の家計調査結果
繰越金の多い都市
繰越金の少ない都市
これまでの繰越金の推移
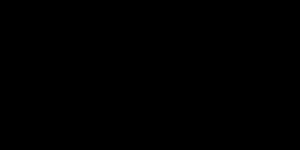
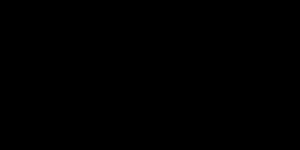
詳細なデータとグラフ
繰越金の現状と今後
繰越金とは、前月・前期に使いきれずに翌月へ持ち越された金銭的余剰を意味します。家計調査では、収入と支出の差額として捉えられ、無職世帯にとっては年金や貯蓄の残額を翌月へつなぐ“生活防衛線”とも言えます。この金額が高ければ家計に余裕があることを示し、低ければ月内で収支がぎりぎり、あるいは赤字の可能性があります。
都市別の繰越金の傾向
今回のデータによると、1世帯あたりの繰越金が最も多かったのは小都市A(10.32万円)で、前年同期比+49.1%と急増。中都市(10.2万円)も+15.14%の増加と堅調です。1方、大都市(8.53万円)は+8.099%とやや控えめ、小都市B(6.393万円)は-13.97%と減少しています。
これは、物価の高い大都市では日々の生活費が繰越金を圧迫しやすく、また小都市Bでは社会保障制度の恩恵が乏しい、あるいは住民の収入構造が変化していることが影響していると考えられます。対照的に小都市Aや中都市では生活コストが安定しているか、支出を控えやすい高齢層が多い可能性があります。
世代間の特徴
無職世帯の大半は高齢世帯で構成されており、収入は年金に依存しています。高齢化の進行とともに支出を抑え、繰越金を積み増す家庭も増えてきましたが、医療費や介護費が不安定な支出要素として存在します。小都市Aの繰越金増加は、そうした支出を抑制できた年の影響とも推測されます。
また、比較的若い無職世帯(就労意志ありの離職中など)では、貯蓄も少なく繰越金が出づらい傾向にあります。
今後の推移と課題
今後、物価上昇が続けば繰越金は都市によって大きく2極化する可能性があります。特に大都市では住居費・光熱費・食費の上昇が家計を圧迫し、繰越金のさらなる減少が懸念されます。1方、地方都市では、社会福祉の充実や地域価格の安定が繰越金の維持・増加を後押しする要素になるかもしれません。
ただし、こうした動きも年金支給月のばらつきや医療・介護負担の拡大、災害などの突発的要因で1変するリスクがあります。また、デジタル化やキャッシュレス決済の普及により、繰越金の把握や計算方法そのものが変わる可能性もあります。
まとめ
繰越金は、無職世帯の「今月をどう生き延びるか」のバロメーターです。都市間での違いは生活コスト・福祉制度・住民の家計意識に起因しており、今後も繰越金は地域差が強まる可能性があります。社会政策や地域支援のあり方が、無職世帯の暮らしの安定に直結すると言えるでしょう。




コメント