家計調査によると、2025年3月時点で無職世帯の特別収入は全国平均で1.162万円。都市別では中都市が最も高く(1.35万円)、大都市が最も低い(0.913万円)。前年比では中都市が+59.52%と顕著な伸びを示す一方、小都市Bや大都市では減少傾向が見られる。災害支援、自治体施策、人口構成などが都市間格差の要因であり、今後は高齢化と支援制度の変化によって地域ごとの差がさらに拡大する可能性がある。
特別収入の家計調査結果
特別収入の多い都市
特別収入の少ない都市
これまでの特別収入の推移
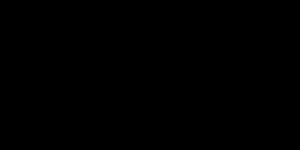
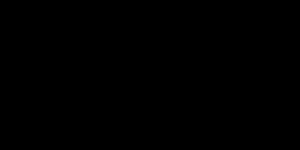
詳細なデータとグラフ
特別収入の現状と今後
「特別収入」とは、無職世帯における定常収入(年金、仕送りなど)とは別に、1時的・臨時的に発生する収入のことである。代表的なものは以下の通り:
-
保険金の受け取り
-
災害見舞金
-
臨時給付金(自治体や国の補助)
-
財産処分や贈与の収入
無職世帯にとって、特別収入は突発的な支出(入院・介護・葬儀・災害)に対応する命綱的な役割を果たしており、その動向は生活の安定度を測る1指標である。
2018年~2025年の全体的推移と背景要因
2018年から2020年は比較的安定した水準だったが、2020年には新型コロナによる特別定額給付金などで全国的に急増。その後、コロナ関連の給付終了とともに減少傾向に転じたが、地域によっては災害支援や高齢者向け給付が継続しており、ばらつきが目立つ。
特に、2024年~2025年は物価高対応の支援策が中都市や1部小都市で支給されたと推測される1方で、大都市では減少に転じており、地域間の財政政策の差が表れていると考えられる。
都市別の特別収入とその増減要因
都市別の特別収入水準(2025年3月時点)
-
中都市:1.35万円(+59.52%)
-
小都市A:1.26万円(+20.4%)
-
小都市B:1.069万円(-33.37%)
-
大都市:0.913万円(-0.911%)
考察:
-
中都市: 伸び率が高く、災害支援や地域特化の給付(例:高齢者向け暖房手当、物価高騰対策給付など)が行われた可能性がある。人口構成として高齢者比率が高く、政策対象として厚遇されやすいことも寄与。
-
小都市A: 堅調な増加を示すが中都市ほどの伸びではない。公的給付制度の恩恵は受けつつも、財政規模や政策展開が中都市に比べて限定的。
-
小都市B: 前年比大幅減少。前年の支給が1時的な要因(災害・地域限定施策)によるもので、2025年には支援が終了したと推定される。
-
大都市: 安定はしているが、減少傾向。高齢者世帯数は多いものの、自治体ごとの財政余力不足や、支援の1律化による「埋没」が影響した可能性がある。
都市間格差の背景要因
-
自治体の財政力と支出優先順位 中都市や1部小都市では高齢者支援や物価高騰対策の給付に積極的な1方、大都市は住民数の多さから1人当たり給付額が小さくなる傾向。
-
災害や突発的支援の有無 災害の多かった年・地域では保険金や支援金の流入で1時的に特別収入が増加することがある。
-
高齢者比率と生活困窮率 高齢者単身世帯や低所得世帯が多い地域ほど特別収入への依存が高まり、政策による波を受けやすい。
世代構造との関係
無職世帯の大半は高齢者世帯であり、特別収入も主にこの層に集中している。
-
60~74歳:退職金の分割受取、保険金などが見られやすい。
-
75歳以上: 医療関連補助、生活保護や特別給付の対象になりやすい。
また、単身高齢者と複数人世帯では、支援の受取状況や相続・贈与の可能性にも違いがある。
特別収入の課題
-
恒常性の欠如 特別収入は1時的なものであり、生活基盤として当てにするには不安定。
-
地域による格差 「どこに住んでいるか」で収入が左右される構造は、住民の生活の公平性を損なう。
-
可視化の難しさ 個々の給付や贈与など、内訳が多岐に渡るため、政策としての成果や課題が見えにくい。
今後の予測と政策への提言
今後の推移予測:
-
全国平均では緩やかな減少が続く → コロナや災害支援の1巡により、特別収入の水準は下がっていく。
-
中小都市では施策次第で増加もありうる → 高齢化対策や物価支援が続く地域では、特別収入が下支えされる。
-
大都市では横ばいか微減傾向 → 行政のマンパワーや予算制限から、細やかな支援策が難しい。
政策への提言:
-
特別収入の内訳を公的に整理し、政策効果を可視化する。
-
高齢単身世帯への定期的支援制度の創設。
-
自治体間格差を是正するための交付税配分の見直し。
まとめ
無職世帯における特別収入は、生活の安全弁として1定の役割を果たしているが、その性質上、地域格差や年度ごとの波が大きく、安定的な生活設計には不向きである。特に中都市では政策効果が数値として現れており、逆に大都市では効率重視が収入の減少として反映されている。今後は、年齢層と居住地を軸にした支援政策の再編成が必要となるだろう。




コメント