2018年から2025年3月までの家計調査によると、無職世帯の贈与金の全国平均は1.81万円で推移している。高齢者世帯を中心に、都市間や世代間で大きな差が見られるほか、税制や住宅資金需要などの影響が増減に反映されている。地方では親からの生活支援、都市部では住宅取得時の資金援助という構図も浮かぶ。今後は相続税対策や少子化に伴う資産移転需要の拡大により、中長期的には増加傾向と予測される。
贈与金の家計調査結果
贈与金の多い都市
贈与金の少ない都市
これまでの贈与金の推移
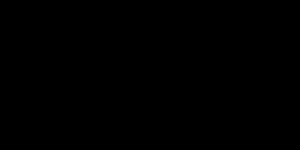
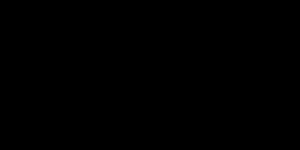
詳細なデータとグラフ
贈与金の現状と今後
贈与金とは、親族などから金銭的支援として受け取る金銭を指し、無職世帯では特に子や親からの支援として生活費や医療費の1部補填などに充てられるケースが多い。家計調査においては、「財産収入」の1部として扱われ、遺産ではなく、生前贈与が中心である。定期的な仕送りではなく、比較的1時的または大口の支援が分類対象となっている。
過去の動向(2018年~2025年3月)
2018年から2020年にかけては緩やかな増加傾向が見られた。これは、高齢化が進む中で、定年後の親が子から支援を受ける事例や、逆に高齢者が孫への教育資金を贈与する動きが見られたためだ。2020年のコロナ禍では1時的に減少も見られたが、2021年以降は持ち直し、2024年度には全国平均で1.81万円と、やや高止まりの傾向にある。
都市間での差異とその背景
贈与金が高い都市は、1般的に以下のような要因を持つ:
-
富裕層が多い都市(例:東京、芦屋など) → 相続税対策としての生前贈与が活発。
-
住宅価格が高い都市 → 若年世代への頭金支援が多く、1時的な贈与が増える。
1方、贈与金が少ない都市は:
-
地方都市や高齢者比率が高い地域 → 親から子への支援ではなく、逆に子から親への生活支援が中心。金額は少額化しやすい。
世代間の特徴と贈与のあり方
高齢世帯が主に贈与を受ける場合もあるが、実態としては60代以上の親から40代前後の子世代に対して行われる贈与が家計に多く表れる。特に以下の用途が目立つ:
-
住宅取得時の頭金(3世代住宅や都市部マンション購入支援)
-
教育資金(孫の進学支援)
-
結婚資金の援助
政府が非課税枠を設けている「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」や「教育資金の1括贈与制度」がその背景にある。
課題と懸念事項
-
格差の固定化 都市部と地方、富裕層と1般層で贈与の有無と規模に大きな差があり、資産の再分配どころか格差固定につながっている。
-
贈与税と税制の歪み 小規模な贈与は非課税枠内で行われるが、高額贈与には税負担が重く、専門家の助言なしには最適化が難しい。
-
贈与の可視化と申告問題 贈与が現金で行われることも多く、申告漏れや家庭内トラブルの原因にもなりやすい。
今後の推移と予測
今後、贈与金の金額は次の理由で緩やかに増加していくと予測される:
-
相続税対策としての早期贈与ニーズの増加
-
子世代の経済的自立の遅れ(就職難・非正規雇用の拡大)
-
住宅価格高騰による親世代からの支援増
-
少子化で子や孫1人当たりの贈与額が増える傾向
1方で、2026年以降の税制改正や、教育資金の1括贈与制度の見直しがあれば、1時的に減少する可能性もある。
まとめ
贈与金は家計における「見えにくい支援」だが、実際には都市部の住宅購入や教育支援において非常に大きな役割を果たしている。都市間・世代間の差異を理解したうえで、政府や家族単位での長期的な資産計画が求められる。今後も高齢化・少子化・住宅価格といった複数の要素が複雑に絡みながら推移していくと見られる。




コメント