2025年3月時点で、無職世帯の1世帯あたりの「受贈金」は全国平均914円と、ごく小額ながらも特定の生活支援や援助の実態を反映しています。主な内容は子世代からの仕送りや冠婚葬祭関連の贈与、地域的な文化による習慣的支援です。都市部と地方で受贈金額の差があり、今後は高齢単身世帯の増加や扶養力の低下により、受贈金が生活補完として再注目される可能性もあります。
受贈金の家計調査結果
受贈金の多い都市
受贈金の少ない都市
これまでの受贈金の推移
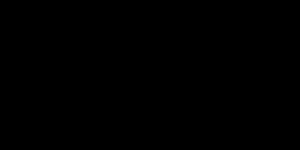
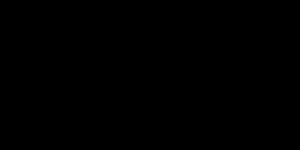
詳細なデータとグラフ
受贈金の現状と今後
家計調査における「受贈金」は、現金やモノとして家計以外の個人や団体から受け取った贈与を意味します。具体的には以下のような支出が含まれます。
-
子どもや親族からの仕送り(定期的・臨時的)
-
親族・知人からの祝い金や香典、見舞金
-
社会的支援(近隣住民、地域の互助団体からの援助)
-
公的支援ではなく、私的な金銭的贈与
この項目は「1時的・非制度的支援」を映し出すものであり、受取や給付とは異なり、情緒的・文化的背景が強いのが特徴です。
2018年〜2025年の受贈金の推移と背景
平均額が千円未満と小額であるにもかかわらず、受贈金は社会的変化を映し出すミクロな指標でもあります。
2018〜2019年
経済状況は安定しており、贈与は冠婚葬祭や定期仕送りが中心。月平均受贈金は800〜900円前後で推移。
2020〜2021年(コロナ禍)
-
帰省自粛・冠婚葬祭の縮小で贈与機会が激減。
-
ただし、生活困窮により仕送り型の支援が1時的に増加。
-
結果として、月平均はやや上下しつつも横ばい。
2022〜2025年
-
インフレ進行や物価高騰で高齢世帯の生活が厳しくなり、子世代による支援再開や増額の兆し。
-
1方で、親子ともに経済的余力が乏しい世帯では受贈機会が減少。
結果として、2025年3月時点での平均は914円。これは決して無意味な額ではなく、むしろ「贈与という文化の変容」を映し出す値です。
都市別の受贈金──地域文化と家族構造の影響
都市ごとに見た場合、受贈金額には以下のような違いがあります。
受贈金の多い都市の傾向
-
地域的に扶養意識や親族間の関係が強い地域(例:関西・9州地方の中都市)
-
多世代近居や実家支援文化が残っているエリア
-
親族イベントや冠婚葬祭が活発な地域
これらの都市では、定期的な仕送りや、冠婚葬祭の金銭授受が生活に根づいています。
受贈金の少ない都市の傾向
-
首都圏・都市部で核家族化・孤立化が進行している地域
-
高齢者が単身で暮らすケースが多く、支援関係が希薄
-
冠婚葬祭の簡略化、キャッシュレス化も影響
都市化が進む地域ほど、贈与文化の退潮や支援の非金銭化(例:物品・サービス提供)が見られます。
世代間の違いと生活構造
受贈金の受け手である無職世帯の中にも、世代によって受贈の形が異なります。
60〜70代(前期高齢者)
-
子ども世代がまだ働き盛りであり、定期的な仕送りがあるケースも
-
親族間イベントに頻繁に3加し、受贈金が発生しやすい
75歳以上(後期高齢者)
-
子ども世代がすでに退職に近く、支援余力が縮小
-
本人が受贈するより、むしろ孫や子に贈与する立場に回ることが多い
このように、「支援される側から支援する側へ」の転換が高齢期には起こるため、受贈金の額は高齢化とともに減少する傾向にあります。
受贈金にまつわる課題と見えない支援の構造
受贈金は額が小さく、記録に残らない場合も多いため、家計調査で表面化しているのは氷山の1角です。
主な課題
-
贈与の記録漏れ:現金ではなく物品や電子マネー等での支援が増加
-
格差の固定化:受贈できる人とできない人の格差が拡大
-
精神的プレッシャー:贈与を期待・依存する関係が負担となるケースも
また、支援の「非貨幣化(例:買い物の代行、配食など)」が進むと、受贈金としてはカウントされないが実質的支援は存在する、という現象も広がっています。
今後の展望──「見えにくい支援」の可視化と制度的対応
今後、受贈金という項目は以下の理由で、形を変えつつ存在感を持ち続けると考えられます。
高齢単身世帯の増加
家族との接点が減る中で、受贈金は精神的なつながりの指標として重要性が高まる。
キャッシュレス時代の新たな贈与形態
ポイント送金・チャージ支援など、新しい形の金銭支援が増え、統計には反映されにくくなる。
社会的孤立の防止策としての注目
地方自治体やNPOによる地域通貨や互助支援の贈与的活動が拡大する可能性がある。
そのため、今後は「受贈金」という狭義の概念ではなく、非制度的支援の全体像を見ていくことが求められます。
まとめ:「受贈金」は微細だが重要──家族と地域のつながりの鏡
全国平均わずか914円の「受贈金」ですが、その裏には日本社会の変化が凝縮されています。
-
家族の扶養文化の衰退
-
高齢者の孤立と支援の不均衡
-
お金に換算できない支援の拡大
これらは社会の「見えない温もり」と「ひずみ」の両方を映す鏡です。今後は、金額の多寡ではなく、「支援の有無と質」を中心に議論していく必要があります。




コメント