2025年3月時点で、無職世帯の財産「受取」は全国平均49.96万円と高水準を維持しています。年金や保険給付、満期返戻金、相続などが主な内訳ですが、都市や世代間で大きな格差が見られます。都市部では一時的な保険金受取や不動産売却益が多く、地方では定期的な年金・仕送りが中心です。今後は高齢化の進展とともに受取額の個人差が拡大し、資産の有無が老後の生活格差に直結することが懸念されます。
受取の家計調査結果
受取の多い都市
受取の少ない都市
これまでの受取の推移
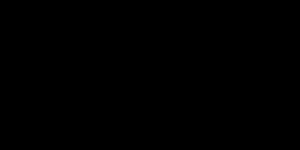
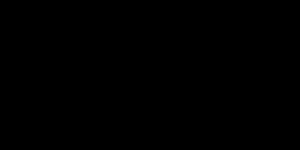
詳細なデータとグラフ
受取の現状と今後
「受取」とは、家計調査において1時的または臨時的に受け取った資産的収入を指します。無職世帯における「受取」は、主に以下の要素を含みます。
-
保険の満期返戻金や1時金
-
預貯金の利子や投資収益
-
相続や贈与による資産の移転
-
不動産の売却益
-
特定支給金(例:介護保険給付金など)
「収入」と異なり、「受取」は持続的な生活費の源ではないものの、老後資金の補填や医療・介護費の支払いなど、家計にとって非常に重要な位置を占めます。
2018年〜2025年3月の受取額推移
2018年から2025年までの期間、受取額の動向は次のような傾向を見せてきました。
2018〜2019年
経済が比較的安定していたため、保険商品の満期受取や定期預金の満期などで受取額が1定。
2020〜2021年(コロナ禍)
感染拡大の影響で1部資産の取り崩しや解約が進み、受取額が1時的に増加。特別給付金などの政府支援金もこの項目に計上された可能性が高い。
2022〜2024年
物価上昇や生活費増加により、老後資金として蓄えていた資産の引き出しや売却が増え、受取額も高水準を維持。
2025年3月時点
全国平均49.96万円という数値は過去最高水準に近く、1時的資産の流動化が進んでいる兆候とも読めます。
都市別の違い──受取額の差を生む地域要因
都市別に見た受取額には、顕著な地域格差があります。
受取額が高い都市の特徴
-
大都市圏や政令指定都市(東京、名古屋、横浜など)
-
金融資産や不動産資産を保有する世帯が多い
-
保険加入率が高く、退職時の1時金や相続資産も豊富
特に都市部では、退職金を1括で受け取る文化や、相続による不動産売却が絡むことで、高額の「受取」が1時的に発生する傾向があります。
受取額が少ない都市の特徴
-
地方圏(特に過疎地域)
-
金融資産や保険加入が少ない
-
年金収入に依存し、「受取」の頻度が少ない
農村部では世代間の資産移転は物的(家や土地の使用)にとどまり、現金としての「受取」は発生しにくい傾向です。
世代間の差──受取の内容と時期の違い
無職世帯の中でも、年代によって受取額の傾向が異なります。
60〜70代(前期高齢者)
-
定年退職後、退職金や企業年金の1時金の受取が多い
-
保険や共済の満期金もこの年代に集中
-
不動産の相続を受けての売却が発生するケースも
75歳以上(後期高齢者)
-
まとまった受取は減少し、医療給付金や介護1時金などが中心
-
逆に相続「する側」になり、資産は流出傾向に
また、配偶者が亡くなった際の死亡保険金などもこの世代で多く見られます。
受取に潜む課題──格差と資産形成の壁
「受取」の額には明確な資産格差が反映されており、以下のような課題があります。
-
退職金や保険加入の有無による格差:非正規雇用や自営業者は受取が少ない
-
相続できる資産の地域・家庭差:都市部と地方、単身と3世代同居で大きく異なる
-
金融知識の差:資産運用をしている家庭ほど高額受取が見込まれる
これらは「老後の生活の質」に直結するため、政策的な対応が必要です。
今後の見通し──「受取」は減少傾向か
将来的には、無職世帯における受取の中位値は低下傾向になると予測されます。その要因は以下の通りです。
-
退職金制度の縮小:中小企業や非正規職では導入率が低い
-
相続税対策による生前贈与の分散化:受取が分割・小額化する
-
保険文化の変化:貯蓄型保険よりも掛け捨て型の普及が進む
また、団塊ジュニア世代(1970年代生まれ)が高齢化を迎える頃には、そもそも資産を受け取れる人の割合が大きく下がると見られます。
まとめ:受取は“運”の格差──制度と文化の再設計を
受取は、1生のうちで数回しか発生しないことも多く、個人の資産形成・家庭背景・制度環境の影響を強く受ける項目です。
それゆえ、資産を「持つ者と持たざる者」の格差が1層拡大する可能性があり、今後は以下の対応が求められます。
-
金融教育の拡充と早期の資産形成支援
-
退職金制度の再整備
-
相続や贈与の在り方の再検討
「受取」は老後の安全弁であると同時に、社会全体の格差構造の象徴でもあります。生活の安定を図るうえで、意識的にその重要性を見直す必要がある時代に入っています。




コメント