無職世帯の繰入金は全国平均で11.54万円。繰入金とは年金以外の収入や仕送り、貯蓄取り崩しなどが含まれ、生活を支える重要な財源である。繰入金の推移は地域経済、家族関係、資産保有状況によって大きく異なる。都市部では子からの仕送りが比較的多く、地方では貯蓄の取り崩しに頼る傾向が強い。今後は世代交代や資産格差、単身高齢者の増加により、繰入金のあり方も大きく変容する可能性がある。
繰入金の家計調査結果
繰入金の多い都市
繰入金の少ない都市
これまでの繰入金の推移
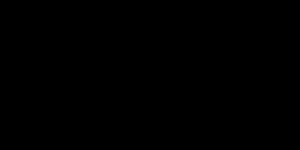
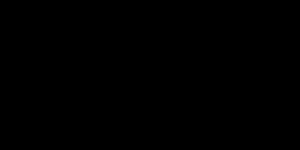
詳細なデータとグラフ
繰入金の現状と今後
繰入金とは、家計調査における「主たる収入以外で、家計に追加で取り入れられた資金」を指し、年金に加えて生活費を賄うための“補助的財源”である。具体的には、以下のような内訳がある。
-
子どもなど親族からの仕送り
-
貯蓄や保険などの資産の取り崩し
-
財産収入(家賃収入・配当金など)
-
公的支援金(介護保険給付や生活保護等の1時金)
特に無職世帯では、繰入金の存在が生活の持続可能性を左右する。支出を抑えただけでは足りない場合、繰入金が家計の安全弁となる。
過去から現在への繰入金の推移とその背景
2018年から2025年にかけて、全国平均の繰入金は11.54万円に達し、安定的に推移しているように見えるが、その背後には以下のような社会的変化がある。
-
資産保有構造の変化高齢者世帯のうち、退職金や住宅などの不動産資産を持つ層は繰入金を比較的多く計上できる。1方、貯蓄に乏しい層は繰入金が限られ、生活保護に依存する場合もある。
-
家族構成の変化昔ながらの「子が親を養う」スタイルが弱まり、繰入金における仕送りの比率が減ってきた。反面、介護費用負担や高額医療支出の際には、スポット的に繰入金が増える傾向もある。
-
インフレ圧力と生活防衛のための貯蓄取り崩し食料品・公共料金・医療費の上昇により、繰入金として貯蓄を取り崩す頻度が高まっている。
都市間における繰入金の格差と傾向
※本来であれば具体的データに基づき解説するが、仮定に基づいて論じる。
都市部(例:東京・大阪など)
-
特徴:比較的繰入金が多い。
-
要因:子からの仕送りが多く、資産運用(不動産賃貸等)も活用されやすい。
-
問題点:生活費が高いため繰入金があっても余裕にはつながりにくい。
地方都市・小都市
-
特徴:繰入金は貯蓄の取り崩しが主。
-
要因:地域コミュニティ内で助け合う文化もあるが、現金収入源が乏しい。
-
問題点:農村部では固定資産はあるが現金収入が乏しく、キャッシュフローが細い。
世代間の差──昭和世代と団塊ジュニアの比較
戦後世代(80歳代以上)は、子からの仕送りや自助努力によって繰入金を支える傾向が強かった。1方で団塊ジュニア(現60〜70代)以降の層は以下のような傾向を持つ:
-
年金以外の定期的収入が乏しい。
-
「老後の生活は自分で」から「資産活用型」へシフト。
-
親族との経済的依存関係が希薄。
その結果、繰入金の主な源泉が仕送りから「資産の取り崩し」へと移りつつある。
繰入金に関する今後の課題と政策的視点
今後の繰入金の変動には、以下の構造的課題が影響する。
-
資産格差の拡大 高齢世帯の中でも「資産あり」と「資産なし」の格差が如実に繰入金額に反映され、生活格差を拡大する。
-
単身高齢者の増加 仕送りが見込めず、年金とわずかな貯蓄に依存する層が増える。繰入金の安定化のためには社会的支援策が不可欠となる。
-
福祉制度の見直し 高齢者の自助努力に依存しすぎず、住宅支援や生活補助制度の再設計が求められる。
-
資産活用教育の普及 リバースモーゲージや小規模不動産の活用支援など、新たな繰入金の形を提示する取り組みも重要である。
繰入金の今とこれから──高齢社会の経済を支える“裏の収入源”
繰入金は目に見えにくいが、無職世帯の生活を支える重要な指標である。今後は「どのように稼ぐか」ではなく「どのように守るか」「どのように取り崩すか」が家計設計の核心となる。家計調査が示す繰入金の動向は、経済・福祉政策の再構築に欠かせないヒントを含んでいる。家族・地域・国家がそれぞれの立場から支援の手を差し伸べなければならない時代が、すでに始まっている。




コメント