2025年3月時点の家計調査によると、無職世帯の事業・内職収入の全国平均は月7,157円で、最も高いのは小都市B(10,470円)、最も低いのは中都市(5,651円)でした。前年同期比では大都市が+58.58%と大幅増、小都市Bも+16.09%と堅調。一方で中都市と小都市Aでは減少傾向です。内職や小規模事業は高齢者の生計補完手段として重要ですが、都市構造や就労機会、技術環境への対応度が影響しています。今後は高齢者の就業支援や地域単位での副業環境整備が鍵となります。
事業・内職収入の家計調査結果
事業・内職収入の多い都市
事業・内職収入の少ない都市
これまでの事業・内職収入の推移
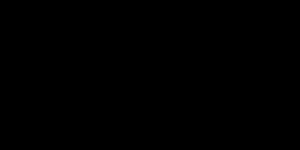
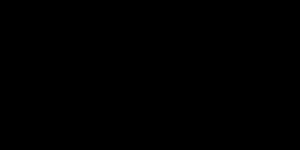
詳細なデータとグラフ
事業・内職収入の現状と今後
無職世帯における「事業・内職収入」とは、農業・商業・個人営業や在宅での内職など、雇用形態に属さない形で得る収入を指します。主に年金生活の高齢者が、自宅で手工芸品を作って販売したり、知人の畑を手伝ったりといった、柔軟な働き方で得る報酬です。
また近年では、デジタル化の進展により高齢者によるネット販売や、クラウドソーシングなど新たな内職形態も生まれており、就労の多様化が収入にも反映されつつあります。
全国平均と都市別の収入傾向 ― 小都市Bの存在感、大都市の回復
2025年3月時点での全国平均は7,157円。都市別では以下のような傾向が見られます:
-
小都市B:10,470円(+16.09%)
-
大都市:7,623円(+58.58%)
-
小都市A:6,351円(-9.323%)
-
中都市:5,651円(-8.958%)
最も収入が高いのは小都市Bで、前年より16%増と安定的な成長を見せています。これは地域密着型の副業機会(地場産業の手伝いや農業的内職など)が多く存在しているためと考えられます。
1方、大都市では+58.58%と急激な増加が見られますが、これは物価高や年金不安の中で「働かざるを得ない」高齢者が、副業やネットを通じた内職に積極的に取り組み始めた結果とも読み取れます。
減少傾向にある地域 ― 小都市A・中都市の背景
小都市Aと中都市ではそれぞれ9.3%、9%弱の減少となっています。この背景には、以下のような要因があると考えられます:
-
高齢化の進行と身体的な就労制限
-
地域経済の停滞による内職需要の減少
-
コロナ禍による地域内の接触制限と仕事機会の減少
-
デジタルスキルの格差により、新たな働き方への適応が困難
特に中都市では、工場や流通業などのパート的な内職機会が減り、代替手段が用意されていないまま、収入減となっている可能性があります。
世代間・地域間の特徴 ― 事業・内職収入を得る層の姿
事業・内職収入の多くは60代〜70代の高齢者が中心ですが、都市ごとの就労観や生活コストも関係しています。
-
小都市Bのような地域:生活コストが低く、地元での労働機会(農作業、地場産業、手工芸等)もあり、働き続けることが地域文化として定着。
-
大都市圏:医療や生活サービスは充実しているが、生活費も高いため、少額でも稼ぐ動機が強くなり、副業・ネット活用も進む。
-
中都市・小都市A:都市機能の縮小や若年層の流出が激しく、高齢者が働ける場が限定的。支援の手が届きにくいエリアとも言える。
今後の推移と課題 ― 働ける高齢者をどう支えるか
今後、無職世帯の「事業・内職収入」は地域によって2極化が進む可能性があります。
プラス方向に進む条件:
-
デジタル環境と教育の整備(高齢者向けのITリテラシー支援)
-
自治体による内職マッチング支援やクラウドソーシング促進
-
シニア人材向けの起業支援や小規模事業支援策の拡充
マイナス方向に進む懸念:
-
高齢化による就労困難者の増加
-
地域経済の衰退による仕事の枯渇
-
「孤立化」する高齢者の増加により、内職情報へのアクセス自体が困難になること
政府や自治体が地域ごとに実態を踏まえた施策を講じることで、生活補完的な内職収入を持続可能なものにしていく必要があります。
まとめ ― 「働く高齢者」という現実への支援を
事業・内職収入は、今や高齢無職世帯にとって重要な生計補完の柱となっています。特に年金だけでは生活が困難な世帯にとって、わずかな金額でも「収入があること」は心理的安定と実際の家計維持の両面で大きな意味を持ちます。
地域間での収入格差は、支援環境や就労機会の違いに起因しており、今後もこうした違いが拡大する懸念があります。支援の焦点を、年齢や地域に応じた「多様な働き方」へとシフトし、誰もが役割を持ち続けられる社会を築くことが重要です。




コメント