2025年3月時点の家計調査によると、無職世帯における「他の世帯員収入」の全国平均は月1.634万円で、都市別では小都市Bが最も高く1.888万円、大都市が最も低く1.412万円となっています。前年同期比では、小都市Bが-35.68%と大幅減である一方、小都市Aは+4.973%と増加しました。この収入は主に同居の現役世代の給与や仕送りなどによって構成され、世帯構成や地域の雇用環境が強く影響します。今後は世代間同居の減少や単身化の進行により、収入の減少が懸念されます。
他の世帯員収入の家計調査結果
他の世帯員収入の多い都市
他の世帯員収入の少ない都市
これまでの他の世帯員収入の推移
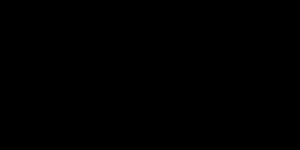
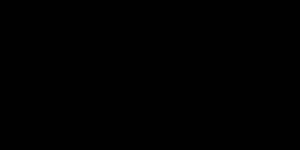
詳細なデータとグラフ
他の世帯員収入の現状と今後
無職世帯の「他の世帯員収入」とは、世帯主以外の就労者や収入のある同居者(主に子どもや配偶者など)から得られる収入を指します。これは現役世代の給与所得やパート収入、仕送りなどを含み、高齢者世帯の経済的な自立に影響を与える重要な補完的収入源です。
全国平均と都市別収入 ― 表面に出た構造格差
2025年3月時点での全国平均は月額1.634万円。小都市Bが1.888万円で最も高く、大都市は1.412万円と最も低くなっています。小都市BやAのような地域では、家族間での支え合いの文化が根強く、同居率も高いため、「他の世帯員収入」が多くなりやすい傾向があります。反対に、大都市では単身世帯や夫婦のみの世帯が多く、こうした収入の構成比が相対的に低くなっています。
前年同期比の動向 ― 大幅な減少とわずかな増加の意味
前年同期比では、小都市Bが-35.68%と大幅減少しています。これは1時的に働いていた世帯員の退職や就労時間の減少、または転出による影響が考えられます。1方、小都市Aでは+4.973%とわずかに増加していますが、これは地方における多世代同居や子ども世代の雇用安定化などが背景にあると推察されます。
大都市(-20.85%)や中都市(-13.84%)の減少は、核家族化や就労状況の悪化、特に非正規雇用の収入減が影響している可能性があります。都市部では単身者の増加により、そもそも「他の世帯員」がいない世帯も増えているため、この収入項目の比重が年々下がっているのです。
世代間の同居と家族構成が生む格差
他の世帯員収入は、世代間の同居が前提となって初めて成立する収入形態です。そのため、同居率の高い地方圏では数字が高く、都市部では低くなるという傾向が強く表れます。また、単身高齢者世帯や高齢夫婦のみの世帯ではこの収入は存在しないため、収入全体に占める重要性も都市によって異なります。
今後はさらに高齢者の単独世帯化が進むことが予想され、特に都市部では「他の世帯員収入」が収入源として機能しにくくなる懸念があります。
今後の推移と政策的課題
今後、「他の世帯員収入」は全国的に減少傾向が続く可能性が高いです。その背景には、(1)核家族化の進行、(2)若年層の非正規雇用率の高さ、(3)地域間での経済格差、(4)住宅事情による同居の困難さ、などが挙げられます。
政府や自治体による世代間扶養の支援制度、例えば多世代住宅の推進や就労支援の強化、または高齢者向けシェアハウス制度の整備などが、この収入源の安定化に貢献しうる施策です。
まとめ ―「家族内の支え合い」の限界と地域の役割
「他の世帯員収入」は、家族内の支援という日本的な仕組みに支えられた収入であり、地方では今なお大きな役割を果たしています。しかし、都市化と単身化の波の中で、この仕組みは限界に近づきつつあります。今後は地域社会や行政が、家族機能を補完する役割を担うことが求められるでしょう。無職世帯の生活安定には、「家族以外のセーフティネット」の充実が不可欠となります。




コメント