家計調査における非消費支出の全国平均は9.817万円であるが、都市ごとの差が著しい。特に東京都区部や横浜市などの首都圏では13万円台と高く、地方都市の那覇市や宮崎市などでは4〜6万円台にとどまる。増減率にも大きな差が見られ、広島市は急増、那覇市や堺市では急減している。非消費支出は主に税金・社会保険料で構成され、地域の所得水準や行政サービスの違いが影響している。世代間格差や今後の少子高齢化の進行に伴う制度変化にも注意が必要である。
非消費支出の家計調査結果
非消費支出の多い都市
非消費支出の少ない都市
これまでの非消費支出の推移
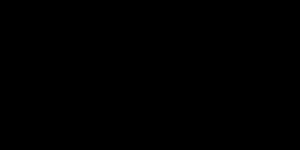
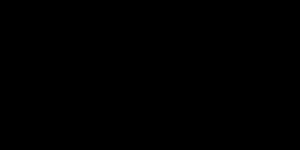
詳細なデータとグラフ
非消費支出の現状と今後
非消費支出とは、食費や家賃といった日常的な消費に直接結びつかない支出を指し、主に税金(所得税・住民税)および社会保険料(健康保険・年金・雇用保険など)が該当する。これらは勤労世帯が生活を維持するうえで不可避な義務的支出であり、可処分所得(自由に使えるお金)に直接影響を与える。
長期的な動向 ― 増え続ける社会保障負担
2000年代初頭から2025年にかけて、非消費支出は全体として増加傾向にある。とくに2000年代後半から2010年代にかけては、少子高齢化の進行とともに年金・医療保険料の増額、税制改正(定率減税廃止など)が相次ぎ、可処分所得が圧迫される構造が形成された。
2010年代以降は景気回復や賃金上昇も見られたが、非消費支出の伸びの方が早く、「働いても暮らしが楽にならない」という声が多くの都市で上がる背景となった。
都市間の非消費支出格差の実態
2025年3月時点の家計調査では、東京都区部(13.75万円)、さいたま市(13.44万円)、横浜市(13.43万円)などが高水準である1方、那覇市(4.19万円)、堺市(5.66万円)、宮崎市(5.76万円)などは極めて低水準にとどまっている。
この格差の要因には以下のような構造がある:
-
平均所得水準の差:高所得都市では所得税・社会保険料が高くなる傾向。
-
企業規模・雇用形態:都市部では正社員比率が高く保険料負担も大きい。
-
地場経済と行政サービスの差:1部地域では扶養控除・自治体補助などが充実しているため支出が抑えられる。
また、首都圏や地方中核都市では非消費支出が前年比で増加しており、たとえば広島市(+77.24%)や横浜市(+50.99%)などは急増している1方、地方都市では堺市(-47.92%)や那覇市(-24.52%)などで急減している。これは所得構造の変化や転職・退職者の影響なども考えられる。
世代間の特徴と課題 ― 若年層・高齢層でどう違うか
若年層(20〜30代)の勤労世帯では、賃金水準が低めにもかかわらず、社会保険料は高水準で課されており、実質的な負担率が高い。1方、40〜50代では所得水準は高いが、同時に教育費や住宅ローンなどの支出も重なり、非消費支出とのバランスに苦しむケースが多い。
高齢者世帯では、そもそも非消費支出の大部分を占める「社会保険料」の仕組みが異なり、勤労世帯とは単純比較ができない。しかし、保険料負担の財源として現役世代への転嫁が強まっているのが近年の特徴である。
今後の展望と政策的課題
非消費支出は、今後も増加基調が続く可能性が高い。理由は以下の通りである:
-
社会保障制度の財源不足:保険料率のさらなる引き上げは避けられない。
-
少子化による労働力人口の減少:負担の分母が減ることで1人当たりの負担が増加。
-
地域間格差の固定化:都市部と地方で異なる税負担・サービス設計が続く可能性。
そのため、政府には以下のような政策的対応が求められる:
-
社会保険制度の負担と給付の再設計
-
所得再分配の強化による低所得層支援
-
地方都市における税制優遇措置の柔軟化
-
デジタル化による行政コスト削減と効率化
非消費支出に「見えない不平等」を読み解く
非消費支出は、日常の家計感覚には現れにくいが、実際には家計の可処分所得や地域の生活満足度を大きく左右する要因である。都市間・世代間の格差、制度設計の不均衡は、日本の持続可能性を問う重要な問題として、今後も注視されるべきである。




コメント