2000年以降の家計調査に基づくと、勤労世帯の事業・内職収入は全国的に減少傾向を経て、近年一部都市で急増している。那覇市や高知市などは地方特有の事情や副業解禁の影響で大きく増加。一方、堺市や神戸市では収入ゼロとなり、都市間格差が広がっている。世代間でもシニア層の小規模事業志向と若年層の副業多様化により、収入構造が二極化。今後は地方創生とテレワーク環境の整備が動向を左右する見通し。
事業・内職収入の家計調査結果
事業・内職収入の多い都市
事業・内職収入の少ない都市
これまでの事業・内職収入の推移
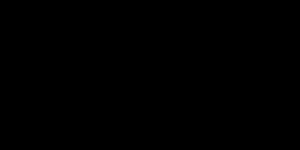
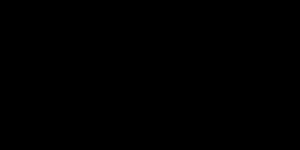
詳細なデータとグラフ
事業・内職収入の現状と今後
事業・内職収入とは、勤労者世帯のうち主たる収入ではないが、個人事業・副業・在宅ワークなどによって得られる収入を指す。自営業者とは異なり、勤労者世帯(サラリーマン世帯など)が対象であるため、副次的な収入源であることが多い。
2000年代以降の全国的な推移と背景
2000年代前半は、終身雇用と年功序列型賃金が1般的で、副業は制度上も文化的にも消極的に捉えられていた。そのため、事業・内職収入の平均値は低く推移していた。
しかし、2008年のリーマン・ショック以降、企業収益の悪化、非正規雇用の増加、そして働き方改革の流れが徐々に副業容認へとつながった。2020年以降のコロナ禍では、在宅勤務の普及により、副業・内職を始める機会が増加したことが、直近の急増に影響を与えていると考えられる。
都市別の収入格差と地域要因
2025年3月時点のデータによると、事業・内職収入が特に高い都市として那覇市(26,750円)、高知市(26,040円)、名古屋市(14,780円)が挙げられる。
この背景には以下の要因がある:
-
那覇市・高知市:都市部に比べ雇用の選択肢が限られるため、地域住民が小規模ビジネスや手工芸、観光関連の副業を行う傾向が強い。また、在宅ワークを活用した県外企業との取引も増加。
-
名古屋市・静岡市:製造業が強い地域では、技術系副業(例:設計、CAD、リモート保守など)の需要が高まり、個人での契約・請負が増えている。
1方で、堺市・宮崎市・神戸市などでは事業・内職収入が「ゼロ」となっており、これは地元企業の副業禁止規定や、高齢化とITリテラシーの低さ、在宅勤務環境の整備遅れが影響していると考えられる。
世代間の特徴と価値観の違い
副業・事業収入に対する意識は世代によって異なる。
-
若年層(20〜30代):デジタルネイティブであり、YouTube運営、SNS発信、クラウドソーシングによるライター・デザイナーなどの仕事に柔軟に対応。副業をキャリアの1部と捉える傾向が強い。
-
中年層(40〜50代):本業での安定収入を基盤に、副業を老後資金の準備や趣味と実益を兼ねる活動として捉える層が増えている。
-
シニア層(60代以上):定年退職後の生活資金補填として、農業、手作業、フリーマーケットなど地域密着型の内職が多くなる。
現在の課題——なぜ収入がゼロになる都市があるのか
事業・内職収入が統計上「ゼロ」となった都市は、堺市、宮崎市、徳島市、熊本市、神戸市、福井市、福岡市と多岐にわたる。これは以下の課題に起因する。
-
企業側の副業規制:特に大企業の支店が集中する都市では、就業規則により副業が制限されている場合がある。
-
行政支援の不足:副業や内職に関する相談窓口・支援制度が整備されていない地域では、実施に踏み切れない家庭が多い。
-
文化的バリア:副業=本業の裏切りという価値観が根強く残っている地域もある。
今後の予測と政策提言
今後、事業・内職収入は以下のように展開していくと予測される:
-
都市部と地方の2極化の進行:大都市では副業環境や制度が整っており、ITリテラシーの高い住民が集まるため、今後も緩やかに増加する見込み。1方で、地方では1部の自治体で増加するが、多くは行政支援がない限り停滞する可能性がある。
-
シニア向け内職支援の重要性:定年後の生活設計の1環として、簡易な事業支援(手作り商品販売や農業内職)の制度整備が求められる。
-
若年層へのクラウド型副業の推進:フリーランスやパラレルキャリア志向の高まりに対応し、教育段階から副業リテラシーを身につけさせる施策が鍵となる。
おわりに
家計調査に見る事業・内職収入の動向は、単なる金額の増減ではなく、地域の産業構造、雇用環境、住民の価値観や政策対応の差を浮き彫りにしている。今後の社会では副業・事業が「選択肢の1つ」から「生活の柱の1部」へと進化する可能性があり、それに対応する社会・企業・政策の3位1体の支援が求められる。




コメント