2025年3月時点での年収別の庭の手入れ代は、平均514.1円ながら、1500~2000万円層が2155円と突出しています。近年では900~1000万円層の支出が前年比+6522%と急増し、中間所得層では減少傾向も見られます。本稿では、2002年からのデータをもとに、所得階層ごとの消費傾向と変化の背景を読み解き、今後の支出動向や問題点について解説します。
年収別の庭の手入れ代
1世帯当りの月間支出
これまでの年収別の推移
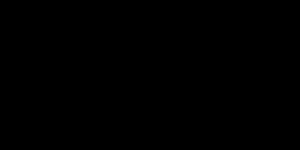
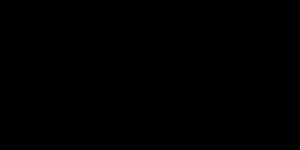
詳細なデータとグラフ
年収別の現状と今後
庭の手入れ代という項目は、1見すると些細な支出に見えますが、実は家計の余裕や暮らしへのこだわり、さらには時間的な余裕の有無までが反映される重要な生活指標です。特に年収別で見ると、消費性向の違いや、生活スタイルの断層が顕著に現れます。
長期的な傾向と近年の変化
高所得層による支出の上昇傾向
データ範囲である2002年以降、高所得層(特に1500万円以上)は景気変動を受けにくく、可処分所得の増加と共に「生活の質」を重視した支出が徐々に拡大しています。特に2020年代に入り、在宅時間の増加やガーデニングブームを背景に、外注による庭の手入れがステータスや快適さの1部として定着しつつあります。
中間・低所得層では支出抑制と格差の拡大
500~800万円層では庭の維持に対して支出を抑える傾向が強まりました。特に2025年3月時点で500~600万円層が-61.5%、700~800万円層が-17.3%と大幅に減少しているのは、物価高と住宅ローン・教育費との兼ね合いによる「支出の選別」が背景にあります。
階層別に見る特徴と支出構造
高所得層:1500~2000万円、2000万円以上
-
支出額:2155円、1442円
-
特徴:自宅の管理を外注化し、労働からの解放と快適さを重視。庭の設計からメンテナンスまでを1括委託する傾向が強く、いわば「時間を買う」消費形態。
-
課題:2000万円超の層は前年比で-28.37%と大幅減。富裕層の中でも節約志向が高まっており、「贅沢の見直し」や資産保全が意識され始めている可能性があります。
中堅所得層:800~1000万円
-
支出額:800~900万は424円、900~1000万は596円
-
動き:特に900~1000万層で+6522%という爆発的な増加。この層は、かつては「節約志向」だったものの、物理的・時間的余裕が生まれたことで庭の管理を1部外注し始めたと見られます。
-
今後の課題:住宅価格や教育費とのバランスが厳しく、支出増が継続するかは不透明。
中間層:400~800万円
-
支出額:軒並み200~400円台
-
傾向:400~500万は-35.1%、500~600万は-61.5%と大きく減少。高齢化で庭を縮小・放棄するケースや、DIY志向の拡大も影響していると考えられます。
低所得層:200~400万円
-
支出額:200~300万は248円、300~400万は322円
-
特徴:支出額は小さいが、200~300万円層は前年比+230.7%と急増。この背景には、生活保護世帯や高齢者世帯における最低限の外注ニーズの顕在化があり、「自力での維持が限界」という実態も浮かび上がります。
支出変動の背景にある社会的・経済的要因
時間資源と外注化の加速
年収が上がるほど、時間単価が高くなり「自分でやるより任せた方が合理的」という考え方が1般化。高所得層ほど庭の管理を外部に委託する傾向が強まっています。
高齢化と労働負担の転換
中低所得層でも、高齢者や障がい者世帯では外注が必須となりつつあり、それが支出増に繋がっています。特に200~300万円層の増加はその傾向を如実に示しています。
インフレと節約志向
物価上昇によって「庭にまでお金を回せない」と考える層が増加。中間層での支出減少は、生活費の中での優先順位の低下を表します。
今後の予測と対策の方向性
富裕層の支出は安定か微増
今後も高所得層では外注による庭の手入れ需要が継続し、業者のサービスがより多様化・高品質化していくと考えられます。
中間層の2極化
中間層は「維持する層」と「削減する層」に分かれ、2極化が進む可能性があります。家族構成や住宅立地などによって大きな差が生じるでしょう。
低所得層の支援と地域サービスの重要性
高齢者の増加に伴い、シルバー人材センターや自治体の家事支援サービスの整備が不可欠。最低限の庭管理が健康や防犯上も重要であることから、公共的な支援の議論が必要です。
おわりに ― 庭を守るという生活文化の継承
庭の手入れ代は単なる生活支出ではなく、家庭の豊かさと余裕を象徴する支出でもあります。今後は、所得にかかわらず、どのように庭という空間を維持し、活かしていくかという視点が問われていく時代になるでしょう。支出データからは、日本社会の格差、時間の価値、そして生活の質をめぐる選択のリアルが浮かび上がっています。




コメント