2025年3月時点の家計調査によれば、全国の勤労世帯あたりの18歳未満人員数は0.84人で、地方都市を中心に増加傾向が見られた。一方で都市部や北陸・近畿の一部では顕著な減少も確認される。本稿では、過去から現在にかけての推移、都市間・世代間の特徴、そして今後の予測を詳述し、出生率や人口移動との関係を含めて丁寧に解説する。
18歳未満人員数の家計調査結果
18歳未満人員数の多い都市
18歳未満人員数の少ない都市
これまでの18歳未満人員数の推移
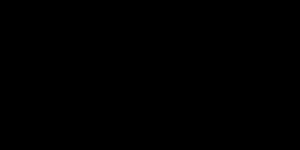
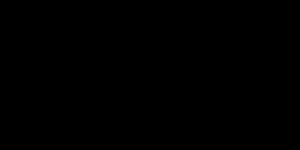
詳細なデータとグラフ
18歳未満人員数の現状と今後
全国の18歳未満人員数は、2000年代初頭から1貫して減少傾向にあった。背景には少子化の進行があり、特に都市部では晩婚化や共働き世帯の増加、住宅コストの高さなどが出産意欲の低下に拍車をかけてきた。しかし2020年代以降、地域によっては回復の兆しも見られている。
2025年3月時点では、全国平均で0.84人と依然として1人を下回る水準だが、増加傾向に転じている都市も多く、少子化の1様な進行ではなく、地域間格差が広がっていることがうかがえる。
18歳未満人員数の高い都市とその特徴
上位10都市を見ると、鹿児島市(1.34人)、新潟市(1.31人)、山形市(1.30人)など、いずれも地方都市が中心である。注目すべきは、鹿児島市の前年同期比+97.06%、新潟市の+45.56%、松山市の+57.89%という急増である。
これらの都市には共通して以下のような特徴がある。
-
住宅費が比較的安価:郊外に戸建てを持つことが容易で、子育て世帯の定住につながる。
-
自治体の子育て支援策が手厚い:保育料無償化、給食費補助、第3子以降支援など。
-
3世代同居が根付いている文化圏:育児負担の分散と就業継続が可能。
特に鹿児島や新潟では、Uターン就職やリモートワークの普及が1因と考えられ、都市部からの人材流入も要因となっている可能性がある。
18歳未満人員数の低い都市とその背景
1方で、富山市(0.49人)、長野市(0.51人)、神戸市(0.52人)などは大きく減少している。富山市の前年同期比-48.42%、千葉市の-35.96%、宇都宮市の-36.61%といった数値は衝撃的である。
要因としては以下が考えられる。
-
若年層の流出:大学進学や就職で都市圏に流れる傾向が強く、定住が進まない。
-
高齢化率の上昇:核家族化が進行し、若い世帯が少数。
-
育児環境の制約:都市部に比べて医療・教育インフラが不足気味、あるいは選択肢が限られる。
また、近畿・北陸圏のいくつかの都市(福井市、京都市、奈良市など)も減少が著しく、地域経済の停滞や人口流出が大きな課題となっている。
世代間の構造と人口ボーナスの終焉
世帯あたりの18歳未満人員数は、単に出生数だけでなく、世帯構造に強く影響される。たとえば「親と子のみ」の核家族より、「親・子・祖父母」の複合世帯では育児がしやすく、子ども数が多くなりやすい。
かつては団塊ジュニア世代が子育て期を迎え、人口ボーナス期として1定の子ども数が維持されていたが、現在は団塊ジュニアも50代となり、その影響はほぼ消滅した。代わって人口減少と世代交代が進む中で、「1人っ子世帯」が標準化しつつある。
今後の予測と政策的課題
都市によっては増加が見られるが、これは1時的な要因の可能性もある。特に出産適齢期の女性人口が今後減少するため、長期的には再び低下に転じる可能性が高い。
政府および自治体の対応としては以下が求められる。
-
定住支援と若年層の雇用創出 地方移住者への住宅・就業支援を通じて、子育て世帯の流入促進を図る。
-
教育・医療インフラの充実 安心して子どもを育てられる環境整備が求められる。
-
再分配政策の見直し 子育て世帯への給付強化や税制優遇が少子化対策として有効。
-
柔軟な働き方と育児の両立支援 男性の育児3加推進や、保育サービスの充実が鍵を握る。
おわりに
18歳未満人員数の推移は、単なる出生統計にとどまらず、都市のあり方、暮らしの構造、地域経済の今後を映す鏡である。1部地方都市での回復は希望の兆しである1方、それが持続的であるかは不透明であり、今後の行政の手腕が問われている。特に都市間格差や、子どもを持つことの「損得勘定」から解放された社会構築が、喫緊の課題となろう。




コメント