2017年から2025年3月までのデータをもとに、年齢別に見る食卓セット支出の動向を分析。特に40~44歳層での支出が急増しており、+383.3%の伸びを記録。共働き・子育て世代の利便性ニーズが背景にある。一方、50代以降は全体的に支出が減少。高齢層では再び需要が高まる兆しも見える。今後は世帯構造の変化とライフスタイルの多様化が影響を与えると予測される。
年齢別の食卓セット
1世帯当りの月間支出
これまでの年齢別の推移
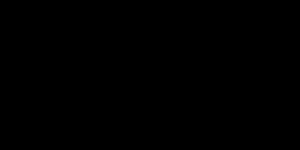
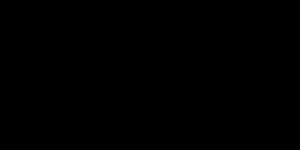
詳細なデータとグラフ
年齢別の現状と今後
食卓セットとは、家庭の食事に必要な調味料や簡易惣菜、調理キットなどをひとまとめにした商品群で、主に「手軽さ」「時短」「バランスの良い食事」が特徴である。近年の物価上昇や共働き世帯の増加、調理負担の軽減ニーズと相まって注目されている。特にコロナ禍以降は中食市場と重なりながら需要が拡大し、年齢別の動向に明確な違いが表れている。
年齢別支出の全体傾向
2025年3月時点の最新データによると、全年齢層の平均支出は117.1円と控えめだが、世代ごとの支出には大きな差がある。最も高いのは40~44歳の493円で、次に35~44歳の334円、40~49歳の306円が続く。1方、85歳以上では79円と支出は大きく下がる傾向がある。支出が高い層と低い層でその背景にある生活様式や消費意識の差が浮き彫りとなっている。
40代の支出急増の背景
40~44歳が+383.3%、35~44歳も+185.5%という大幅な増加率を示している。これは次の要因が考えられる:
-
共働き・子育て世帯のピーク層:仕事と育児の両立により、調理の手間を省くニーズが急増。
-
可処分所得の相対的高さ:30代後半~40代前半は給与水準も安定し、外食よりも「家で時短かつ健康的」な中食需要が拡大。
-
EC・サブスクの普及:食卓セットをネット注文や定期購入する家庭が増加。導入障壁が下がった。
50代以降の支出減少の要因
50代から60代にかけて支出が減少しているのは、以下の理由が主と考えられる:
-
子育て終了による家庭人数の減少:夫婦のみ、あるいは単身生活となり、まとめ買いの必要が薄れる。
-
手作り回帰・健康志向の高まり:自炊を好む傾向があり、加工食品やキット商品への依存度が低い。
-
支出の最適化意識:リタイアを見据えて支出全般を抑制する傾向がある。
特に45~49歳では前年比-65.98%と大幅な減少が目立つ。これは、家計の見直しや物価高騰を受けて支出先の選定がシビアになっていることも関係している。
85歳以上の意外な支出増加
高齢層(85歳~)は支出額自体は少ないが、前年同期比で+229.2%と急増している。この動きには以下が影響していると見られる:
-
介護・支援サービスとの連携:1部の自治体や介護施設では、調理負担軽減の1環としてミールキットの導入が進んでいる。
-
家族との同居や支援世帯の支出:高齢者が同居する家庭では、栄養バランスを重視した食卓セットが活用される傾向がある。
今後の展望と政策的課題
今後、食卓セットの支出は以下のような変化が予測される:
-
若年~中年層でのさらなる定着:共働き比率が高止まりし、宅配型サービスとの融合により利便性が拡大。
-
高齢層向け市場の新展開:嚥下や栄養ケアを意識したシニア向けのミールセットが進化すれば、新たな需要が開拓される。
-
政策支援の必要性:低所得・高齢世帯への栄養確保と物価対策のため、自治体レベルでの補助や配達支援が鍵となる。
まとめ ~世代によって異なる“食”のかたち~
年齢によって、食卓セットへの関心・必要性・支出余力は大きく異なる。40代は「利便性と効率」、50代以降は「自立的な調理」、高齢層では「支援と健康維持」が主軸となる。今後のマーケティングや政策立案においては、こうした世代ごとの違いを十分に踏まえる必要がある。




コメント