2025年3月の食卓セット支出では給与住宅世帯が最も高く、賃貸民営住宅は最低。支出の格差は住宅形態の特性やライフスタイルの違いによる。特に転居の多い給与住宅や家具の老朽化が進む公営住宅では支出が高めだが、民営賃貸では支出が抑制傾向。今後は家具のサブスクや省スペース志向が支出動向を左右すると予測される。
住宅別の食卓セット
1世帯当りの月間支出
これまでの住宅別の推移
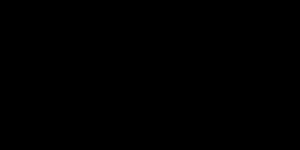
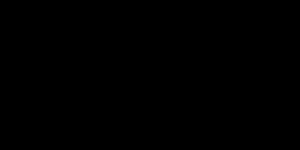
詳細なデータとグラフ
住宅別の現状と今後
食卓セットの購入は、生活空間の余裕、ライフスタイル、所得、住宅の所有形態と密接に関連しています。特に近年の物価上昇や住宅事情の変化により、支出の差が住宅形態によって顕著になってきました。本章では、2017年から2025年3月までのデータをもとに、住宅別の食卓セット支出の特徴と今後の見通しを読み解きます。
データの概要 ― 住宅形態別支出の順位と平均値
2025年3月時点での住宅別食卓セットの平均支出は236.1円ですが、形態によるばらつきは非常に大きくなっています。
支出額の高い順に並べると:
-
給与住宅:728円
-
その他:362円
-
持ち家(住宅ローンあり):178円
-
持ち家(ローンなし):116円
-
公営住宅:112円
-
民営住宅:40円
この差には、住まいの性質や住民の経済状況、転居の頻度、生活の安定性などが大きく影響しています。
住宅形態別の支出傾向と背景
給与住宅
企業から提供される住宅に住む世帯は、転勤や新生活に伴う家具購入のタイミングが多く、728円と群を抜いた支出額となっています。新規入居時や単身赴任、家族帯同などで食卓セットを新調する傾向があり、家具付きでない場合は自費購入が必要になるため支出が大きくなります。
「その他」住宅
これは寮や社宅などの特殊な住宅形態を含む可能性があり、362円と高額ながら、前年同期比では-51.34%と急減。1時的な設備更新需要が1巡した可能性や、家電・家具備え付けの住宅が増えたことが影響していると考えられます。
持ち家(ローンあり・なし)
住宅ローンを抱える世帯では178円とやや高めだが、-42.58%と大幅に減少。家具よりも住宅ローン返済に重きを置いているとみられます。1方、ローンのない持ち家では116円にとどまり、-40.21%の減少。高齢世帯の比率が高く、買い替えニーズが少ないことが背景と考えられます。
公営住宅
低所得者層の居住が多い公営住宅ですが、今回のデータでは+143.5%と異例の増加。家具の老朽化や新規入居者の家具需要、あるいは補助制度による購入の影響があった可能性があります。
民営住宅(賃貸)
最も支出が低いのが民営住宅(40円)で、-87.92%という劇的な減少。賃貸物件に住む若年層や単身世帯では、引っ越しのしやすさやミニマル志向が強く、大型家具である食卓セットは敬遠されがちです。
住宅形態による生活スタイルの違い
住宅形態ごとに住人の年齢層、所得、転居頻度、所有意識が異なります。
-
給与住宅・その他:流動性が高く、新生活にあわせた家具購入が頻繁。
-
持ち家:長期居住を前提にするが、1度そろえた家具を使い続ける傾向。
-
公営住宅:支出余力が限られるが、生活基盤再建時の需要もある。
-
民営住宅:家具付きやコンパクトな生活様式が主流。支出は最小限。
今後の予測と市場の方向性
今後、以下のような動きが想定されます:
-
家具レンタル・サブスクの浸透特に賃貸層を中心に、「買わずに使う」選択が広がることで、家具購入支出はさらに抑えられる可能性があります。
-
省スペース化と可動性重視の家具増加小型住宅に合わせ、折りたたみや収納機能付きの食卓セットが増加。家具業界の方向性もこれに対応する必要があります。
-
高齢者向け買い替え需要の局所的増加持ち家に住む高齢層では、1度購入した家具が劣化し、買い替えが必要になる時期に入るため、限定的に需要が再燃する可能性があります。
まとめ
食卓セットの支出額は住宅の種類によって大きく異なり、特に給与住宅や1部の持ち家で高い支出が確認される1方、賃貸・民営住宅では支出が抑えられています。物価高やライフスタイルの変化により、今後は「所有」から「利用」への転換が進む中で、家具の在り方そのものが変わる過渡期に入っていると言えるでしょう。




コメント