2025年3月時点の家計調査によると、繰入金の全国平均は29.17万円。東京都区部が突出して高く、奈良市や宇都宮市も上位に位置する一方、鹿児島市や新潟市などでは低水準にとどまる。都市間の経済格差や家計余裕度の差、世代ごとの家計構造の違いが背景にあり、今後は物価上昇と所得の地域差が動向に影響すると見られる。本稿では繰入金の推移や問題点、都市・世代別の特徴、将来予測について丁寧に解説する。
繰入金の家計調査結果
繰入金の多い都市
繰入金の少ない都市
これまでの繰入金の推移
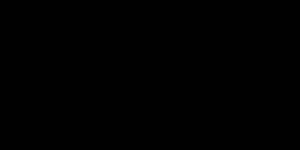
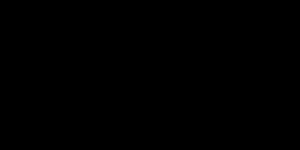
詳細なデータとグラフ
繰入金の現状と今後
繰入金とは、家計において他の金融資産や預貯金から生活費へ補填する金額、または年金や保険の満期返戻金、1時金的な補助金、親族からの仕送りなど臨時的収入を差します。勤労世帯にとって、これは日常生活を支える「予備的な手段」としての役割を果たしています。特に不測の支出が発生した際、繰入金が生活を支える緩衝材として機能します。
全国平均の推移と都市別上位の特徴
2025年3月の全国平均繰入金は29.17万円。2000年代初頭には20万円前後で推移していたと考えられ、コロナ禍や物価高騰の影響で年々増加傾向にあります。
上位都市の特徴:
-
東京都区部(77.87万円)首都圏でありながら生活費の高さに加え、高所得層の余剰資金運用の影響が大きい。資産からの取り崩しや企業経営者の繰入が多いと推測。
-
奈良市(60.96万円)・宇都宮市(51.38万円)・仙台市(49.68万円)地方中核都市においては、高齢世帯や2世帯住宅の割合が高く、退職金や貯蓄の取り崩しによる繰入が目立つ。
-
高知市(36.52万円)増加率が+233.2%と急上昇しており、1時的な要因(災害補助金や相続など)が影響している可能性がある。
これらの都市に共通するのは、「現役世代だけでなく、金融資産保有層の動きが反映されやすい」点です。
繰入金が少ない都市の課題と背景
1方、繰入金が少ない都市(鹿児島、新潟、長崎、松山、山口など)は、いずれも地方都市であり、所得水準が相対的に低く、可処分所得に余裕がない世帯が多いとされます。
特徴的な傾向:
-
金融資産の蓄積が乏しい世帯が多い
-
生活費に対して手取り収入でやりくりする傾向が強く、繰入の余地が少ない
-
親世代からの支援や副収入も限定的
また、長崎市は-77.25%という大幅な減少を示しており、制度変更や補助金の打ち切り、1時金の終了など政策的要因も影響している可能性があります。
世代間での特徴と構造的要因
繰入金の多寡は世代間でも明確な差があります。
-
高齢世代(60代以上)貯蓄からの取り崩しが多く、退職金や年金の1部を臨時的に繰入れるケースが多い。
-
中年世代(40〜50代)子育て支出のピークと住宅ローン返済が重なり、繰入は増減が激しく、ボーナス時期に左右されやすい。
-
若年世代(20〜30代)所得水準が低く、そもそも繰入対象となる貯蓄が少ないため、全体的に繰入額は少なめ。
こうした世代間ギャップは、「貯蓄からの繰入余力」という面で地方と都市圏の違いよりも顕著に現れる傾向があります。
繰入金増減の要因分析
繰入金の増減には以下のような要因が複雑に絡んでいます:
-
経済的イベント(リーマンショック、コロナ、物価高騰)
-
政策的変化(給付金、1時金の有無)
-
所得水準の伸び悩み
-
世帯構成の変化(単身化、共働きの増加)
-
資産の偏在(富裕層と1般層の格差拡大)
たとえば東京都区部の+116.7%という急増は、資産取り崩しが進んでいる1方で、相続・贈与による資産移転が背景にあると見られます。
今後の動向と展望
◆短期的見通し(~2026年)
物価高が続く限り、生活防衛的な意味合いで繰入金は増加傾向を維持。特に都市圏では年金受給前後の世代の繰入が活発になる可能性があります。
◆中長期的見通し(~2030年)
-
地方における繰入金の低水準は続く可能性が高く、都市と地方の「生活力格差」が広がる。
-
若年世代の金融リテラシー向上や投資志向が進めば、将来的には繰入金の構成にも変化が現れる可能性あり。
-
高齢世帯の繰入過多は、今後の資産枯渇リスクを高める要因にもなりうる。
繰入金から見える家計の現実
繰入金という項目は、単なる「余剰資金の補填」にとどまらず、日本の家計が直面している構造的課題—資産格差、地域格差、世代間格差—を映し出す指標でもあります。今後、可視化と政策的なサポートが求められる分野となるでしょう。


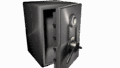

コメント