2025年3月までの家計調査によれば、全国の持家率は87%と高水準を維持する一方、都市間での格差が顕著となっている。横浜市や相模原市では90%超の高い持家率が見られるが、那覇市や札幌市などでは50~70%台と低水準にとどまっている。世代間の資産格差や都市構造、人口流動性の違いがこの差を生んでおり、今後の住宅政策にも大きな影響を及ぼすと考えられる。
持家率の家計調査結果
持家率の多い都市
持家率の少ない都市
これまでの持家率の推移
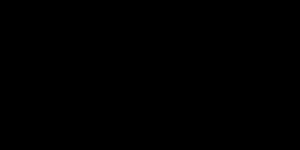
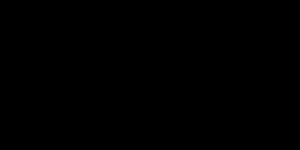
詳細なデータとグラフ
持家率の現状と今後
2008年から2025年までの家計調査のデータによれば、日本全体の持家率は高水準を維持しており、最新値で87%に達している。これは国際的に見ても高い水準であり、長年にわたって日本社会で「持ち家こそが安定」の価値観が定着していることの現れだ。
バブル崩壊以後も地方を中心に持家志向は根強く、特に郊外・地方都市では土地取得や建築費の相対的安さも背景にあり、高い持家率を支えてきた。1方で都市部、とりわけ地価が高く住宅供給の構造が賃貸重視となりやすい地域では、持家率が相対的に低くなる傾向がある。
持家率の高い都市の特徴
横浜市(98.2%)、相模原市(96.1%)、福井市(96%)など、90%を超える都市では、いくつかの共通点が見受けられる。
-
郊外型住宅地の広がり:特に相模原市や横浜市では、郊外型の戸建て住宅地が大きく開発され、家を購入して移り住む層が厚い。
-
安定した中高年層の存在:福井市や津市、新潟市などは、若年層の都市流出がありつつも、地元定着型の高齢層が多く、住宅ローン返済を終えた世代による「完済持ち家」が支配的。
-
比較的安価な地価と土地保有文化:中部地方や北陸では地価の安さに加え、「土地を持つことが当然」という価値観が根強い。
持家率の低い都市の事情
那覇市(49.4%)、札幌市(68.2%)、盛岡市(74%)など持家率の低い都市には、異なる社会構造がある。
-
地価と賃貸市場の発達:那覇市や札幌市は地価の高さと都市集中が進んだ結果、分譲よりも賃貸の方が選ばれやすい構造となっている。
-
移動・転勤が多い地域構造:札幌市や広島市のような拠点都市では、企業の支店や官公庁が集まり、転勤族の需要が多く、賃貸市場が厚い。
-
若年層比率が比較的高い:若年層が多く定住前の賃貸暮らしを続ける傾向があることも、持家率の低さに影響している。
世代間での持家観と格差
かつては「結婚して家を買う」が人生設計の基本とされたが、現代ではその構図は崩れつつある。特に若年層では、住宅ローンへの不安や将来の不確実性から、賃貸を選ぶ傾向が強まっている。
さらに、非正規雇用の拡大や物価上昇に対し賃金が伸び悩む中で、20代・30代が家を買える資力を持ちにくくなっている。1方で、高齢世代は既にローン完済済みの家を所有しており、こうした世代間の「住宅資産格差」が深刻化している。
持家率の増減が示す社会の変化
注目すべきは、横浜市(+9.232%)や相模原市(+13.73%)など都市圏でも持家率が急上昇している点である。これは近年の低金利環境を活かして、比較的若い世代がマンションなどを取得している可能性がある。
1方、那覇市(-14.97%)や甲府市(-15.3%)のように、急激な減少が見られる都市では、人口流出・高齢化・住宅の老朽化など多面的な要因が絡み合っていると考えられる。
今後の見通しと課題
将来的には以下のような動向が想定される:
-
空き家問題の顕在化:地方では持ち家はあっても住む人がいない「空き家」が急増。放置すれば都市景観や治安にも影響。
-
都市部での購入困難の増加:都市中心部では住宅価格の上昇が進み、1般的な家庭には手の届きにくい水準になりつつある。
-
住宅政策の多様化が必要:若年層向けの購入支援、高齢者の住み替え促進、空き家の流通活性化など、世代や地域に応じた政策が不可欠になる。
まとめ:持家率の先に見える日本社会の選択肢
持家率という指標は単なる住宅の所有比率ではなく、日本社会の「定住性」「資産形成」「地域のつながり」など、多くの社会的要素を映し出す鏡である。都市間・世代間の持家率の格差が拡大する中、どのように住まいを位置づけ、社会として支えるかが問われている。個人の選択を尊重しつつも、誰もが安心して暮らせる住環境を整備する政策が今後の焦点となるだろう。




コメント