2025年3月時点の家計調査によると、勤労世帯の外食支出は全国平均で1.824万円。東京都区部やさいたま市、熊本市など都市部で高額傾向にあり、福岡市は前年比+45%と急伸。一方で神戸市や金沢市などでは大幅な減少が目立つ。背景には物価高、テレワーク普及、家族構成の変化などが影響。世代や地域によりニーズが分かれる中、今後も都市部での二極化傾向が進行すると予測される。
外食(勤労)の家計調査結果
外食(勤労)の多い都市
外食(勤労)の少ない都市
これまでの外食(勤労)の推移
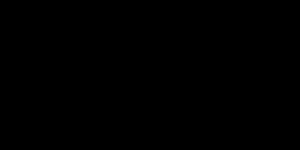
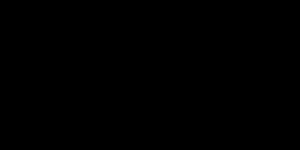
詳細なデータとグラフ
外食(勤労)の調理品・外食現状と今後
勤労世帯の外食支出は、2000年代初頭から緩やかな上昇を続けてきました。リーマンショック後の1時的な冷え込みを経て、特に2010年代後半から2020年直前までは、共働き家庭の増加や時短ニーズにより再び上昇基調に戻りました。
2020年からの新型コロナウイルス感染拡大によって外食支出は1時的に大きく落ち込みましたが、2023年以降は回復傾向が顕著となり、2025年3月時点では全国平均で1.824万円と、過去の水準を上回る水準に到達しました。
都市別の支出額トップとその背景
最新データで外食支出が高かった都市トップ10は以下の通りです:
-
東京都区部:2.712万円
-
さいたま市:2.666万円
-
熊本市:2.5万円
-
千葉市:2.466万円
-
名古屋市:2.448万円
-
横浜市:2.202万円
-
奈良市:2.197万円
-
京都市:2.167万円
-
大阪市:2.154万円
-
福岡市:2.146万円
これらの都市に共通する特徴は、都市中心部へのアクセスの良さ、共働き世帯比率の高さ、可処分所得の1定水準の維持です。特に福岡市(+45.07%)や熊本市(+22.66%)など9州圏では、外食文化の根強さと新店舗の増加が支出を押し上げた要因とみられます。
東京都区部の高水準は1貫しており、これは「外食が日常である」という都市生活者の価値観に加え、外食店の選択肢の多さや利便性が背景にあります。
支出が少ない都市の共通点と課題
1方で、支出が最も少なかった都市は以下の通り:
-
神戸市:0.996万円(前年比 -40.77%)
-
青森市:1.12万円
-
金沢市:1.227万円
-
堺市:1.263万円
-
宮崎市:1.272万円
-
徳島市:1.321万円
-
和歌山市:1.326万円
-
山口市:1.345万円
-
岐阜市:1.442万円
-
浜松市:1.482万円
神戸市の急減や堺市、岐阜市などの大幅な減少は、地元飲食業の衰退や物価上昇による節約志向の強まり、また中高年世代の比率が高いことによる保守的な食生活が影響していると考えられます。
これらの地域では、外食への心理的・経済的ハードルの高さが依然として存在し、「調理して食べる」というライフスタイルが根強く残っています。
世代間で見る外食の価値観の変化
世代ごとに見ると、20~40代の現役世代では「時短・利便・味の多様性」を重視し、外食に対して比較的積極的です。特に若年層では、飲食店を「交流の場」としてとらえる傾向が強く、コストよりも体験を重視するケースが多く見られます。
1方、60代以上の高齢層では健康意識や節約志向が強く、また物価上昇に対する耐性も低いため、外食を控える傾向が鮮明です。地域社会に根差した生活が中心であり、「自宅で手料理」が生活スタイルに定着しています。
物価高騰・賃金上昇との関係
近年の外食支出は、物価高騰と実質賃金の伸び悩みという相反する要素のはざまで揺れ動いています。外食価格の上昇により「外食離れ」が起きる1方で、「中食(調理済み食品)」や「安価な外食チェーン」への需要はむしろ高まっています。
地域によっては、地元密着型の定食屋や回転寿司などの利用が中心となる1方、都市部ではサブスクリプション型外食サービスや高単価の専門店の利用も増加しており、所得階層や地域特性によって大きく消費スタイルが分化しています。
今後の予測と政策的示唆
外食支出は、短期的には都市部での2極化傾向が続くと考えられます。高所得層は外食への支出を増やす1方、中所得以下の層では「安くて早い」外食に集中し、それ以外は節約志向が強まるでしょう。
また、地方都市では飲食店の撤退や人手不足が続けば、そもそも「外食の選択肢がない」という供給制約が深刻化する可能性もあります。
政策面では、地元飲食店支援策や低所得世帯向け食生活支援、また健康的な外食メニュー開発の奨励などが必要とされます。加えて、テレワークの定着により「オフィス外食」が減少した分、家庭周辺での需要をどう掘り起こすかが鍵になります。
結びに
勤労世帯の外食支出は、単なる「食事」の問題ではなく、ライフスタイル・地域経済・雇用構造と深く結びついた社会的テーマです。支出額の裏にある背景を理解することで、今後の生活政策や地域活性化策の方向性が見えてくるでしょう。




コメント