2025年3月時点の家計調査によると、全国平均の通信費は1.219万円で、熊本市や岐阜市などでは高額な一方、神戸市や長崎市では大幅減が見られました。本稿では、2008年以降の通信費の推移、都市間の格差、世代ごとの通信習慣の違い、スマートフォンの普及や格安プランの影響を踏まえ、今後の通信費の方向性を丁寧に解説します。
通信の家計調査結果
通信の多い都市
通信の少ない都市
これまでの通信の推移
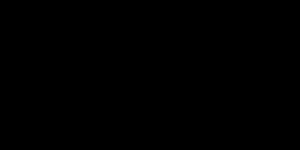
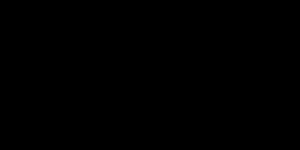
詳細なデータとグラフ
通信の現状と今後
2008年から2025年にかけて、家庭の通信費は明確な構造変化を遂げてきました。2008年頃は固定電話とインターネット接続が主な支出でしたが、2010年代前半からスマートフォンの普及により、携帯通信費の比重が急増しました。
特に2015年以降は「3大キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク)」による高額プランが家計を圧迫し、通信費は1世帯あたり月額1.2〜1.5万円前後で推移するようになります。2020年以降、政府の「携帯料金引き下げ政策」や「楽天モバイルの新規3入」「格安SIMの普及」によって、ある程度の抑制効果が見られるものの、世帯構成や地域によって支出額に大きな差が残ります。
2025年の地域別動向とその背景
2025年3月時点での1世帯あたりの通信費は全国平均で1.219万円ですが、以下のように都市間で大きな開きがあります。
高い都市の傾向:
-
熊本市(1.586万円・+22.73%)
-
岐阜市(1.431万円・+8.53%)
-
山形市(1.408万円・+24.14%)
-
高松市(1.36万円・+44.03%)
これらの都市では、以下のような要因が高額支出の背景にあると推測されます:
-
光回線や高品質プランの加入率が高い
-
家族世帯比率が高く、複数回線契約が1般的
-
地域密着型プロバイダやローカル携帯会社が少なく、競争が弱い
低い都市の傾向:
-
神戸市(0.735万円・-28.03%)
-
長崎市(0.773万円・-25.8%)
-
津市(0.91万円・-18.34%)
これらの地域では、
-
高齢世帯の比率が高く、スマートフォンの利用頻度が低い
-
格安SIMやプリペイド型の利用が多い
-
通信費節約意識の浸透
などが背景にあると考えられます。特に神戸市や長野市のような都市では、人口構造と情報リテラシーのバランスが強く通信支出に影響している可能性があります。
世代間で異なる通信習慣
若年層(20〜40代)
-
高額プラン利用が多い
-
スマートフォン・タブレット・ゲーム機・サブスクとの複合利用
-
モバイル通信が中心で、Wi-Fi環境にあまり依存しない傾向も
高齢層(60代以上)
-
フィーチャーフォン(ガラケー)や格安スマホの利用者が依然として1定数存在
-
ネット利用は必要最小限で、通信費も抑制的
-
自治体が提供するデジタル支援講座の影響で利用が拡大する地域もあり
このように、世代によって通信費の使い方が根本的に異なるため、都市別平均にも大きな影響を与えています。
通信環境と政策の影響
日本の通信費の構造には、以下のような外的要因が絡んでいます:
-
政府の携帯料金引き下げ圧力(2020年〜)→ 価格競争が生まれ、家計支出の圧縮が進行中
-
5Gの普及とプランの高額化→ ハイスピード通信の恩恵と引き換えに1部世帯では支出が拡大
-
固定回線 vs モバイル回線の競合→ 1部では「固定回線をやめる家庭」も増加し、構成比の変化が生じている
今後の予測と課題
今後の通信費は以下のように推移していくと見られます:
地域格差は縮小するが、完全解消は困難
格安プランや新興事業者の進出により、通信費の格差はやや縮まる見通し。ただし、高齢者や情報弱者を多く抱える地域では節約が進みにくい可能性あり。
通信の複雑化と分散化
通信サービスが「回線費」「サブスクリプション費」「データ容量」など多様化しており、世帯の構成や価値観によって通信費の定義そのものが変わりつつある。
通信支出の中に「教育・娯楽」要素が増加
リモート授業、配信コンテンツの常用化により、単なる「情報通信」から「生活基盤」への昇格が続いており、今後も1定の通信費は維持される可能性が高い。
まとめ
日本の通信費は、スマートフォンの普及と政策的誘導によって多様化・2極化が進みました。地域や世代によって支出に大きな差があるものの、今後は格安サービスや5Gの普及によって徐々に再均衡が図られる見込みです。ただし、通信環境へのアクセスそのものが「格差の再生産」になりかねないという点では、今後も政策的支援と教育啓発が求められます。




コメント