家計調査によると、二人以上世帯における「身の回り用品」支出の平均は2075円で、都市間で大きな差が見られます。広島市や大分市では急増する一方、札幌市や堺市などでは減少傾向が顕著です。本稿では、これまでの動向や都市・世代ごとの特徴、背景にある生活様式の変化、今後の予測について章立てで解説します。
身の回り用品の家計調査結果
身の回り用品の多い都市
身の回り用品の少ない都市
これまでの身の回り用品の推移
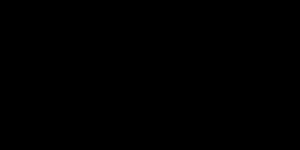
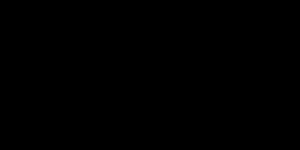
詳細なデータとグラフ
身の回り用品の諸雑費現状と今後
身の回り用品とは、日常生活で使用する小物や消耗品を指します。例としては、傘、ハンカチ、ポーチ、裁縫用品、靴ひも、ベルト、手袋などが含まれます。これらは生活必需品ではあるものの、購入頻度や金額には家庭の価値観や生活様式が色濃く反映されます。
2008年以降の全体的な支出傾向
2008年から2025年3月までのデータを振り返ると、身の回り用品の支出は長期的に見ると緩やかな増減を繰り返しており、明確な右肩上がりのトレンドは見られません。平均支出は2000円前後で推移しており、家計の中では比較的小さな変動範囲に収まっています。
コロナ禍では、外出機会の減少により消費は1時的に抑制されましたが、その後のリベンジ消費や衛生意識の高まりで部分的な回復も見られました。
都市間での支出差とその背景
高支出都市の特徴
-
広島市(5039円、+136.5%):地場産業である繊維や雑貨製造の存在が関連している可能性あり。加えて、駅前開発などでショッピング施設が充実しており購買機会が多い。
-
大分市(4003円、+171.8%):前年比で2.7倍近く増加。地方都市の中でも支出が突出しており、生活雑貨への1括購入傾向が推察される。
-
前橋市(2770円、+265%):急増は1時的な特需や、調査対象家庭の世帯構成変化が影響か。
低支出都市の特徴
-
青森市(723円、-30.88%)・札幌市(772円、-52.46%):寒冷地では実用的で長く使える製品の選好が強く、買い替え頻度が少ない傾向。
-
堺市(1260円、-61.93%)・津市(1128円、-66.19%):西日本都市での著しい減少は、生活コスト圧縮や低価格帯商品へのシフトが考えられる。
世代間での消費傾向の違い
若年層
ファッション雑貨や流行小物を含む傾向が強く、支出は1時的に高くなることも。100円ショップやファストファッションでの購入が主流。
中高年層
耐久性や実用性を重視。買い替え周期が長く、全体として支出は安定的。ネット購入も増加中だが、実店舗志向が根強い。
高齢世帯
不要不急の支出を控える傾向があり、身の回り用品の支出は最も少ない層。必要なものは昔から所有しており、消費には慎重。
今後の支出推移の予測
ネット通販の普及による価格の下落
Amazonや楽天での価格競争が支出額を抑える方向に作用。特に若年層を中心に、実店舗での購入が減り続ける可能性がある。
高齢化による支出の鈍化
高齢化が進むにつれて、身の回り用品への支出は全国的に減少する傾向が強まると予想されます。今後、全体平均が2000円を下回る時期もあるかもしれません。
環境志向と長期使用志向の広がり
脱プラスチックや「使い捨て文化」からの脱却が進むことで、安価で大量消費されてきたアイテムの購入頻度は減少し、逆に「少し高くても長持ちするもの」へのシフトが進行。
まとめ
身の回り用品の支出は、日常生活の中での「ちょっとした余裕」や「生活スタイルの個性」が反映される消費分野です。都市ごとの経済構造や気候、生活文化、さらには世代ごとの価値観が大きく関わるため、単純な価格比較では測れない深みがあります。今後も、生活様式の多様化や人口構成の変化により、支出傾向は都市ごとにさらに分化していくと見られます。




コメント