総務省の家計調査に基づく2025年3月時点のデータによると、賞与(ボーナス)の全国平均は1.64万円である一方、都市間格差が顕著となっている。仙台市や北九州市などは前年から大幅増加したのに対し、青森市や千葉市などはほぼゼロに落ち込んでいる。長期的に見ると、景気変動や就労形態の変化、地域産業の構造によって、世帯ごとの賞与額に大きな差が生じている。今後は非正規雇用の増加や地域経済の停滞がさらなる格差を生む懸念もある。
賞与の家計調査結果
賞与の多い都市
賞与の少ない都市
これまでの賞与の推移
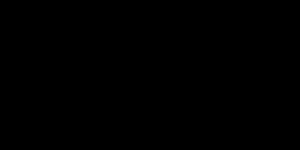
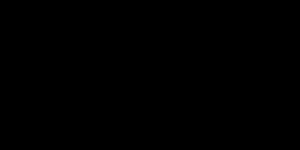
詳細なデータとグラフ
賞与の現状と今後
賞与は、日本の企業文化において長らく「夏と冬に支給される臨時収入」として定着してきた。総務省の家計調査においては、「繰越・臨時収入」の1部として分類され、勤労者世帯の可処分所得に対する重要な構成要素である。ただし、これは必ずしも毎月の給与と同様の安定収入ではなく、企業の業績や雇用形態、勤務期間に大きく左右される性質を持つ。
2025年3月時点の実態――都市間の極端な格差
今回のデータで特に注目すべきは、仙台市の1世帯あたり賞与額が8.145万円と全国平均の1.64万円を大きく上回っている点である。前年同期比+591.6%という急増ぶりも異常値である。他に山口市(5.521万円)、北9州市(5.396万円)なども高水準で、地域経済の回復や特定産業の好調さが影響している可能性がある。
1方で、青森市(0.0988万円)をはじめ、千葉市・浜松市・奈良市など9都市では賞与支給がほぼゼロで、前年同期比-100%という異常な状況が見られた。これは中小企業の業績不振や非正規雇用比率の高さ、自治体財政の硬直化などが背景にあると推察される。
賞与の長期的な傾向と背景
2000年以降の長期的トレンドを見ると、日本全体では「安定した賞与支給の崩壊」が進行している。特にリーマン・ショック(2008年)やコロナ禍(2020年)を境に賞与額が1時的に激減した後、正社員比率の減少と中小企業の比重増加により、全国平均額は回復しづらい状態が続いている。
さらに、企業側も業績連動型の賞与制度に移行し、固定賞与の保証が薄れている。また、非正規労働者には賞与が出ないことも多く、これが世代間・職種間・地域間の賞与格差の拡大につながっている。
地域間の構造的な差
都市間の賞与格差は、1過性の景気要因だけでなく、地域産業の構造そのものに根差している。例えば、製造業や重工業の比率が高い北9州市や岡山市では、業績連動の賞与が大きくなりやすい。1方で、公務員比率が高い地方都市では、賞与額は1定水準に保たれる傾向があるが、雇用政策の見直しや財政難により減額傾向も見える。
また、観光産業に依存する地域や人口減少が深刻な都市では、賞与支給自体が行われないケースが多い。青森や鳥取、盛岡などで前年からほぼゼロにまで落ち込んだ背景には、構造的な雇用不安と、業種の偏りが影響していると考えられる。
世代間の賞与観――「もらえないのが当たり前」へ
若年層(20~30代)においては、賞与に対する期待値自体が低下している。非正規雇用や契約社員として働く層が多く、賞与支給の前提となる勤続年数や評価制度に組み込まれていないためである。逆に、40~60代の正社員層では、年2回の賞与支給が生活設計に組み込まれており、これが支給されない場合の心理的・実質的ダメージは大きい。
このように、「賞与格差」は単なる金額の問題だけでなく、世代ごとの労働観やライフプランそのものに影響を与えていることが分かる。
今後の見通し――消滅と2極化の予兆
今後、賞与の支給状況は「都市部の大企業+高スキル職」に集中し、それ以外では限りなくゼロに近づくという2極化の道を辿る可能性が高い。テレワークや副業解禁の流れが進む中で、固定給・賞与という形態は時代に合わなくなり、成果報酬型やプロジェクトベースの支払い方式へと移行していくだろう。
また、政府の働き方改革や最低賃金の底上げが進む1方で、賞与のような変動収入には直接影響しづらく、地域格差はむしろ拡大する懸念が強い。


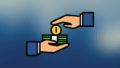
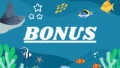
コメント