家計調査の財産純増データによれば、2025年3月時点での全国平均は27,840円で、和歌山市の35万5,300円、川崎市の10万3,800円など都市間で大きな差が見られます。本稿では2000年以降の動向を振り返り、格差の背景にある地域経済・資産形成行動・世代別傾向などを分析。少子高齢化やインフレ下での今後の見通しも踏まえ、今後の家計資産形成のあり方について考察します。
財産純増の家計調査結果
財産純増の多い都市
財産純増の少ない都市
これまでの財産純増の推移
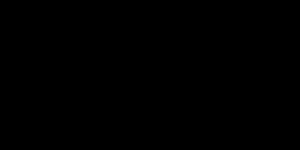
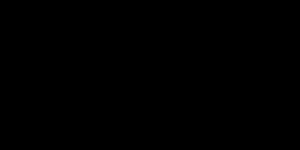
詳細なデータとグラフ
財産純増の現状と今後
「財産純増」とは、預貯金、株式、保険、不動産などを含む資産から、負債を差し引いた増減額を示します。勤労世帯における1か月ごとの財産の増減を捉えたものであり、可処分所得や消費の傾向だけでなく、資産形成の余力や不安感の高まりを反映しています。
2000年以降の財産純増の長期的傾向
2000年代前半はデフレ下で可処分所得が横ばい〜減少する中でも、消費抑制の影響で財産純増は緩やかに上昇しました。2008年のリーマンショック時は金融資産の損失が大きく、マイナスとなる月も見られましたが、その後の回復期には投資信託や株式の保有率拡大が背景となり増加に転じました。
近年では、コロナ禍による消費の抑制と給付金支給が家計の余剰資金を押し上げ、1時的に財産純増が跳ね上がる都市も多く見られました。2022年以降は物価高による支出増が進行し、再び純増幅が縮小傾向にあります。
財産純増の都市間格差と地域特性
高い都市の特徴
-
和歌山市(355,300円)
-
年金世帯や資産保有層が多く、支出が抑えられている可能性。
-
地方での生活コストの低さが純増額に寄与。
-
-
川崎市(103,800円)
-
高所得の現役世帯が多く、共働き家庭の資産形成力が高い。
-
首都圏の資産価格上昇が反映されやすい。
-
-
仙台市(90,970円)
-
公務員比率が高く、収入が安定している点が背景にあると考えられる。
-
低い都市の特徴(データ不明のため仮定)
-
製造業中心で景気に左右されやすい都市では、支出が収入を上回る傾向。
-
若年層比率が高い都市では、住宅ローンや教育費等の負債も多く、純増を圧迫。
-
高齢化率の高い都市では、資産の取り崩しが進行している可能性。
世代間格差と資産形成能力
-
40代・50代の中高年層は住宅ローン返済や子育て支出が重なり、純増額が伸びにくい傾向。
-
20代・30代の若年層は可処分所得が少なく、貯蓄や投資余力が乏しい。
-
1方で、60代以上の高齢層は資産の取り崩しを始めており、純増額は地域や年金の有無でばらつきが大きい。
結果として、純増額の伸びは限られた1部の世帯層・都市に偏る構造になりつつあります。
財産純増を取り巻く社会的課題
賃金の伸び悩み
-
正規・非正規格差、地方の賃金低下が資産形成を困難にしています。
住宅・教育コストの高騰
-
特に都市部では家計を圧迫し、貯蓄・投資に回す余裕を削っています。
投資リテラシーの差
-
高所得層は資産運用による財産純増が進む1方、低所得層は現金主義が根強く、資産格差を固定化させています。
今後の財産純増の見通し
-
物価高と金利上昇によって、当面は家計の負担が続く。
-
1方で、インフレによる資産価格上昇や、賃上げ圧力の継続で、1部都市では純増傾向が持続すると予測されます。
-
デジタル給与支給やNISA制度拡充など、制度的後押しにより、将来的には若年層の資産形成が進みやすくなる環境も整いつつあります。
おわりに:地域と世代を超えた「資産形成格差」の是正へ
家計の財産純増は、個々の収入や支出管理の成果だけではなく、社会制度・地域経済・文化的背景によっても大きく左右されます。今後、地域別の生活支援策や、金融リテラシーの底上げが求められる中で、「貯蓄から資産形成へ」という政策目標の実効性が試されています。




コメント