日本の住宅形態ごとに自動車整備費の支出には顕著な差があり、持ち家(住宅ローンあり)が最も高く月額4997円、公営住宅や給与住宅は2000円台と低水準です。住宅所有者は郊外居住の傾向が強く、車依存度が高いため整備費もかさみます。逆に給与住宅や公営住宅では都市部居住者が多く、車不要の生活が支出の低さに反映されています。今後は高齢化・都市集中・物価上昇により、整備費支出の二極化が進むと予想されます。
住宅別の自動車整備費
1世帯当りの月間支出
これまでの住宅別の推移
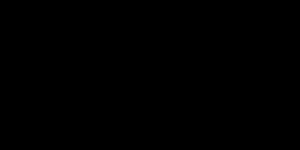
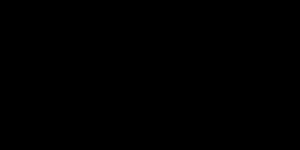
詳細なデータとグラフ
住宅別の現状と今後
日本の家計における自動車整備費は、居住する住宅の形態によっても大きく異なります。2025年3月時点のデータでは、全体の平均が月間3659円であるのに対し、住宅ローン付き持ち家では4997円、給与住宅では1909円と2倍以上の開きが見られます。本稿ではこの住宅別支出の実態を分析し、背景となる生活スタイル、車利用環境、今後の動向などを解説します。
住宅別の支出ランキングと増減傾向
住宅形態別の自動車整備費(月間)の支出状況と増減率は以下のとおりです。
| 住宅形態 | 月額整備費 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 持ち家(ローンあり) | 4997円 | +14.74% |
| 持ち家(ローンなし) | 4906円 | +9.46% |
| その他 | 4431円 | -28.72% |
| 民営賃貸 | 3782円 | +59.38% |
| 都市再生機構・公社等 | 2444円 | +28.23% |
| 公営住宅 | 2106円 | +22.73% |
| 給与住宅 | 1909円 | -43.84% |
このように住宅所有者の支出が高く、特に持ち家勢が突出しています。
住宅所有者の車依存傾向
郊外居住による自家用車必要性
持ち家世帯は都市部よりも郊外や地方に多く、日常生活における移動手段として自動車が不可欠です。通勤・通学・買い物すべてが車に依存するケースが多く、その使用頻度の高さが整備費の上昇に直結しています。
車両保有台数の多さ
複数人の通勤・通学ニーズを支えるため、1世帯で2台以上所有しているケースも多く、その分整備費もかさみやすくなっています。
民営・公的賃貸住宅の違い
民営住宅(民間アパート等)
民営住宅に住む人々の整備費が大幅に増加(+59.38%)しているのは、居住地が郊外型へシフトしていることや、若年~中年層が車を主な交通手段として利用している傾向があるためと考えられます。
公営住宅・給与住宅
公営住宅や給与住宅に住む人々は整備費が最も低く、特に給与住宅では前年比-43.84%という大幅な減少が見られます。これらは公共交通が発達した都市部に集中しており、自動車を保有しないか、最低限しか使わない世帯が多いとみられます。
「その他」住宅の減少理由とは
「その他」に分類される住宅(例えば親族宅に居住、定住せず複数拠点を持つなど)は、支出が-28.72%と大きく減少しています。流動的な生活を送る人々にとっては、自動車の維持が負担となり、車の保有自体を見直している可能性が高いといえます。
今後の予測と課題
高齢化と車の役割の変化
高齢者世帯が今後増える中、都市部居住で公共交通を活用する傾向が強まり、公的住宅の整備費支出はさらに低下する可能性があります。
地方と都市の整備費格差
1方、地方の持ち家世帯では自動車依存が進行し続け、維持・修理費の高騰が家計を圧迫するリスクも。部品価格や整備人件費の高騰が加われば、年率10%前後の上昇も想定されます。
EV化と整備費の構造変化
将来的には電気自動車の普及により、整備内容そのものが変化し、オイル交換やエンジン周辺整備が不要になる1方で、バッテリーや電装系の高額な交換コストが新たな課題として浮上するでしょう。
政策対応と家計管理の視点
-
整備費補助制度の地域別導入:郊外居住者や高齢者の車維持費を支援。
-
都市部のカーシェア推進:低所得層や賃貸居住者に向けた選択肢の拡充。
-
持ち家取得支援とセットでの車支出対策:新築取得と同時に自動車維持支援制度を組み込むことで、家計全体の健全化を図る。
まとめ
住宅形態による自動車整備費の違いは、地域性・生活様式・所得水準などと密接に関連しています。特に住宅を所有する郊外型世帯の負担は今後さらに増す可能性があり、公共施策・企業側の対応・家庭の選択によって、その支出構造は大きく変わっていくでしょう。住宅政策と交通政策は、今後ますます連動した設計が求められる時代に入っています。




コメント