腕時計の世帯別月間支出は、2025年3月時点で平均302.2円と推移しており、特に世帯人数が多い家庭(5人・6人以上)で支出が高い傾向にあります。前年同期比では世帯5人で252.3%の増加と顕著な伸びを示す一方、就業者数0人の世帯や小規模世帯では支出が急減しています。家族構成や就業状況によって腕時計への支出動機が異なり、今後も多人数世帯や共働き家庭を中心に一定の支出が維持されると予測されます。
世帯別の腕時計
1世帯当りの月間使用料
これまでの世帯別の推移
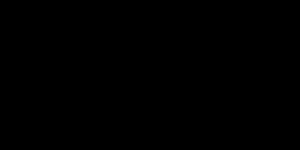
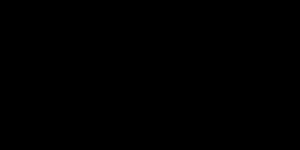
詳細なデータとグラフ
世帯別の現状と今後
2021年から2025年3月にかけてのデータによると、日本における1世帯あたりの腕時計の月間支出は平均302.2円に達しています。これは過去の数値と比較して高めの水準であり、特に世帯人数や就業状況が支出額に大きく影響していることが明らかです。中でも世帯5人では613円、世帯6人以上でも419円と大きな支出がみられ、逆に就業者が0人の世帯ではわずか56円に留まっています。こうした偏差は、腕時計が生活必需品というよりも、ファッション性やプレゼント需要によって購入が左右されることを物語っています。
世帯構成別の支出傾向
多人数世帯(5人・6人以上)
支出額が最も高いのは5人世帯で613円、前年比252.3%の急増を記録しています。多人数世帯では、進学や就職などのライフイベントが重なりやすく、腕時計を贈り物や実用品として購入する機会が増えると考えられます。6人以上の世帯も419円と高水準を保っており、こちらも家族のライフサイクルに伴う消費が主因と見られます。
中規模世帯(3〜4人)
1方で、3人・4人世帯はそれぞれ210円・204円と平均を下回り、前年比も大幅な減少(-61.4%、-53.42%)を記録しています。この背景には、コロナ後の消費抑制や、家計全体での節約傾向があると考えられます。特に中間層での生活防衛意識が強まり、贅沢品と見なされやすい腕時計の購入は控えられた可能性があります。
小規模世帯(2人)
世帯2人では302円とほぼ平均並みですが、前年比では-20.32%と減少しています。夫婦のみや高齢者世帯が中心となるこの層では、スマートフォンで時間を確認する習慣の定着や、腕時計の実用性の低下が影響していると考えられます。
就業者数と支出の関係
就業者2人の世帯は412円と高めの水準を維持しており、前年からもわずかに増加(+2.743%)しています。共働きで経済的に余裕のある家庭では、腕時計がビジネスアイテムやファッションの1部として選ばれていることがうかがえます。
1方、就業者1人では220円、0人では56円と大幅に低下しています。特に0人世帯は前年比で-88.57%と急落しており、無職世帯や年金暮らしの高齢世帯での支出余力の限界を示しているといえます。
今後の支出傾向の予測
今後も腕時計市場は2極化が進むと予想されます。ひとつは、収入の安定した多人数世帯・共働き世帯が支出を維持する層。もうひとつは、スマートフォンやスマートウォッチの普及により腕時計そのものの需要が減少する層です。前者においては、プレゼント需要やブランド時計志向が支出を支え、後者では実用的ニーズの低下が支出縮小に拍車をかけるでしょう。
加えて、若年層の間で「腕時計=ステータス」という価値観が薄れつつあり、装飾品としての腕時計の役割はより限定的になっていく可能性もあります。
まとめ
世帯構成や就業状況は、腕時計への支出に大きな影響を及ぼしています。多人数世帯や就業者が多い家庭では、生活イベントやファッション性の観点から支出が活発である1方、単身や無職世帯では生活必需品以外の消費は厳しく抑制されている現状です。今後は社会構造の変化とテクノロジーの進展が、腕時計市場に新たな適応を求めることになるでしょう。




コメント