日本の二人以上世帯における肉類支出は増加傾向にあり、2025年3月時点で平均8,233円。京都市や広島市など都市部で高く、地方では節約傾向が目立つ。高齢層と若年層では消費スタイルが異なり、今後は物価上昇と健康志向が支出に影響すると予測される。地域格差の広がりにも注意が必要である。
肉類の家計調査結果
肉類の多い都市
肉類の少ない都市
これまでの肉類の推移
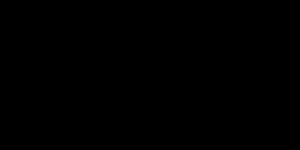
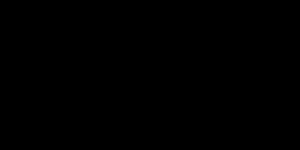
詳細なデータとグラフ
肉類の肉類現状と今後
日本の食生活において肉類の消費は長年にわたり重要な位置を占めており、家計調査における「肉類支出」の動向は、食文化の変遷や地域・世代ごとの生活様式の違いを反映する指標の1つといえます。ここでは、2008年から2025年3月までの調査データを基に、肉類支出の地域別傾向、世代間の違い、そして今後の見通しについて詳細に解説します。
肉類支出の全体的な傾向
2008年以降、日本の2人以上世帯における肉類支出は概ね増加傾向にあります。直近2025年3月のデータでは、全国平均で1世帯あたり月額8,233円と過去と比較して高水準にあります。背景には以下のような要因が考えられます。
-
外食控えによる家庭内調理の増加(特にコロナ禍以降)
-
健康志向の高まりによる鶏肉・赤身肉の人気
-
冷凍食品やミールキットなどの利便性向上
地域ごとの特徴と格差
高支出都市の特徴
上位10都市には、京都市(11,270円)、広島市(10,540円)、奈良市、岡山市、大津市など近畿・中国地方が多く見られます。これらの都市では比較的所得が高く、また高齢化率が中庸で、バランスの取れた消費傾向があると考えられます。京都市に至っては前年比+23.72%と突出した伸びを示しており、観光客の回復や地域ブランド肉(京丹波地鶏など)の影響も背景にあると見られます。
低支出都市の特徴
1方で前橋市(5,934円)や長野市、水戸市、那覇市などは支出額が6,000〜7,000円台にとどまっています。特に福島市(前年比-15.36%)、宇都宮市(-10.58%)などでは前年比で大きく減少しており、地元経済の低迷や物価高による「節約志向」の影響が伺えます。また、長野県のように伝統的に野菜や大豆製品の消費が高い地域では、相対的に肉類支出が抑えられる傾向があります。
世代間の違いとその背景
若年層は鶏むね肉や豚こまなど価格が手頃で調理しやすい部位を選ぶ傾向があり、家庭内での簡便調理を好む傾向が強いです。1方で、高齢層は健康意識が高く、脂肪分の少ない部位や国産品を重視する傾向があります。また、年金生活者などは価格変動に敏感で、価格が上昇するとすぐに支出を抑える傾向も見られます。
今後の予測と課題
今後の肉類支出の推移には以下のような要素が影響を与えると予想されます。
-
物価上昇圧力:輸入飼料価格や円安が続けば、今後も肉類価格は上昇傾向が継続し、消費を圧迫する可能性があります。
-
健康志向の深化:特に都市部で、高たんぱく・低脂肪な食材への需要が伸び、肉類でも鶏肉や赤身肉が主流となるでしょう。
-
地域間格差の拡大:可処分所得の地域差が大きくなるにつれ、肉類支出にもさらなる偏在が生じる可能性があります。
政策的には、家計を支援する物価対策や、国産畜産業への支援も消費傾向に影響を与える要因として注目されます。




コメント