2025年3月までの家計調査によれば、全国平均で1.119万円の特別収入に対し、宮崎市や大分市など地方都市で大きく増加し、逆に大阪市や名古屋市など大都市で減少傾向が目立つ。背景には地方の一時金支給、家族支援制度、地方自治体の政策が関係している。世代間では高齢者世帯の一時的収入が目立つ傾向があり、今後も地域格差は拡大の可能性がある。特別収入は景気変動や行政施策の影響を強く受ける収入項目といえる。
特別収入の家計調査結果
特別収入の多い都市
特別収入の少ない都市
これまでの特別収入の推移
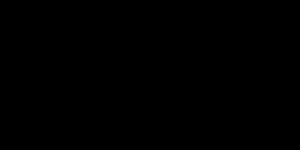

詳細なデータとグラフ
特別収入の現状と今後
家計調査における「特別収入」とは、定常的な給与所得とは別に得られる1時的な臨時収入を指し、具体的には慶弔金、保険金、相続金、災害見舞金、年金以外の給付金、賞金、還付金などが含まれる。毎月の収支に占める割合は小さいが、家計にとっては1時的な資金の補填手段となり、特に中低所得層や高齢者世帯にとっての重要度は高い。
2025年3月時点の特別収入の分布 ― 地域別に見る差異
最新の家計調査(2000年1月〜2025年3月)によると、全国平均の特別収入は1.119万円だが、地域によって著しい差がみられる。
高水準地域(上位10都市):
-
宮崎市(4.422万円):前年同期比+782%という驚異的な伸び
-
大分市(4.185万円)
-
京都市(3.602万円)
-
大津市(2.313万円)
-
広島市(2.196万円)
これらの都市は、地域振興券、災害見舞金、地元企業の従業員への1時金支給、自治体主導の子育て・介護支援金などの影響が考えられる。
低水準地域(下位10都市):
-
高知市(0.23万円)
-
熊本市(0.257万円)
-
鳥取市(0.317万円)
-
横浜市(0.348万円)
-
大阪市(0.363万円)
特に熊本市・鳥取市は前年比マイナス70%以上の急落であり、前年度にあった何らかの1時支給の反動減と考えられる。大阪市や名古屋市などの大都市でも減少しており、大都市部の臨時支給の減少、あるいは家計が特別収入を得られる構造的余地の低下がうかがえる。
世代間格差 ― 高齢世帯と若年世帯で異なる特別収入の内実
高齢世帯では、保険金や相続金、退職金の分割支給などが特別収入として計上されるケースが多く、金額的にも大きくなりがちである。1方、若年層では祝い金や自治体の子育て支援、あるいは副業収入が主となり、安定性・金額ともにばらつきが大きい。
また、支出余力が少ない若年層ほど1時収入の影響を受けやすく、コロナ禍における給付金やプレミアム商品券の効果も1時的に反映されていると考えられる。
なぜ地方都市で急増したのか ― 政策的背景と地場要因
特別収入の急増には、次のような要因がある。
-
地域支援策の影響:宮崎・大分・京都などでは、地域特有の子育て・災害・高齢者支援が1時金として配布された可能性がある。
-
災害復旧関連支出:地震・台風などの被災地域では、国や自治体による給付金、保険金支払いが集中する。
-
地元企業の決算状況:地方の優良企業が利益還元として臨時支給を行うことも。
-
世帯構成の違い:若年単身世帯が多い都市部に対し、3世代同居などが多い地方では贈与や祝い金の受け取りも特別収入に含まれやすい。
大都市部での減少傾向 ― 構造的な問題
大阪市や名古屋市など、いわゆる「3大都市圏」では、特別収入が相対的に低く、かつ前年比で大きく減少している。
-
要因1:給付対象外化の進行:高所得者や単身世帯が多く、支援策の恩恵を受けにくい。
-
要因2:企業側の1時金抑制:インフレやエネルギーコストの上昇で経営が逼迫し、1時的な支給が抑えられている。
-
要因3:家計側の収入変動の不安定化:副業ブームの1方で収入申告を避ける傾向もあり、統計上の数字に現れにくくなっている可能性もある。
今後の予測と展望 ― 地域格差は拡大するか
今後、特別収入は次のような動きを見せると予想される。
-
短期的には、自治体の給付政策次第で上下するが、予算制約から給付金は縮小傾向。
-
中期的には、高齢化と地方移住の増加により、地方での保険金・相続金の増加が続く可能性。
-
都市部では、企業の臨時収入配分は抑制され、特別収入の減少傾向が続く。
-
全体としては、地域格差が拡大し、特別収入は「家計格差の拡大装置」となる懸念もある。
特別収入をどう捉えるか ― 家計管理への示唆
特別収入は偶発的であり、予測不能な側面を持つ。しかしながら、家計管理においては「臨時収入を全額消費に回す」のではなく、貯蓄・ローン返済・投資に回す計画性が求められる。
また、家計調査における特別収入の変化を見ることで、個々の自治体や政府の支援策の方向性を読む指標ともなり得る。今後、政策の変化が可処分所得にどう影響するかを注視していく必要がある。




コメント