2018年から2025年の無職世帯における穀類支出は平均7,787円で、大都市が最も高く8,833円、最も低い小都市Bは6,721円となっている。増加率は全地域で二桁成長だが、小都市間の差異が顕著。収入制約や生活スタイルの違いが消費に影響し、今後は高齢化や経済環境の変化が支出動向に大きな影響を与えると予想される。
穀類(無職)の家計調査結果
穀類(無職)の多い都市
穀類(無職)の少ない都市
これまでの穀類(無職)の推移
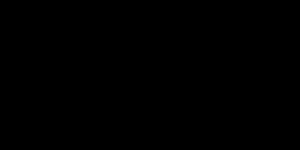
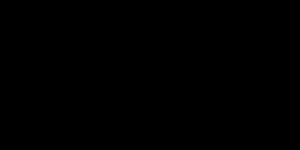
詳細なデータとグラフ
穀類(無職)の穀類現状と今後
無職世帯は、収入が主に年金、貯蓄、扶助金などに依存するため、消費行動は勤労世帯とは異なる傾向があります。穀類支出は、生活費の基本的な部分を占めるため、無職世帯の食生活や経済状況の影響が色濃く反映されます。ここでは2018年1月から2025年3月までのデータを基に分析します。
穀類(無職)の平均支出と地域別比較
2025年3月時点の平均支出は7,787円。地域別では
-
大都市:8,833円(前年同期比+19.75%)
-
全国平均:7,876円(+16.32%)
-
小都市A:7,759円(+20.35%)
-
中都市:7,746円(+12.05%)
-
小都市B:6,721円(+14.15%)
となっており、大都市が突出して高い支出を示しています。逆に小都市Bは最も低額で、約2,100円の差があります。
都市間差の背景と生活スタイルの違い
大都市の高支出理由
大都市は物価水準が高いことに加え、スーパーや店舗の多様化により多様な穀類商品が流通しており、比較的高品質な商品を選ぶ傾向があります。また高齢者が多い無職世帯においても、健康志向の高まりが質の良い穀類購入につながっています。
小都市Bの低支出要因
小都市Bでは物価水準が低い1方で、所得が限定的な無職世帯が多く、節約志向が強いことが想定されます。伝統的に安価な主食を中心に消費しており、新しい穀類商品や加工品の普及が遅れている可能性もあります。
全国平均・中都市・小都市Aの中間的性格
全国平均や中都市、小都市Aは支出水準が似ているものの、小都市Aの増加率が20%超と最も高いことから、生活環境の変化や健康志向の拡大、地元産穀類の消費増加が見られる地域もあることが示唆されます。
過去の動向と課題
2018年以降、無職世帯の穀類支出は緩やかな上昇傾向にあります。これは、食品価格の上昇や健康志向の影響、加えて高齢化による食の多様化が背景にあります。1方で、地域間での価格差や生活習慣の違いが大きく、所得制約が強い無職世帯にとっては経済的負担が増している課題もあります。
世代間の特徴と影響
無職世帯は高齢者世帯が多いため、穀類消費においては健康上の配慮が強い傾向があります。低糖質や雑穀、玄米の需要が高まりつつある1方、嚥下困難などの身体的制約から調理の簡便さを重視した穀類商品も求められています。若年の無職世帯が増える場合は、食費全体の見直しや外食依存も変動要因となります。
今後の推移と予測
-
高齢化の進展により、健康志向穀類の消費拡大は継続。
-
物価上昇に伴う節約志向も並存し、地域間格差が広がる可能性。
-
地方の小都市Bなど低支出地域では消費停滞や減少も懸念される。
-
介護食品や簡便食品の市場拡大が穀類消費の新たな需要を生む。
-
社会保障制度や経済環境の変化が無職世帯の消費パターンに影響を与える。
まとめと政策的示唆
無職世帯の穀類消費は地域格差と世代特性により多様な傾向を示しています。高齢化社会において、健康的で手軽な主食の供給は生活の質向上に直結します。地方の消費低迷を抑え、全国的な食料安定供給や生活支援策を強化することが必要です。地域特性に応じた食品政策や情報発信が今後の課題となります。




コメント