2018年以降の無職世帯における生鮮野菜平均支出は約7,488円。大都市での支出が最も高く8506円、全国平均7555円、中都市や小都市ではやや低い傾向。全体的に前年同期比で増加傾向にあり、特に小都市Aが18.5%増と顕著。経済的余裕や健康志向、地域の食文化が消費に影響。今後は高齢化進展や物価変動が消費パターンに影響し、多様な対応策が必要になる。
生鮮野菜(無職)の家計調査結果
生鮮野菜(無職)の多い都市
生鮮野菜(無職)の少ない都市
これまでの生鮮野菜(無職)の推移
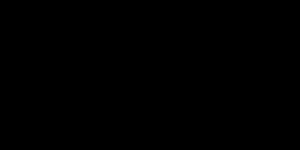
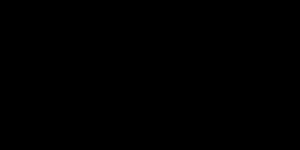
詳細なデータとグラフ
生鮮野菜(無職)の野菜現状と今後
無職世帯は主に高齢者や専業主婦、失業者を含み、収入形態や生活パターンが勤労世帯と異なります。2018年から2025年の家計調査によると、生鮮野菜の平均支出は7,488円と勤労世帯よりやや高く、健康維持や家庭での食事準備の比重が大きいことが反映されています。特に高齢化の進展が生鮮野菜消費に大きな影響を与えています。
都市規模別の支出額と増加率の傾向
支出額のランキング
-
大都市:8,506円(前年同期比+15.38%)
-
全国平均:7,555円(+12.88%)
-
中都市:7,459円(+7.836%)
-
小都市A:7,160円(+18.5%)
-
小都市B:6,761円(+12.1%)
大都市での支出が最も高く、小都市Bが最も低いが、全体として前年からの増加率は全地域でプラスとなっており、特に小都市Aの18.5%増が目立ちます。
増加率の特徴
小都市Aは地域の食材利用の見直しや健康志向の高まり、あるいは地産地消促進による野菜利用増加が影響と推測されます。大都市も高齢者向けサービスの充実や品揃えの多様化で支出増加が続いています。
地域差の背景と要因分析
経済的な余裕と価格の影響
無職世帯は年金など1定の収入源が中心であり、収入の安定性は地域差によって異なります。大都市では生活コストが高いものの、収入水準や補助制度の充実で野菜支出が高くなる傾向があります。小都市では価格変動の影響が大きく、支出に差が出やすいです。
生活スタイルと食習慣の地域性
高齢化が進む地方都市では伝統的な野菜消費が根強い1方で、都市部では多様な野菜商品や健康志向により消費内容が多様化。都市部の無職世帯は宅配サービスや加工野菜利用も増えています。
世代間の特徴と健康志向の影響
無職世帯の中心は高齢者が多く、病気予防や栄養バランスを考えた野菜摂取意識が強まっています。若年の無職者や専業主婦世帯では手軽さ重視の傾向もあり、カット野菜や冷凍野菜の利用が増加。1方で高齢者は新鮮な生野菜を好む傾向があります。
問題点と課題
-
価格の上昇や供給不安定が無職世帯の食費負担を増加させるリスク。
-
地域によっては流通や店舗の不足により野菜の入手が困難な場合もある。
-
高齢者の買い物支援や調理支援の不足が健康リスクにつながる可能性。
-
地方小都市での人口減少により需要が縮小し、販売機会の減少も懸念材料。
今後の推移と展望
-
高齢化のさらなる進展により無職世帯の野菜需要は増加傾向が続く見込み。
-
価格変動に対応するための地産地消や地元農産物の利用促進が重要になる。
-
食事の利便性向上を目指し、加工野菜や宅配サービスの活用がさらに拡大すると予測。
-
健康志向の多様化に対応し、栄養指導や地域福祉との連携が消費拡大の鍵。
まとめ
無職世帯の生鮮野菜消費は2018年以降、都市規模により差がありつつも全体的に増加傾向にあります。大都市は経済的余裕やサービス充実で支出が多く、小都市は地元農産物の活用や健康志向の高まりが増加を促進。今後は高齢化対応や生活支援が消費パターンを左右し、地域間格差の縮小と持続可能な食生活支援が重要課題となります。




コメント