無職世帯の平均有業人員数は0.42人で、親が無職でも同居する子や配偶者が働く実態が見える。地方では三世代同居で高め、大都市圏では単身高齢者で低めとなる。今後は高齢者の継続就労や扶養家族の非正規就業により微増傾向が続くと予測される。
有業人員数の家計調査結果
有業人員数の多い都市
有業人員数の少ない都市
これまでの有業人員数の推移
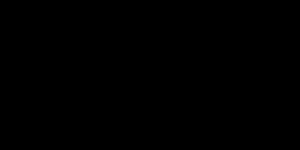
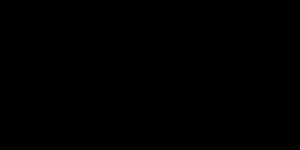
詳細なデータとグラフ
有業人員数の現状と今後
「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯を意味します。このため、同じ世帯に他の家族(配偶者・子・親族など)が就業している場合も含まれることがポイントです。今回の家計調査で示された、全国平均の「0.42人」という数値は、無職世帯であっても世帯当たり平均して約4割に有業者がいることを示しています。
これは、高齢の無職世帯主に対して、子どもや配偶者がパート・アルバイト・フルタイムなどで家計を支えている実態を浮かび上がらせています。
2018年からの有業人員数の推移と変動要因
■2018年〜2020年:微減傾向
-
働き手が少ない高齢世帯の増加により、有業人員数は0.40人前後で推移。
-
高齢の配偶者も仕事を辞め、完全な年金生活に入る例が増加。
■2021年〜2023年:底を打って増加傾向
-
コロナ禍による就労制限・休職・解雇などで1時的に減少。
-
その後、非正規就労の増加や年金不足対策で高齢者や扶養家族が就労に回帰。
-
就職氷河期世代の子どもが親と同居しながら就労している例も増える。
■2024年〜2025年:0.42人に微増
-
賃金上昇の恩恵は1部限定的ながら、就業意欲の回復や副業容認の流れが後押し。
都市ごとの有業人員数の違いと背景
有業人員数が高い都市の特徴
-
地方中核都市や郊外都市(例:浜松市、福山市、前橋市)
-
高齢親と同居する40〜50代が働き手となっている
-
世帯主はリタイア済でも、子ども世代が働き家計を支える
-
地価や家賃が比較的安く、“3世代+α家計”が成り立ちやすい
-
有業人員数が低い都市の特徴
-
都心部やベッドタウン(例:東京23区中心部、神戸市東灘区)
-
高齢単身・夫婦の世帯が多く、完全に年金生活
-
就労者の同居率が低く、世帯内に働き手がいない
-
世代間での有業人員数の違い
高齢夫婦のみの世帯
-
有業人員数は0〜0.1人が多数
-
収入源は年金中心、仕事をしていない
高齢親+就労子世帯
-
有業人員数は1人以上のケースが多い
-
子が非正規やパートで親を支えている
-
「隠れた就労支援」が存在し、統計に出にくい貢献もある
3世代同居型
-
有業人員数が1.5人前後になる例も
-
複数の働き手が家計を分担、就労形態も多様
有業人員数から見える社会課題
年金・生活保護制度とのギャップ
-
年金だけでは足りず、家族の働きで穴埋め
-
本人が無職でも「世帯単位」で収入があると制度利用が制限されるケースあり
就労する若年無職者との同居
-
親が無職で子が働いている「逆転支援」型
-
就職氷河期や非正規雇用層の若者がこの構造に該当
-
世帯内格差・経済的依存構造の固定化が懸念される
働き手の高齢化と就業継続
-
70代での就業も増加しており、有業人員数に反映されるが、身体的・精神的負担も大
今後の見通しと課題
■中期的予測(2030年前後)
-
有業人員数は0.43〜0.45人で横ばいから微増
-
高齢者の“ゆるやかな就業”が増える(短時間勤務、副業等)
-
若年層との同居・扶養関係が維持される限り、1定の有業人員数は維持
-
■注目すべき課題
-
就業の質と安定性の確保
-
無職世帯内の働き手が非正規中心であるため、所得が不安定
-
-
制度の世帯主中心主義の見直し
-
世帯主が無職であっても、実質的な家計担い手がいる世帯への支援策の再構築が必要
-
-
若年層の“隠れ支援者”としての就業の把握と活用
-
同居者の就労状況に応じた施策展開が求められる
-
政策・地域社会・個人に求められる対応
-
政策的対応
-
世帯単位の支援制度を多様な世帯構造に合わせて再設計
-
フレキシブル就労や高齢者雇用のインセンティブ拡大
-
-
地域社会
-
働き手が少ない世帯への生活支援(配食、送迎、医療連携)
-
世代間扶養の支援(親子世帯支援住宅や家賃補助)
-
-
個人・家族
-
退職後も就業継続を視野にライフプランを設計
-
親子・兄弟間での「家計共同体」としての意識共有
-
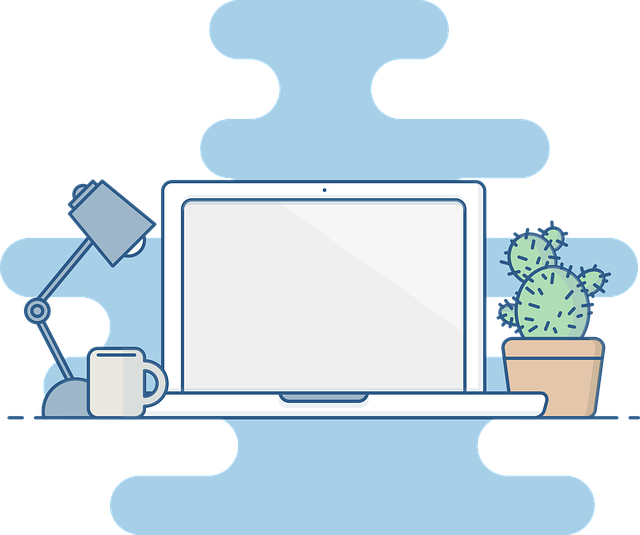



コメント