家計調査のデータによると、2025年3月時点で無職世帯の月間実収入の全国平均は5.471万円であり、都市間で顕著な差が見られます。小都市Bは7.001万円と最も高く、大都市は4.506万円と最も低い水準でした。増減率では中都市の+9.294%が目立ち、小都市Aは-10.17%と大きく減少しています。これらの差異は地域の物価、社会保障、雇用機会、家族構成などの要因に起因しており、今後は高齢化や地方経済の変化によりさらなる格差拡大の懸念があります。
実収入の家計調査結果
実収入の多い都市
実収入の少ない都市
これまでの実収入の推移
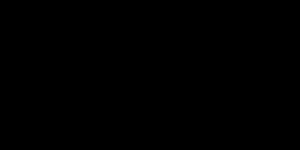
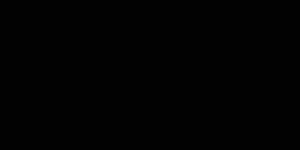
詳細なデータとグラフ
実収入の現状と今後
無職世帯とは、世帯主が就労していない世帯を指し、主に年金、仕送り、事業・内職収入などに頼る構造を持ちます。家計調査では、これらを含めた実収入が「月間収入」として捉えられ、生活の安定性を図る重要な指標となります。
実収入の地域別水準とその背景
2025年3月時点での無職世帯の実収入を見ると、小都市B(7.001万円)が最も高く、大都市(4.506万円)が最も低いという結果が示されています。1般的に都市規模が大きいほど生活費も高く、年金や仕送り収入の実質的価値が下がる傾向にあります。小都市Bの高水準は、地価や生活コストが低いため、仕送りや年金の余裕が出やすい点が考えられます。
前年同期比で見る動向と問題点
前年同期比の増減率では中都市が+9.294%と堅調な伸びを示す1方、小都市Aは-10.17%と大幅に減少しました。これは、地域経済の停滞や企業の撤退、若年層の都市流出による仕送りの減少が影響している可能性があります。また、大都市も-4.394%と減少しており、都市部での物価上昇が年金生活の圧迫要因となっていることがうかがえます。
世代間の違いと生活スタイルの変化
高齢者世帯では、実収入の主たる部分を公的年金が占める1方、同居の子や親族の支援がある世帯では、世帯全体の実収入が相対的に高くなる傾向があります。特に地方では多世代同居が残る地域も多く、都市部に比べて収入安定性が高い場合も見られます。
今後の予測と政策的課題
高齢化が急速に進む中で、年金財源の圧迫や地方の経済停滞は無職世帯の実収入にさらなる影響を与えると予測されます。とくに物価上昇への対応策や、地域ごとの生活支援策の強化が求められます。生活保護や地域福祉サービスの充実がカギとなるでしょう。また、多様な就労形態の導入や内職支援など、年金以外の収入源の創出も政策的に重要になります。
まとめ
無職世帯の実収入は地域差が大きく、生活環境や社会制度に大きく左右されます。地方と都市部での支出構造や家族構成の違い、年金制度の変化などが複雑に絡み合っており、今後の社会保障政策の再設計と地域間格差の是正が喫緊の課題です。持続可能な高齢者支援のあり方が問われています。




コメント