無職世帯の持家率は全国平均で93.8%と非常に高く、特に小都市においては95%を超える水準となっています。これは高齢者層を中心とした無職世帯が長年の住宅ローン返済を終え、持ち家に住んでいるケースが多いためです。一方で中都市では減少傾向が見られ、今後の世代交代や若年層無職者の増加により持家率の低下が予想されます。地域や世代の違いが今後の住宅政策や社会保障に与える影響も無視できません。
持家率の家計調査結果
持家率の多い都市
持家率の少ない都市
これまでの持家率の推移
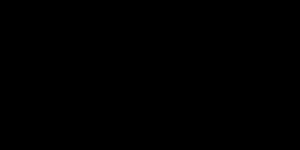
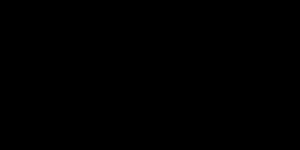
詳細なデータとグラフ
持家率の現状と今後
日本の無職世帯、特に年金生活者を中心とする高齢世帯の多くは、長年のローン返済を終えた持ち家に住んでいます。2025年3月時点での家計調査によると、無職世帯の全国平均持家率は93.8%に達しており、非常に高い水準を維持しています。この数字は、日本の住宅政策やライフスタイル、地域社会の構造を反映している重要な指標といえます。
地域別の傾向
データによると、小都市A(95.3%)、小都市B(94.8%)、大都市(94.3%)と続き、最も持家率が低い中都市でも91.8%と高水準を維持しています。小都市で特に高いのは、土地取得や住宅建築のコストが相対的に低く、早期に持ち家を確保しやすいからです。また、地元に定着する傾向が強く、移動性も低いため、転居の必要が少ない点も影響しています。
1方、大都市でも意外と高い持家率が維持されており、これは都市部での長期勤続によって住宅を取得し、退職後もそのまま住み続ける高齢世帯の存在が多いことが背景にあります。
世代間の違い
無職世帯の多くは高齢者層で構成されており、彼らは「高度経済成長期」「バブル期」を経てマイホームを取得しやすかった世代です。これに対し、今後増加が見込まれる若年~中年の無職世帯(早期離職者や非正規雇用から離脱した人々など)は、そもそも住宅を取得できる経済的基盤が弱いため、将来的にはこの持家率が大きく低下する可能性があります。
社会的・経済的課題
持家率が高いことは安定的な生活基盤を意味する1方で、老朽化住宅や空き家問題と直結しています。特に小都市では人口減少により、相続後に空き家となるケースが増えています。また、持家であっても修繕・維持の費用が負担となり、生活保護や自治体支援に依存するケースも見られます。
今後の予測
持家率は今後、以下の要因によって変動すると考えられます:
-
高齢世代の世帯数減少による自然減
-
若年無職層の増加による持家率低下
-
空き家の利活用や公営住宅政策の進展
-
高齢者向け住み替え支援の有無
特に中都市では前年から持家率が3.5ポイント以上も減少しており、都市部の人口動態や雇用環境の変化が反映されています。
まとめ
無職世帯の持家率は高齢者中心社会の1断面であり、将来の住宅政策や地域社会のあり方を考えるうえで極めて重要な指標です。今後は空き家対策と並行して、持家を前提としない生活基盤整備の必要性も高まるでしょう。都市規模や世代間の違いを丁寧に捉えた対策が求められます。




コメント