無職世帯における女性配偶者の有業率は全国平均で13.7%と上昇傾向にあり、主に60代女性がパートや地域職で家計を支えています。都市部と地方で機会や交通事情により差があり、今後は制度改革と地域支援が鍵となります。
女性配偶者の有業率の家計調査結果
女性配偶者の有業率の多い都市
女性配偶者の有業率の少ない都市
これまでの女性配偶者の有業率の推移
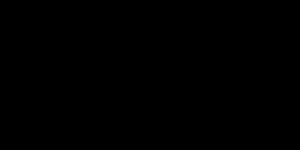
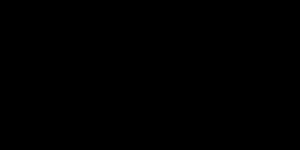
詳細なデータとグラフ
女性配偶者の有業率の現状と今後
「有業率」とは、1定の期間内に何らかの形で働いている者の割合を指します。家計調査での「無職世帯」では、世帯主が就業していない1方で、女性配偶者が就業している世帯を対象にします。この層は、
-
世帯主のリタイア後に妻がパートに出る
-
高齢世帯で妻のみが収入を得ている
-
世帯主の病気・障害等により女性が家計の主軸を担う
といった背景を持ち、いわゆる「家計支援型労働」に該当するケースが多くなります。
有業率13.7%という水準の意味
全国平均で13.7%という有業率は、おおむね7~8世帯に1世帯の割合で女性配偶者が働いていることを示します。この水準は2018年以降、徐々に上昇傾向にありました。背景には:
-
女性の就業機会の多様化(パート・短時間労働・在宅ワーク)
-
公的年金だけでは不十分な家計を補う必要性
-
高齢者雇用の拡充政策(特に地方)
が挙げられます。
都市間の差異と要因分析
有業率の高い都市・低い都市は、以下のような社会インフラや雇用構造に強く依存します。
有業率が高い都市の傾向:
-
中核市・郊外都市(例:浜松、福山、長岡など)
-
製造業や流通業が盛んでパート雇用が多い
-
交通手段が確保されており、高齢女性の移動が容易
-
地域密着型の就労機会(福祉・販売・清掃など)が豊富
有業率が低い都市の傾向:
-
大都市圏の中心部(例:東京23区、大阪市中心部など)
-
高齢化が進んでおり、身体的理由で就労が困難な層が多い
-
高齢単身世帯比率が高く、配偶者がそもそもいないケースも増加
-
交通混雑や雇用形態の高度化により、短時間パートの受け皿が少ない
世代間の違いとジェンダー構造
女性配偶者の有業率は、その年齢・世代によって大きく異なります。
-
60代女性:比較的健康で、夫の定年後にパートに出るケースが多い
-
70代以上の女性:健康状態や介護負担の問題で有業率が急減
-
40代後半〜50代の配偶者(若年無職世帯):経済的困窮により有業率が高まる傾向も
このように、60〜64歳前後がボリュームゾーンであり、ここを中心に有業率が高止まりする傾向があります。
課題と社会的影響
主な課題
-
低賃金の固定化:パートや短時間労働では月収数万円にとどまり、家計全体への影響は限定的
-
ケア責任との両立困難:介護や孫の世話と就労の両立に悩む女性が多い
-
労働環境の地域格差:特に地方では、職種・通勤手段の限界が就労意欲を削ぐ
今後の予測と政策的方向性
2025~2035年の予測
-
有業率は15%前後まで緩やかに上昇すると見込まれる
-
企業の人手不足を背景に高齢女性の採用が進む
-
自治体支援(介護助手、配食サービス、清掃など)による「スモールジョブ」の拡充
-
デジタルスキルの習得支援で、在宅型仕事の裾野が広がる
-
制度的課題
-
年金・扶養制度の「130万円の壁」「106万円の壁」などが就労調整を誘発しており、労働意欲と実労働時間がかみ合っていない
-
高齢女性を対象にした職業訓練やスキルアップ支援が未整備で、労働の質的向上が課題
地域・行政・企業の役割
-
地域:コミュニティベースの雇用創出(例:図書館補助員、学校見守り、地域交通サポートなど)
-
行政:柔軟な就労支援・再訓練制度(高齢女性向けジョブマッチングサービス)
-
企業:60代後半女性を対象にした「柔らかい仕事」の開発と安全対策の徹底




コメント