無職世帯の土地家屋借金返済(住宅ローン返済)は全国平均2321円で、都市別に見ると大都市では3539円、小都市Bではわずか460円と大きな差があります。大都市では返済額が増加する一方、小都市では大幅減少。これは世帯構造や世代交代、相続事情、ローン完済のタイミングなどが影響しています。本稿では2018年以降の動向とその背景、都市間・世代間の違い、そして今後の予測と政策課題を章立てで詳述します。
土地家屋借金返済の家計調査結果
土地家屋借金返済の多い都市
土地家屋借金返済の少ない都市
これまでの土地家屋借金返済の推移
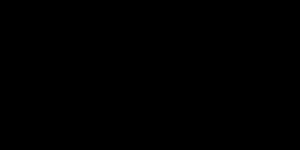
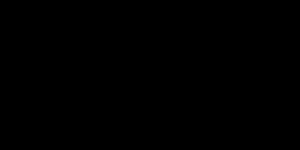
詳細なデータとグラフ
土地家屋借金返済の現状と今後
2025年3月時点で、無職世帯の土地家屋借金返済の全国平均は2321円。この数値は住宅ローンをすでに完済した世帯や、賃貸・公営住宅に住む世帯も含めた無職世帯全体の平均であるため、実際にローン返済を続けている世帯に限れば、実支出額はかなり高いと推察されます。
1般に「無職世帯」とは高齢者世帯が中心であり、年金生活者が多く含まれます。そのため、ローン完済後の持ち家に住むケースが多く、返済中の割合は年々減少してきたと考えられます。
都市別の返済額の格差とその要因
都市別に見た1世帯当たりの返済額(2025年3月時点)は以下の通りです:
-
大都市:3539円(+27.35%)
-
中都市:2567円(+11.27%)
-
小都市A:1909円(-33.48%)
-
小都市B:460円(-55.08%)
このような大きな差の背景には、以下のような要因が関係しています:
大都市の特徴:
-
高齢者の中にも比較的若い高齢層(60代)で、ローン返済中の世帯が残っている。
-
マンションや分譲住宅購入時の借入額が大きく、返済期間が長期化。
-
再雇用終了後のローン返済が続いているケースもあり、返済額は増加傾向。
中都市の特徴:
-
持ち家率は高めだが、大都市より借入額が少なく、完済時期も早い。
-
1部には地方移住者や地方転勤者のローンが残っており、微増傾向が見られる。
小都市A・Bの特徴:
-
相続による持ち家居住が1般的で、ローンを組む世帯自体が少ない。
-
完済者が多く、年齢層も高めでローン支出が発生しにくい。
-
土地家屋の価格が低く、ローンを要さない住宅取得が可能な地域でもある。
前年比から見える動向の変化
前年同期比を見ると、大都市・中都市では返済額が増加しているのに対し、小都市では大幅に減少しています。これは都市の構造と世代交代の影響が大きく関与しています。
増加した都市(大都市・中都市)の背景:
-
ローンの長期化・高額化:都市部ではマンション購入価格が上昇し、ローン返済期間も長くなる傾向。
-
老後も返済が続く生活スタイル:再雇用などで収入がある間に返済を継続し、無職後も支払いが残る。
-
共働き時代の反動:夫婦合算でローンを組み、どちらかが退職して無職世帯化した後も返済は続く。
減少した都市(小都市A・B)の背景:
-
ローン完済が進行:地方ではすでに70歳以上の完済世帯が多く、返済額は急減。
-
土地建物価格の低下や取得方法の多様化:親世代からの相続や格安物件購入など、ローン不要な住宅取得が普及。
-
地域経済の停滞に伴う住宅需要減少:住宅新規取得が減り、新たなローン発生が抑制されている。
世代別の違いと社会構造の変化
返済を続けている無職世帯の多くは60代後半〜70代前半で、団塊世代やその少し下の層です。この層は1980年代〜90年代に住宅を購入し、35年ローンなどの長期返済を選んだ人も多く存在します。
1方、80代以上の世帯では既に完済しており、ローン返済の支出はほぼゼロに近づいています。また、これから高齢化を迎える「団塊ジュニア」や「就職氷河期世代」は、ローンを抱えずに老後に突入する1方、持ち家がないまま高齢期を迎える人も増えると見られています。
今後の推移予測と政策的課題
無職世帯の住宅ローン返済支出は、今後も2極化が進む可能性が高いです。
想定される推移:
-
大都市では今後10年程度はローン返済世帯が1定数残ると予想され、支出平均も高水準を維持。
-
小都市では完済済世帯の割合がさらに高まり、返済支出は縮小し続ける。
-
若年層のローン控えや住宅取得遅れが今後の無職世帯の返済発生を抑制。
政策的な論点:
-
老後にローンが残っている世帯への支援:生活保護世帯の家賃補助制度のように、返済支援も検討課題。
-
住宅ローン免除・圧縮の選択肢:高齢者向けの住宅債務整理策の整備。
-
ローン不要な住宅環境の整備:地方の空き家活用や高齢者向け公営住宅の拡充。
まとめ:無職世帯の住宅ローン支出は時代と共に変化し続ける
住宅ローンの返済は、かつての「定年までに完済」が通用しなくなった現代において、無職期まで継続するケースが現実になっています。大都市圏を中心に、老後の住宅ローン問題は今後の高齢者福祉政策において避けて通れない論点です。
1方、小都市ではローン支出がほぼ消失する1方、住宅の老朽化や修繕費の問題など、別の住宅コストが浮上しつつあります。
これからの時代、「ローン完済=安定」ではなく、どのような住宅で老後を過ごすか、持続可能な住宅政策とは何かがますます重要になるでしょう。




コメント