2025年3月時点の家計調査によると、無職世帯の「受取」は全国平均で49.96万円となり、前年から増加傾向が見られます。中都市が最も高く51.74万円、小都市Bが最も低く48.05万円でした。都市によって年金や一時給付の分布、家族からの仕送りなどに差があり、背景には世帯構成や地域経済の影響があります。今後は、物価上昇や年金制度の改定によって地域間格差の拡大も懸念され、生活支援制度の充実が課題です。
受取の家計調査結果
受取の多い都市
受取の少ない都市
これまでの受取の推移
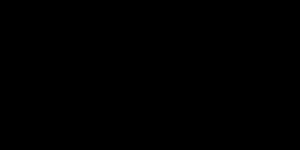
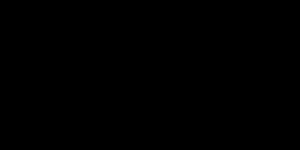
詳細なデータとグラフ
受取の現状と今後
「受取」とは、無職世帯が1ヶ月間に得た臨時的・継続的な現金収入を指し、主に以下の項目で構成されます:
-
公的年金(基礎年金・厚生年金など)
-
1時給付金(特別定額給付、医療・介護費助成など)
-
家族・親族からの仕送り
-
保険金や退職金の分割受取など
就労による所得がない世帯にとって、この「受取」は生活の支柱であり、月次の家計維持だけでなく、将来的な貯蓄や医療費の備えにもつながる重要な収入源です。
全国平均の動向とその背景
2025年3月時点の全国平均「受取」は49.96万円。これは過去数年と比較してもやや高めの水準であり、特に2020~2022年の給付金政策の影響を除けば、堅調な推移といえます。
主な背景は以下の通りです:
-
物価上昇に伴う年金額の名目調整
-
高齢者世帯に対する福祉給付の強化
-
地域によっては支援金や地域通貨の現金化が増加
ただし、年金の実質価値はインフレに追いついておらず、「受取」増にもかかわらず生活実感としての余裕は乏しいとされます。
都市別の「受取」額と傾向
都市別 受取額(最新)
-
中都市:51.74万円
-
小都市A:50.25万円
-
大都市:48.8万円
-
小都市B:48.05万円
前年同期比 増減率
-
小都市A:+16.09%
-
小都市B:+14.51%
-
中都市:+2.016%
-
大都市:-1.592%
中都市がトップである理由は、地方公務員や企業退職者が多く、厚生年金や企業年金が安定的に支給されている層が多いことにあります。逆に大都市では受取額が減少傾向にありますが、その背景には単身高齢者の増加や、物価高による生活保護層の比率増加があると推察されます。
小都市AとBでは受取の改善が目立ちます。これは、地元自治体による高齢者支援策の強化や、子ども世代からの送金の増加、地元企業による退職金の1部支給などが1因と考えられます。
世代構造と「受取」の性質の違い
無職世帯の「受取」は、基本的に高齢世帯の構成が中心ですが、60代前半と80代以上では性質が大きく異なります。
-
60~70代前半:
-
厚生年金が中心
-
企業年金や確定拠出年金(DC)が加わる世帯も
-
まだ貯蓄が比較的厚い
-
-
80代以上:
-
国民年金主体、受取額が少なめ
-
医療・介護負担増加により実質可処分所得が少ない
-
子どもからの仕送りが家計に占める比重が大きい
-
この世代差は都市間の差にも直結します。たとえば大都市は高齢単身世帯が多く、厚生年金未加入の元自営業者や女性単独世帯が目立ち、受取額が低くなる傾向にあります。
今後の動向と政策的課題
今後、「受取」の動向には以下の変数が影響を与えると考えられます:
-
年金改定の動向:
-
マクロ経済スライドにより年金支給額が抑制傾向にある
-
現役世代とのバランス維持のため、実質減少のリスク
-
-
地域差の拡大:
-
住民サービスが充実している自治体(例:給付金や医療補助の厚い都市)では受取の維持が可能
-
1方、財政難にあえぐ自治体では支援が先細りする懸念
-
-
インフレ圧力の影響:
-
表面的な「受取」の増加があっても、実質購買力は下がる可能性あり
-
特に地方での物価上昇が急な場合、支援策で対応しきれない層が拡大する
-
-
世帯構成の変化:
-
単身高齢世帯が全国的に増加傾向で、家族からの支援が期待しにくい
-
結果として受取の「実態」は都市ごとの家族構造に依存
-
まとめ
無職世帯にとっての「受取」は生活の生命線ともいえる収入項目です。現在は全国平均で約50万円と安定していますが、その中身は都市や世帯によって大きく異なりつつあります。今後は、公的支援の制度設計に加えて、地域社会による支援のあり方、そして家族間のつながりが1層重要となっていくでしょう。都市間・世代間格差をどう埋めるかが、日本の高齢化社会の核心的課題といえます。




コメント