2018年以降の無職世帯の果物支出は、2025年3月時点で平均4,302円。大都市が最も高く、小都市Bは最も低い。増加率では小都市Aが20.66%と著しく伸びている一方、小都市Bは微減。無職世帯の果物支出は都市規模や地域性、生活環境の影響を強く受けており、健康志向や余暇の充実志向が購買行動に影響。今後は高齢化進展に伴う消費パターンの変化や地域間格差の拡大が予想される。
果物(無職)の家計調査結果
果物(無職)の多い都市
果物(無職)の少ない都市
これまでの果物(無職)の推移
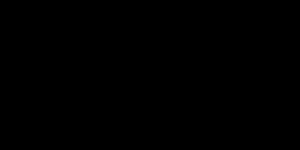
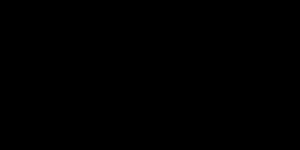
詳細なデータとグラフ
果物(無職)の果物現状と今後
2018年1月から2025年3月までの家計調査に基づくと、無職世帯における果物支出の平均は4,302円に達しています。勤労世帯と比べても高い水準であり、これは無職世帯に含まれる高齢者世帯の果物への支出の重視が背景にあると考えられます。特に健康維持や生活の質向上を目的とした果物の需要が高いことが要因です。
全体としては、都市規模別で大都市が最も果物支出が高く(4,747円)、小都市Bが最も低い(3,335円)という明確な地域差が確認されます。
都市別支出額と増加率の特徴
都市規模別にみると、以下のように支出額と増加率に特徴があります。
-
大都市:支出額4,747円、前年同期比+8.06%
-
小都市A:4,527円、+20.66%
-
中都市:4,514円、+13.25%
-
全国平均:4,386円、+11.15%
-
小都市B:3,335円、-0.66%
この中で特に注目すべきは、小都市Aの20.66%という大幅な増加率です。地域によっては高齢者の生活スタイルや余暇活動の充実、果物を使った健康習慣の浸透が進んでいる可能性があり、これが支出増加に繋がっていると考えられます。
1方、小都市Bは微減傾向であり、人口減少や所得の停滞、地元産果物の価格変動などが消費にブレーキをかけていることが推察されます。
都市間格差の背景と生活環境
無職世帯の果物消費の地域差は、所得格差や生活スタイルの違いに起因します。大都市では利便性が高く、多種多様な果物が購入可能であることに加え、健康志向や食文化の多様化が果物消費を後押ししています。
中都市・小都市Aでは、地域コミュニティの充実や農産物直売所の活用、地方自治体による健康促進キャンペーンの効果も見逃せません。これに対して小都市Bは、経済的な制約や高齢化の進行が消費抑制の要因となっていると考えられます。
世代間の果物消費傾向
無職世帯の中でも多くを占める高齢者層は、健康維持のために果物を積極的に摂取する傾向が強いです。特に糖尿病予防やビタミン補給を意識した果物の消費は1定の支持を得ています。
また、高齢者層は食材選びに慎重で、品質や鮮度を重視しやすいため、価格が多少高くても安全・安心な国産果物を選択する傾向が見られます。これは都市部での支出が高い1因でもあります。
1方で、70歳以下の無職世帯(退職後の比較的若年層)では、余暇時間の増加に伴う趣味や嗜好として果物消費が拡大し、増加率の高い小都市Aの動向に表れている可能性があります。
今後の推移予測と課題
今後は日本社会の高齢化がさらに進むため、無職世帯の果物需要は基本的に増加傾向をたどると予想されます。ただし、地域間の所得格差や人口動態の違いによる格差拡大も懸念されます。
特に小都市Bのような地域では人口減少や高齢者の購買力低下が課題となり、果物消費の減少が進む可能性が高いです。1方、大都市や小都市Aのように健康志向や余暇充実志向が強い地域では、高品質な果物の需要が増え続けるでしょう。
これに伴い、流通業者や自治体は、消費者のニーズに応じた果物の提供形態(小分け、加工品、利便性の高い品種)や価格調整、健康啓発活動を強化することが求められます。




コメント