家計調査から見える果物加工品の支出は、地域ごとの嗜好性や高齢化の影響、価格変動、観光地特性が色濃く反映されている。長野市や宮崎市では支出が急増する一方、高知や徳島では半減するなど、二極化が進む。加工食品の選好は世代間で異なり、今後は健康志向の高まりと単身高齢者の増加が需要に影響を与えると予想される。
果物加工品の家計調査結果
果物加工品の多い都市
果物加工品の少ない都市
これまでの果物加工品の推移
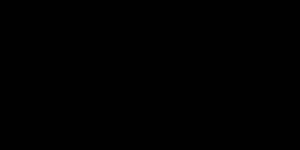
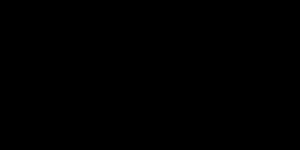
詳細なデータとグラフ
果物加工品の果物現状と今後
果物加工品とは、ジャム、缶詰、ドライフルーツ、ゼリー、フルーツソースなど、生の果物を加工した食品を指す。保存性や利便性の高さから、多忙な現代の家庭では1定の需要を保ってきたが、健康志向や食生活の変化により、消費傾向は年々揺れ動いている。
全国平均と長期的な推移
2008年から2025年3月までのデータによると、全国平均は345.2円と、生鮮果物(3016円)に比べると圧倒的に低い。これは、果物加工品が嗜好品や補助的食品としての立場にあることを示している。また、2020年前後のコロナ禍では在宅時間の増加によって1時的に需要が高まったものの、現在は落ち着きを見せつつある。
地域差が示す消費の特徴
高支出都市の特徴
長野市(640円)、宮崎市(602円)、大津市(512円)などは果物の産地であり、地元の果実を使った加工品が流通している傾向が強い。長野や山形はドライフルーツやジャム、ゼリー文化が根付いており、健康志向の中高年や観光土産としての消費も後押ししている。宮崎市のように温暖な気候で南国果物が豊富な地域では、ジュースや冷凍フルーツの加工も1般家庭に広まっていると考えられる。
また、京都市や東京都区部など大都市圏では、多様な商品ラインナップとマーケティングによって比較的支出が高くなる傾向もある。
低支出都市の特徴
高知市(107円)や徳島市(188円)は、前年同期比でそれぞれ約-49〜51%と大幅な減少が見られる。これは、地元で生鮮果物が手に入りやすいため加工品の需要が少ない、または高齢化と所得低下により支出そのものが減っている可能性が高い。地方都市では「加工品より生で食べたい」という根強い文化が存在している1方で、加工品への依存度が低く価格変動の影響を受けやすい点もある。
世代間の嗜好の違い
若年層は朝食にジャムを使わず、スムージーなどの新しい果物の摂取スタイルに移行している。1方、高齢層では「食べやすくて消化に良い」ゼリーや缶詰などの加工品が重宝される傾向がある。したがって、人口の高齢化が進む地域では、果物加工品への支出が今後も1定の水準で維持されると予測される。
物価と市場価格の影響
近年のインフレと原材料価格の高騰も加工品の価格上昇に影響している。特に輸入果物を使った製品は、為替や物流コストの影響を受けやすく、価格転嫁によって消費者が手を引く例も見られる。その1方で、国内果物の過剰生産分を活用した地場産加工品は価格競争力があり、地元支出の増加に寄与している。
今後の予測と課題
-
健康志向の高まり今後は砂糖不使用・低カロリーの果物加工品が主流になり、高齢世代や糖質制限をしている層に支持される製品が伸びると予想される。
-
地産地消と観光土産としての役割特に観光地では、果物加工品が地元ブランドの柱として機能しており、観光復活とともに消費も伸びる可能性が高い。
-
都市間格差の拡大高所得・健康志向の都市部では消費が拡大する1方で、低所得・人口減少地域では消費低迷が続き、格差は拡大する恐れがある。
-
販路の変化とEC化スーパーや直売所での購入に加えて、ECサイトや定期配送サービスの利用が進むと、より価格帯や商品選定にシビアな動きが加速する。
まとめ
果物加工品の消費は、単なる嗜好や価格だけでなく、都市の性格、世代構成、産地との関係性、観光、健康意識、そして物価情勢という複合的な要因によって形成されている。今後は、人口構造と健康意識の変化を見据えた商品開発と販売戦略が、各地域における支出金額の推移を大きく左右していくことになるだろう。




コメント