2025年3月時点の家計調査によると、勤労世帯における全国平均の有業人員数は1.77人である。都市別では津市や富山市が高く、宮崎市や那覇市が低い水準を示す。地方都市では共働きが一般的な一方、大都市では単身や核家族化が進み有業人員数が減少傾向にある。都市間や世代間のライフスタイル、産業構造の違いが影響しており、今後は高齢化の進展とともにさらなる変化が予想される。
有業人員数の家計調査結果
有業人員数の多い都市
有業人員数の少ない都市
これまでの有業人員数の推移
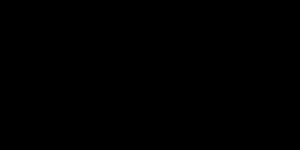
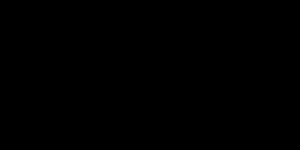
詳細なデータとグラフ
有業人員数の現状と今後
有業人員数とは、世帯内で就業している人の人数を示す統計指標であり、世帯の経済的自立度や就労構造を反映する基本的なデータである。家計調査においては「勤労世帯」の枠組みで、主に夫婦、子ども、または他の同居家族の就業状況を集計する。近年では、共働き世帯や高齢者の再就業、単身世帯の増加など、社会構造の変化が有業人員数に強く影響している。
長期的な推移と全国平均の背景
2000年から2025年にかけての有業人員数の推移を見ると、全国平均は緩やかに減少し、2025年3月時点で1.77人となっている。これは以下のような要因が影響している:
-
核家族・単身世帯の増加
-
高齢化による引退者の増加
-
若年層の非正規雇用比率の上昇
-
女性の就業率は上昇傾向だが、非正規が多く時間制限あり
この全国平均は、かつての「夫婦+子2人」のモデル世帯が少なくなり、1人または2人で就労する構成が主流となった結果といえる。
都市ごとの有業人員数の特徴
高い都市(津市・富山市・千葉市など)
これらの都市の共通点として:
-
共働き文化の浸透(特に地方都市)
-
自動車依存社会による通勤利便性と地価の安さ
-
地場産業や中小企業の就労機会が豊富
-
若年層の世帯構成が中心、または3世代同居も1定数存在
例えば、富山市(2.03人)は前年から+12.78%と大幅な増加。これは女性就労支援策の効果や地場企業の採用意欲の高さといった地域政策も寄与している可能性がある。
低い都市(宮崎市・那覇市・岡山市など)
1方で有業人員数が低い都市には以下の傾向が見られる:
-
高齢化率が高く、就業者が減少
-
単身高齢世帯や夫婦のみ世帯の増加
-
地域経済の縮小傾向と就労機会の減少
-
都市部ではDINKs(子なし共働き)や単身層の割合増加
東京都区部(1.71人)や横浜市(1.66人)は、生活利便性の高さゆえに単身層が集まりやすく、有業人員数は自然と抑えられる。岡山市の-14.66%という大幅な減少は、都市の高齢化や若年層の転出が1因と考えられる。
世代間・ライフステージによる違い
有業人員数は、世帯主の年齢や子育て期か否かによって大きく異なる。
-
30~40代:共働き傾向が強く、有業人員数が高い(2人前後)
-
50代後半以降:退職・介護・健康問題により減少傾向
-
単身若年層(20代):1人就業が基本、転職活動中や非正規も多い
-
高齢世帯(70代以上):再就職率が限られ、1人未満のケースも
つまり、「誰と住んでいるか」「どのライフステージにあるか」によって世帯内の働き手の数が規定される。
今後の予測と政策的課題
今後、有業人員数の全国平均が大きく増加する可能性は低い。以下の点が鍵となる:
-
高齢者就業の推進(70代でも就業可能な職場環境の整備)
-
若年層の地元定着策(Uターン・Iターン就職支援)
-
テレワークの拡充による地方移住の促進
-
保育・介護インフラの整備による女性就業支援
都市別の格差は今後も広がる可能性があり、「共働きしやすい街」と「高齢単身が多い街」との2極化が進むと予想される。将来的には、有業人員数1.5人以下の地域が増える1方、地方中核都市では2人超を維持する地域もあり得る。
まとめ
有業人員数は、単なる統計ではなく、都市の雇用環境や人口構造、世帯の生き方を映し出す指標である。現代日本では、単身化・高齢化・非正規就労の進行が背景にあり、多様な働き方と暮らし方を支える制度設計が求められている。今後もこの数値の変化を注視し、地域ごとの政策対応が重要になるだろう。




コメント