家計調査における有業人員数は、2025年3月時点で全国平均1.33人と、緩やかな減少傾向にあります。地方都市では複数就業者を持つ世帯が多い一方、都市部では高齢化や単身世帯の増加により就業者が減少しています。とくに横浜市や堺市などの減少幅が顕著です。就業環境や世代構成の違いが地域間格差に影響を与えており、今後はリタイア世代の増加と共働き世帯の構造変化により、更なる変動が予測されます。
有業人員数の家計調査結果
有業人員数の多い都市
有業人員数の少ない都市
これまでの有業人員数の推移
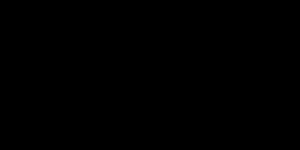
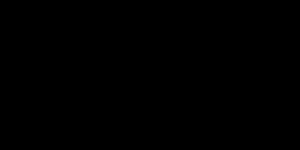
詳細なデータとグラフ
有業人員数の現状と今後
有業人員数とは、調査対象の世帯(2人以上世帯)において収入を伴う仕事に就いている人数を示します。これは世帯の所得構造や生活力、就業形態を反映する重要な指標であり、家計の自立性や地域経済との関係性を理解する上で不可欠な視点です。
全国平均と長期的推移
2008年から2025年にかけて、有業人員数の全国平均は1.4人前後で推移し、最新では1.33人に低下しています。この背景には、高齢化の進行や退職世代の増加、非正規雇用者や無職者の増加があり、世帯における就業者数が徐々に減る構造的要因が働いています。
有業人員数が多い都市の特徴
鳥取市、高知市、高松市、金沢市など、有業人員数が多い都市では、以下のような特徴が見られます:
-
高齢化の進行が緩やかで、就業継続年齢が比較的高い
-
家族単位での就業意識が強い(配偶者や成人子どもも働いている)
-
地元中小企業や自営業の割合が高いため、世帯内に複数の労働者がいる構造
とくに高松市の+25.2%、広島市の+13.08%などは、働き手を家庭内で複数確保する必要性や地域雇用の安定化が反映された結果と考えられます。
有業人員数が少ない都市の特徴
1方、長崎市(1.01人)、横浜市(1.03人)、堺市(1.07人)など、都市部で有業人員数が低い理由には以下が挙げられます:
-
高齢者世帯が多い(リタイア世代中心)
-
単身世帯や高齢夫婦のみ世帯が多い
-
大都市の中流以上層では専業主婦世帯が根強く残っている地域も
-
大分市や宮崎市のように若者の流出で就業世代が減少
特に横浜市や堺市の大幅減少(-21.37%、-25.17%)は、在宅勤務や定年退職者の増加といった都市型の就業環境の変化も影響しています。
世代・ライフスタイルによる違い
-
若年共働き世帯では有業人員数が2人となることも多く、都市近郊や地方都市で目立ちます。
-
高齢者世帯では就業者がゼロ〜1人となる傾向が強く、全国平均を押し下げています。
-
シングルマザー・父子家庭も就業者1人で構成されることが多く、地域差の要因となります。
今後の見通しと課題
-
高齢化の加速により、有業人員数の全国的な減少傾向は続くと見込まれます。
-
女性の社会進出・共働きの推進により、1部地域では増加も見込まれます。
-
テレワークや副業の拡大により、就業形態の多様化が進む1方で、統計上把握しにくい働き方が増える可能性もあります。
-
地方における人材確保と定着支援が地域格差を縮めるカギになるでしょう。
政策的示唆
今後、労働政策や地域振興策を考えるうえで、以下の視点が重要になります:
-
高齢者の継続雇用支援
-
女性・若者の就労支援と保育環境の整備
-
地域ごとの就業支援ニーズに応じた柔軟な対応
有業人員数の動向は、家計の安定だけでなく、地域社会の活力や持続可能性にも直結しており、注視すべきテーマです。




コメント