日本の旅行関係費はコロナ禍後に回復基調に入り、2025年4月の最新月では平均支出6.151万円となった。地域差が顕著で、東海・北海道・大都市で高く、四国は前年比+80%と急増。一方、九州・沖縄は減少傾向。支出世帯の割合も増加し、今後は観光振興と生活格差の両面からの支援が求められる。
家計調査結果
計(旅行関係費)の相場
計(旅行関係費)支出の世帯割合
計(旅行関係費)の推移
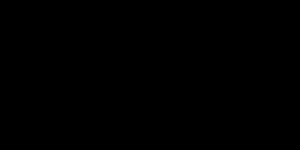
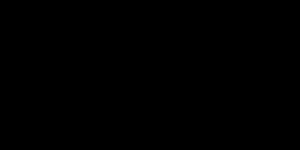
詳細なデータとグラフ
計(旅行関係費)の旅行関係費現状と今後
旅行関係費とは、国内・海外旅行にかかる交通費、宿泊費、観光費、土産物など、旅行に伴う消費全般を指す。これは娯楽消費の1部であり、経済回復や余暇の充実を示す重要な生活指標の1つである。また、地域経済との連動も強く、観光業の活況は地元経済への波及効果も大きい。
2020年以降の支出推移と社会的背景
データの対象である2020年11月から2025年4月は、コロナ禍からアフターコロナへの移行期間にあたる。2020~2021年は外出自粛や観光業の停滞により旅行支出が大幅に落ち込んだが、2022年以降はワクチン普及や旅行支援策(全国旅行支援、自治体のキャンペーンなど)を背景に、旅行関係費は急速に回復基調に入った。最新月の平均支出は6.151万円で、パンデミック以前の水準に近づきつつある。
地域別の支出額と特徴
旅行関係費の支出額を地域別にみると、東海(7.134万円)・北海道(7.128万円)・大都市(7.125万円)が全国平均(6.395万円)を大きく上回っている。これらの地域は観光資源が豊富で、旅行の目的地または出発地としての役割も大きい。また、可処分所得の高い都市部からの移動が活発であることも高支出の1因と考えられる。1方で、小都市A(5.617万円)は平均を大きく下回り、地理的な不便さや所得水準の影響が見られる。
前年同月比から見る回復と格差
前年同月比で支出額の増加がもっとも顕著だったのは4国(+80.51%)である。これは前年が極端に低かった反動に加え、地域プロモーションや旅行需要の回復が重なったと推測される。また、東海(+21.69%)・北海道(+17.02%)のように観光地としての強みを持つ地域では、回復基調がはっきりと表れている。1方、9州・沖縄(-16.26%)のように支出が減少している地域もあり、これは気候変動、災害、航空便の減少、インバウンド偏重など複合的な要因による可能性がある。
支出世帯割合の動向
支出した世帯割合の全国平均は8.64%であり、支出金額の回復に加えて、旅行する世帯自体も徐々に増加していることがわかる。とくに中国(+27.82%)・東海(+16.05%)などの増加率は高く、地域観光の回復が実感される。1方、中都市(-4.53%)・4国(-1.92%)では割合が減少しており、支出額は増えても旅行者層の広がりには地域差があるといえる。
今後の期待と懸念
今後の旅行関係費の推移には、以下のような期待と課題がある。
期待
-
地方創生と観光振興:ローカル観光資源の再評価やデジタル観光の普及により、地方でも高付加価値の旅行が可能に。
-
高齢化社会と余暇志向の融合:シニア層のアクティブ化により、長期・高額旅行の需要が増す。
-
インバウンドとの相乗効果:外国人観光客の回復が国内旅行需要を刺激する。
懸念
-
物価高・燃料費高騰:交通費や宿泊費の上昇により、旅行費用が家計を圧迫する可能性。
-
所得格差と旅行格差:都市部と地方、富裕層と低所得層の旅行機会の格差が広がる恐れ。
-
気候変動や災害リスク:突発的な災害や猛暑が旅行予定に影響を与える可能性。
まとめ
旅行関係費は単なる消費の1要素ではなく、経済・文化・地域振興を反映する重要な指標である。2020年以降の推移を見ても、日本の観光・余暇に対する関心は衰えておらず、今後も安定的な成長が期待される。ただし、地域差と支出層の偏りには注意が必要であり、持続的な観光振興政策と生活支援策の両輪が不可欠である。




コメント