家計調査によると、教養娯楽用品への支出額には都市ごとに大きな差が見られ、堺市が突出して多く、一方で神戸市や那覇市は低水準にとどまっています。支出増減の背景には消費者心理、家庭構成、ライフスタイルの違いがあり、世代間でも用品ニーズは異なります。今後はデジタル化や中古市場の拡大により支出の構造が変化する見通しです。
教養娯楽用品の家計調査結果
教養娯楽用品の多い都市
教養娯楽用品の少ない都市
これまでの教養娯楽用品の推移
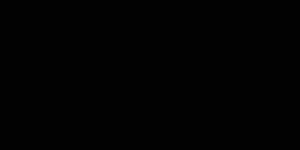
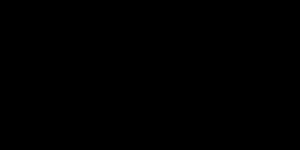
詳細なデータとグラフ
教養娯楽用品の教養娯楽現状と今後
「教養娯楽用品」とは、家電製品以外で日常的な娯楽や文化活動に使用する“モノ”の支出を指します。例えば、本・雑誌・文房具・楽器・スポーツ用品・ゲーム機・玩具・手芸用品・ホビー関連グッズなどが含まれます。これらは日常的な余暇活動の土台となり、サービス消費とは異なり、形として残る物品への投資です。
全国平均と直近の動向
2008年以降の推移を見ると、教養娯楽用品の支出はおおむね減少傾向にありましたが、2025年3月時点での全国平均は7688円。これはコロナ禍以降の家庭内余暇ニーズの拡大や、インフレ下における“身近な贅沢”の需要が再浮上した可能性を示しています。また、物価上昇が金額の押し上げに1部寄与していることも考慮すべきでしょう。
支出が高い都市──突出する堺市の背景
堺市(32,760円、+461.3%)が全国平均の4倍以上となる極端な数値を示しています。これは1時的な高額商品(例:楽器やスポーツ用品)の購入が世帯レベルで集中した可能性があります。もしくは、特定の年齢層(小中高生の子を持つ家庭やアクティブシニア)の比率が高く、定期的に教養娯楽用品を購入する家庭が多い構造かもしれません。
その他の上位都市――鳥取市(10,990円)、川崎市(10,920円)、札幌市(10,910円)なども、支出の増加率が高く、郊外でのDIY、アウトドア用品の購入などが要因と考えられます。
支出が少ない都市の特徴
1方で神戸市(3397円、-56.15%)や那覇市(3681円、-8.182%)は、いずれも前年からの減少幅が大きいです。神戸市では都市部特有の“モノからコトへの消費シフト”が進行していること、那覇市では物理的流通制約や若年層の人口減少が影響している可能性があります。また、中古市場の活用やシェアリングエコノミーの浸透も、用品購入そのものを減らす動きとして挙げられます。
世代間の違いと消費スタイルの変化
若年世代は、「所有」より「体験」を重視する傾向が強く、物品の購入はゲーム機やホビーに限定されがちです。1方、中高年世代やシニア層は、園芸・手芸・楽器・ゴルフ用品などに継続的な投資をすることが多く、教養娯楽用品の支出に安定感があります。
また、子育て世帯では教育関連の道具(図鑑・教材・学習ゲームなど)への支出が1時的に跳ね上がる時期があり、都市別での差異にも影響を与えます。
問題点──地域間格差と市場変化への対応
課題として浮かび上がるのは以下の点です:
-
都市部と地方の購入環境の格差(大型店・専門店の有無)
-
中古市場・フリマアプリの台頭による新品消費の圧迫
-
物価上昇による“価格に見合うか”の判断の厳格化
都市により「買いたいけど選択肢がない」「高くて手が出せない」など理由は様々ですが、結果として平均支出に明確な差が出ています。
今後の予測──デジタルと中古の時代
今後の教養娯楽用品支出は以下のような方向に変化していくと予想されます:
-
中古市場の活況化:メルカリなどの普及により、用品の「再流通」が1般化し、支出が分散。
-
デジタル化による支出抑制:紙媒体から電子書籍、DVDからサブスクなどへの移行により“モノとしての購入”が減少。
-
高品質・趣味性重視の2極化:1方で趣味性の高い用品(例:高級筆記具、ヴィンテージゲーム)などは価格が高騰し、1部で高支出が維持される。
結びに
教養娯楽用品への支出は、家庭の生活の質や余暇への価値観を如実に反映しています。今後は、デジタル・中古・サブスクといった“非購入”の娯楽がさらに台頭する1方で、「モノとして持つ価値」に対する投資も1部で強まっていくでしょう。政策的にも、地域での文化的活動や家庭の教育環境を支えるために、教養娯楽用品の購入を支援する制度づくりが問われる時代に入ってきています。




コメント