2025年4月時点での携帯電話使用料の全国平均は1.336万円で、東北・小都市Bなどで高水準を示す。支出世帯の割合は87%超と高く、通信コストは家計に固定化している。今後は格安プランや5G普及による価格低下に期待が持たれるが、端末代込み契約など課題も残る。
家計調査結果
携帯電話の使用料の相場
携帯電話の使用料支出の世帯割合
携帯電話の使用料の推移
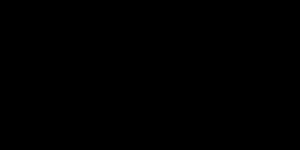
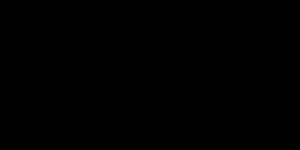
詳細なデータとグラフ
携帯電話の使用料の通信費現状と今後
携帯電話は、もはや現代生活に欠かせないインフラのひとつとなっています。通話やメッセージにとどまらず、インターネット接続、決済、健康管理、教育など多様な機能を担っており、その維持費としての「携帯電話使用料」は世帯支出の中でも高い安定性を持つ支出項目です。2025年4月時点の全国平均支出は1.336万円と高めで、家計における負担の1角をなしています。
地域別の支出額とその背景
地域ごとの支出に目を向けると、東北(1.456万円)、小都市B(1.452万円)、中国(1.415万円)が上位を占めています。これは都市部と比べてインターネットを含む通信手段への依存度が高いことや、家族契約の比率が高いことが1因と考えられます。1方で、関東(1.299万円)や東海(1.299万円)は全国平均をやや下回り、格安SIMや通信費の見直しが進んでいる可能性があります。
月間支出の年間変化と価格推移
前年同月との比較では、全国平均で-0.525%と微減傾向にあります。ただし、中国(+3.753%)、北陸(+3.59%)など1部地域では支出額が増加しています。これは、5Gサービスの普及に伴いデータ使用量が増加したり、高額な機種代金の分割支払いが使用料に含まれているケースがあるためです。
1方、東北(-3.679%)や関東(-1.457%)のように支出が減少している地域では、通信プランの見直しや、MVNO(仮想移動体通信事業者)への乗り換えが進んでいると推察されます。
利用世帯の割合とその特徴
携帯電話使用料を支出している世帯の割合は平均87.57%と非常に高く、全世帯のほとんどが携帯電話に関連する出費を抱えていることがわかります。中でも北海道(90.35%)や4国(89.1%)では9割前後の世帯が支出しており、地方でも携帯電話の普及が進んでいる現状が示されています。
前年比では微増(+0.0841%)となっており、利用率はすでに飽和状態に近いといえるでしょう。
現状の課題と支出構造の変化
最大の課題は、携帯電話使用料が依然として高水準であることです。家族全員で複数台を契約している世帯では、毎月の出費が相当な負担となりえます。政府による料金引き下げ要請や事業者の新料金プラン導入などで平均支出は緩やかに下がりつつありますが、端末代金が使用料に含まれる契約形態が多いため、実質的な負担は減りづらいのが現状です。
また、スマートフォンの高性能化に伴い、通信量の増大=使用料増加という構造が続いており、支出の最適化が困難な状況も見られます。
今後の推移と期待される変化
今後は以下のような変化が予測されます:
-
格安SIMやeSIMの普及により、特に都市部では支出の最適化が進む
-
5Gの完全普及と料金競争の激化により、価格水準がさらに低下する可能性
-
シニア世帯や単身世帯へのスマホ浸透が続くことで、利用率はさらに高止まりする
ただし、高齢者層を中心とした情報弱者へのサポート体制の整備や、契約内容の見直し支援などの施策が不可欠となります。携帯電話はもはや生活必需品であり、そのコスト構造の透明性と公平性が強く求められます。
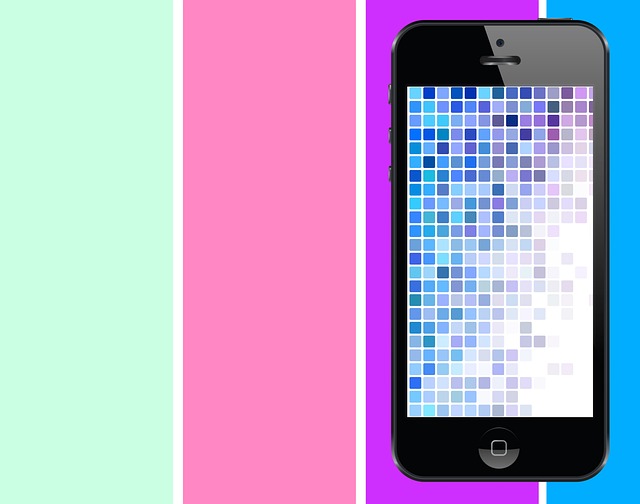



コメント