日本の持家率は全国平均82.6%と高水準を維持しており、都市や世代によって大きな差がある。横浜市や相模原市では9割を超える一方、那覇市などは3割以下にとどまる。若年層では収入や価値観の変化により持家志向が弱まりつつある。今後は地方移住や空き家対策とあわせた住宅政策の見直しが鍵となる。
持家率の家計調査結果
持家率の多い都市
持家率の少ない都市
これまでの持家率の推移
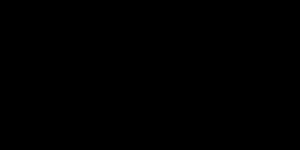
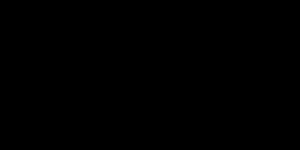
詳細なデータとグラフ
持家率の現状と今後
日本の住宅政策は戦後復興期から「持ち家志向」が強く、特に高度経済成長期には政府による住宅金融支援制度や郊外開発の促進により、持家率は上昇を続けてきました。勤労者世帯においても安定収入を背景に、持家は「1人前の証」として位置付けられ、1990年代までに全国で持家率は約60〜70%に到達しました。その後、バブル崩壊や雇用の流動化、高齢化によって1時的に伸びは鈍化しましたが、直近2025年3月時点での全国平均は82.6%と、依然として高水準を維持しています。
都市間の持家率の特徴
直近データでは、横浜市(97.8%)や相模原市(97.4%)といった首都圏近郊での高持家率が目立ちます。これらの都市は比較的新しい住宅地の開発が進み、郊外型の戸建住宅に住む勤労世帯が多いためです。1方、那覇市(28.9%)や札幌市(62.2%)など、都市構造が賃貸住宅中心であったり、土地取得が困難な地域では持家率が低くとどまっています。
都市ごとの増減を見ると、札幌市(+34.63%)や相模原市(+26.33%)のように大幅に伸びた例もあり、新築分譲や土地価格の落ち着きが影響したと考えられます。1方で、那覇市(-33.41%)や甲府市(-26.28%)のように急減した都市もあり、これは転入人口の変動や賃貸志向の高まりなどが影響している可能性があります。
世代間の意識と課題
若年世代では、非正規雇用の増加や可処分所得の減少、都市部での住宅価格高騰のため、持家取得が困難になってきています。また、価値観の変化により「身軽さ」や「職場近接」などを優先し、賃貸を選ぶ層も増加しています。
1方で、団塊世代やバブル期以降の中高年層はすでに住宅を所有しており、全体の持家率を押し上げる要因となっています。今後これらの世代が高齢化・相続を迎える中で、住宅の空き家化問題が懸念されます。
今後の展望と政策課題
今後、都市部では地価高騰や人口集中により、持家率の伸びは鈍化、あるいは1部減少する可能性があります。反面、地方都市では在宅勤務や移住促進策により、持家の取得が再評価される可能性があります。
政府としては、若年層向けの住宅取得支援やリノベーション支援、空き家活用策の強化が求められます。多様化するライフスタイルに対応した柔軟な住宅政策が今後の焦点となるでしょう。




コメント