役職別では会社役員の支出が3516円と突出し、前年比+3563%。社会的立場や義理文化から高額な祝儀支出が集中。雇用者は支出減、自営業や無職は引き続き低水準。今後は支出の合理化や分散が進み、形式的支出は減少傾向へ。
役職別の挙式・披露宴費用
1世帯当りの月間支出
これまでの役職別の推移
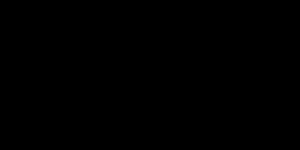
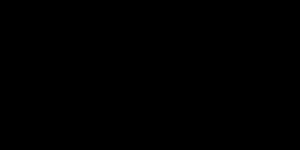
詳細なデータとグラフ
役職別の現状と今後
結婚式や披露宴への出費は、単なる慶事支出ではなく、その人の社会的立場や人間関係の広さ、付き合い方の文化によって大きく異なります。今回のデータでは、役職別平均支出が896.6円である1方、役員は3516円と突出して高額で、他の立場との差が歴然です。これは日本社会における「祝儀文化の階層構造」を象徴する結果ともいえます。
会社役員の支出 ― 義理と責任を背負う「社会的装置」
会社などの役員(3516円)は、前年同期比で+3563%という驚異的な増加を記録しています。この層は、会社経営層・管理職を含むことが多く、社内外の結婚式に3列する機会が多い立場にあります。祝儀金や会費制披露宴の包金額も、その立場に見合う金額が求められるため、1件あたりの支出も大きくなる傾向があります。
コロナ禍による中断期間を経て、2024〜2025年にかけて式が再開されたことにより、役員層の「弾けた支出」が1気に表面化した形です。特に地方企業などでは、役員の結婚式出席は対外関係・社内統治の延長であり、形式的ではあっても礼儀としての支出が不可欠なのです。
雇用されている人 ― 安定しているが、増加圧力は弱い
雇用されている人の支出は428円で、前年同期比-13.36%の減少。これは賃金の伸び悩みや物価高による生活費圧迫の影響であり、祝儀支出を抑える動きが強まっていることが伺えます。企業の雇用者にとって、同僚や後輩の結婚式への出席は依然として多くありますが、社内関係が希薄化しつつある現代では、かつてほど「義理」での出席は強くありません。
また、リモートワークの定着により対面による職場内の絆が薄れたことで、職場を介した人間関係からくる披露宴3加の機会も減少していると考えられます。
無職層 ― 家計制約と社会的距離感
無職の支出は52円で、前年比-1.887%とわずかに減少しています。これは、主に高齢者や専業主婦(夫)を含む層であり、収入が限られる中での自発的な支出抑制が背景にあります。
また、無職層は他人の披露宴に呼ばれる頻度がそもそも低いという点も大きく、支出額が自然と少なくなります。加えて、挙式のスタイル自体が家族婚やフォトウェディング中心となっており、広範な招待者リストから外れる立場でもあります。
自営業主・その他の層 ― 儀礼と個人事業の交差点
自営業主・その他の支出は33円で極めて低く、具体的にはフリーランス、農林水産業、自由業などが該当します。この層は、人付き合いの広さに差があり、業種によっては「冠婚葬祭への出席」を避ける傾向も強く見られます。
また、事業運営に集中する中で、披露宴などの平日開催に時間が割けず、出席を辞退するケースも多くあります。経済的には不安定さを抱える層もあり、「義理や慣習への出費」は極力抑える傾向が強いのです。
今後の見通し ― 支出は1極集中から分散型へ
今後は、役員など1部層への支出集中がやや収束し、雇用者層の支出が持ち直す可能性があります。これは、企業内コミュニケーションの見直しや、新たな冠婚文化(オンライン結婚式・簡易パーティ)の普及によって、形式ばらない支出スタイルが主流になると考えられるからです。
1方で、役員層による祝儀文化は今後も根強く残ると見られますが、企業ガバナンスの観点から交際費の透明化や合理化が進むことで、支出額の「見直し圧力」もかかっていくでしょう。
自営業層や無職層については、引き続き低水準での安定が予想されます。冠婚葬祭への出費は、これまでの「義理の文化」から、「必要と共感に基づいた選択の文化」へとシフトしつつあるのです。




コメント